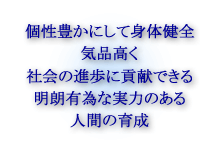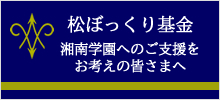シリーズⅡ 「国語力を考える(その3)」
国語成立に向けて -三遊亭円朝と二葉亭四迷、上田万年と言語学、夏目漱石-
 時折、学園中高の図書室に足を運んでいる。司書の方の本に対する造詣が窺える本の選択やレイアウト、さらには適切なカンファレンスは本好きの一人として大いにありがたさを感じている。学校にとって図書室は重要な意味をもっていると考えており、その点、本学園の図書室は、果たすべき役割に十分に応えるものがあり、生徒さらには教職員のさらなる利活用を密かに期待しているところである。
時折、学園中高の図書室に足を運んでいる。司書の方の本に対する造詣が窺える本の選択やレイアウト、さらには適切なカンファレンスは本好きの一人として大いにありがたさを感じている。学校にとって図書室は重要な意味をもっていると考えており、その点、本学園の図書室は、果たすべき役割に十分に応えるものがあり、生徒さらには教職員のさらなる利活用を密かに期待しているところである。
司書の方の指導もあり、生徒会図書委員会の活動も活発になる中、同委員会が「先生のオススメ本」という企画を立て、私にも協力依頼があった。依頼を受け、私がオススメ本の筆頭に挙げたのが井上ひさしの『本の運命』であった。
『本の運命』は、稀代の読書家であり、膨大な蔵書を所有していた井上ひさしが、長年にわたる本との付き合いについて書いた本である。本の中の以下の一節などは忘れ難いものがある。
仙台の高校に入った彼は、先生公認で、一時は映画監督を目指すほど映画館通いに没頭した。やがて、「映画監督の出身大学が『東大か京大』であることを知り、その道を断念した」とは本人の弁である。そこに天啓のようにあらわれたのが、ディケンズの『ディヴィッド・コッパフィールド』であった。「ストーリーとそれを紡ぎ出す言葉が、人間をここまで揺り動かすことができるとは、それまで思ってもみなかった」。それをきっかけ猛烈に本を読み始め、「小説がこれだけ素晴らしいものなら、僕も書いてみたい」と思うようになったという。井上ひさし高校三年の時である。このエピソードのみならず、この本には本好きにはたまらない話が次々に登場してくる。オススメ本の筆頭にあげた由縁である。
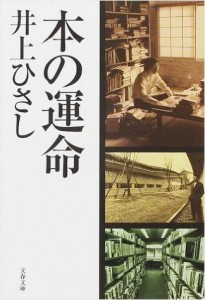 『本の運命』の中に、明治期を代表する落語家三遊亭円朝の話が登場する。
『本の運命』の中に、明治期を代表する落語家三遊亭円朝の話が登場する。
井上ひさしは円朝の全集を読み始めたものの、あまり価値を見出さずその全集を一旦は手放している。その後、「河竹黙阿弥や二葉亭四迷との交友、速記術の普及」、さらに、「口で話す言葉を基に、書き言葉がどのように生まれてきたか、すなわち言文一致体小説の文体の問題」において円朝が重要な役割を果たしていることに気づいていく。神田の古書店で「円朝全集」を買い、読み進めたところ、赤鉛筆で線が引いてある箇所等から、自らが一旦手放した全集であることに気づく。井上ひさしは、「本のほうが僕を執念深く付け回してくる。まるで円朝の噺に出てくる幽霊のようだ(笑)。・・・本は自分で運命を切り開いて行くんですね」とユーモア交じりに語っている。
この箇所を読んだ時、円朝と「速記術」あるいは、円朝と「言文一致体小説の文体」という意味が全く理解できなかった。しかし、山口謡司による上田万年についての本を読む中で、それらのことが、実は、「国語」の確立に影響を与えていることを知ることとなった。

三遊亭円朝
円朝と言文一致体の話に入る前に、まず当時の文体についての話から始めたい。
山口によれば、当時、文体について言えば、「浮世草子」あるいは「源氏物語」にも通じる『和文』、また、大日本帝国憲法にみられる『漢文体』、さらに山口の表現によれば「言葉を写真」にした『言文一致体』があった。加えて、漢文体の変形として、漢文に和語を交えた『雅俗折衷体』があり、鷗外「舞姫」冒頭の「石炭をば早や積み果てつ。中等室の卓のほとりはいと静にて、熾熱燈の光の晴れがましきもやくなし。」はその代表であるとしている。
これらの中で、もっとも分かりやすい文体と言えば、やはり『言文一致体』であろう。
それでは、言文一致体と円朝がどのように結びついているのだろうか。その説明には、まず速記から入る必要がある。
学生時代、親しい友人が学内の速記研究会に入っていた。何度か部室を訪ね、私も少し齧ったとまでは言えないものの、その一端を垣間見たことがある。その程度ではあるものの速記というものに多少親しみのようなものを覚えないでもない。
速記と言えば国会。国会の議事録は速記により記録されてきた。遡れば、明治二十三(1890)年の第一回帝国議会。明治二十三年十二月に制定された貴族院規則第一〇九条には「議事速記録は、速記法に依り議事を記載す」とある(衆議院においても同様の規則が制定された)。当然のことながら、わが国にその時点で速記というものがあったということになる。
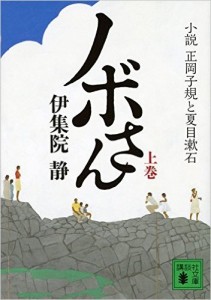 山口によれば、速記と国会を結びつけたのは落語であり、三遊亭円朝であった。名人であり、人気もすこぶる高い円朝。「小説正岡子規と夏目漱石」という副題のある『ノボさん』(伊集院静著)を読むと、主人公子規も漱石も落語が好きでかつ造詣が深く、落語をとおして互いの距離が急速に縮まったことが描かれている。二人とも円朝には一目置いており、さらに他の落語家の時は木戸銭が三銭五厘なのに、円朝は四銭であったことが紹介されるなど、『ノボさん』には円朝の人気の高さが生き生きと描かれている。一言申し添えれば、上田万年も落語が大好きだったという。
山口によれば、速記と国会を結びつけたのは落語であり、三遊亭円朝であった。名人であり、人気もすこぶる高い円朝。「小説正岡子規と夏目漱石」という副題のある『ノボさん』(伊集院静著)を読むと、主人公子規も漱石も落語が好きでかつ造詣が深く、落語をとおして互いの距離が急速に縮まったことが描かれている。二人とも円朝には一目置いており、さらに他の落語家の時は木戸銭が三銭五厘なのに、円朝は四銭であったことが紹介されるなど、『ノボさん』には円朝の人気の高さが生き生きと描かれている。一言申し添えれば、上田万年も落語が大好きだったという。
抜群の人気を誇った円朝の落語、とりわけ円朝と分かち難く結びつく「牡丹灯籠」という高座噺が、明治十七(1884)年に『怪談牡丹灯籠』というタイトルで出版されている。そして、その出版を可能にしたのは速記であった。
わが国の速記は、「明治五(1872)年頃に、田鎖綱紀という人物が独力で発明し、アメリカのグラハム式というものを日本語に応用したもの」とされている。『怪談牡丹灯籠』は、田鎖に速記を学んだ若林玵蔵によって筆記された。速記において、この若林玵蔵なる人物は重要な役割を果たしている。若林は仲間や弟子と募って、僧侶の説教や演説会の演説を速記し腕を伸ばしていったようである。やがて、文部大臣や東京帝国大学総長をつとめた外山正一など有力者の仲立ちもあり、議会の記録に速記が採用されることになった。前述の貴族院(衆議院)規則制定と同時に採用された速記者三十四名は全員若林の弟子だったという。
このように、円朝は速記をとおして議会の議事録に影響を与えたが、一方で小説にも影響を与えている。
言文一致と言えば二葉亭四迷。実は、言文一致体小説の嚆矢とされる『浮雲』誕生にも円朝が関わっているのである。
語学が得意な四迷は、「外国語で書かれた文章には「口語と文語」の区別がない。ならば、日本語でも」と考えたがどう書いてよいか分からない。そこで、坪内逍遥に相談に出かけている。そのときの話を四迷は「余が言文一致の由来」という文章の中で書いている。

二葉亭四迷
四迷は、その忠告に従い完成した作品を持参すると、逍遥から「これでいい。生じっか直したりなんぞせぬ方がいい」という評価を貰うことになる。『浮雲』誕生である。
いわば、円朝のアシストによる二葉亭四迷のゴールとでも言うべきだろうか。まさしく円朝と言文一致体は深くつながっていたのである。
ただし、四迷は、「です、ます」調か、「だ」調かを迷ったり、漢語については、「行儀作法」は使うが「閑雅」は用いない等、国民語の資格を得ているかどうかという原則を自ら立て、漢語の使用不使用を決めるなど、苦労や工夫をしている。さらに、語彙については、式亭三馬の深川言葉を参考にしたと自ら述べている。
「国語」の確立はまだ先の話とはいえ、山口が、「円朝の落語を写しつつ、語彙を三馬に求めるという二葉亭四迷言による言文一致の方法は、読みやすい文章で、ひろく全国に「読者」を開拓した」と述べるように、言文一致が小説の形で創始され、広がりをもつことになったのである。それは四迷自身はおそらく意識しなかったにせよ、「国語」確立に向けての重要な一歩であったことは間違いないように思われる。
ところで、明治時代の初めの頃、当然のことながら、人々は日本語を話し、日本語で手紙や文章を書いていた。しかし、まだ、「国語」は存在していない。
あるいは、当時、わが国においても、世界には英語やロシア語やフランス語さらにはサンスクリット語などがあることは知られており、一定の理解をもつ人々はいたものの、それらの言語をたとえば「日本語」と比較して考えるというようなことは行われていなかったのである。
日常使用されていた日本語が「国語」になるためには、表記や表現、文体について検討が加えられ、ある種の標準形をつくることが必要であり、そして、それは決して容易いことではなかった。すなわち、「国語」を確立するためには、日本語を学問の対象として研究し、諸外国の研究成果を活用しながら、分析し整理をしていく作業が必要であった。そして、その中心にいたのが前号でもふれた上田万年なのである。

上田万年
ここで、上田万年、特に彼の「言語学」研究について話をしておきたい。
万年は、東京帝国大学に入学し、「博く言語について学問する」から来ているとされる「博言学」すなわち「言語学」を学ぶことになる。
万年の「博言学(言語学)」の先生は、バジル・ホール・チェンバレン(1850~1935)。
イギリスに生まれ、母の死でフランスの伯母の家で育ち、ドイツ人の家庭教師に学び、またスペインでも生活しという生い立ち、加えて優れた語学の才能もあり、ラテン語、ギリシア語を含め十一ヶ国語をマスターしていたという人物である。万年は彼の下で研鑽を積むことになるが、「『比較言語学』という学問を我が国に植え、世界の言語とともに『日本語』を研究の対象としていた」偉大な師との出会いは、万年にとってこの上ない幸運であったと言うべきであろう。
チェンバレンは、万年が東大に入学する二年前の明治十六(1883)年、父の死でイギリスに一旦帰国したものの再び戻った日本で、『古事記』の英訳を出版している。その意義について山口は、「チェンバレンの金字塔」と評した上で、以下のように述べている。

バジル・ホール・チェンバレン
また、チェンバレンは、明治二十年に、前年ロンドンで出版した『A Simprified Grammar of the Japanese Language』を日本語訳した『日本語小文典』という文法書を刊行している。
さらに、『古事記』や『日本書紀』に見られる古代日本語の語彙と朝鮮語、琉球語などの比較研究をとおし、日本語が言語歴史学的にどこまで遡れるかを明らかにした『日本語の最古の語彙について』という学術的に貴重な論文を発表している。この論文は、万年も助手として加わったこともあり、チェンバレンとの共著として発表されている。共著として発表されたことは、万年にとって誠に名誉なことであったと思われる。
この間、学生には、ヨーロッパの最新の言語学に関する多くの研究者の成果物を、作品名を挙げながら読むよう進めている。
優れた研究者であり、また知の伝達者でもあるチェンバレンから、万年は、日本語を科学的に分析することを学んでいった。優れた研究者とはいえ、外国人から日本語を学ぶことは、学生にとって、戸惑いや反発心もあったようである。万年自身も、最初は、チェンバレンが日本文法を講義することを「非常に奇異」に感じ、また、西洋人から日本文法の講義を聞くことを「国辱」とさえ感じている。
しかしながら、講義を受けるにつれて、広い視野で、根拠を踏まえながら、丁寧に指導する師に傾倒し、「これはどうしても、この学風が日本にも起こらねばならぬという事をつくづく感じる」ようになっていくのである。
東京帝国大学を卒業し大学院に進んだ万年に、明治二十三(1890)年、「言語学」研究のためのドイツ留学の命が下った。留学に際し、万年の関心事は、「大日本帝国の国語の創設」、「博言学的な日本語研究の推進」にあったようである。
万年はベルリン大学に留学し、当時最高の言語学の担い手とされたゲオルク・フォン・デァ・ガーベレンツの指導を受けることになった。ドイツ語圏で初めての東洋言語学の教授となったガーベレンツは、「一般言語学」で名高いソシュールに先立って、ソシュールの「ラング」と「パロル」という概念を指摘していた人物とされ、また日本語についても深い造詣の持ち主であった。
万年が、ガーベレンツという当代随一の研究者の指導を受けることができたことは、万年にとっても、さらに言えば日本にとっても幸運なことであった。山口の本には万年の学びの内容が詳細に描かれているが、ここでは省くこととしたい。いずれにしても多くの成果を得、並行して、新しい「日本語」をつくるための決意と意欲をもって、万年は帰国の途につくのである。
帰国後最初に行った講演「国語と国家と」において、万年は、「日本語の科学的な研究はまだ今はじまったばかりである。しかし、今後、日本語という母国語が、どのようなものなのかを研究し、きちんとした日本語の教育を行っていく必要がある」と述べ、さらに、わが国の公式文書が漢文で綴られ、また文学者も漢文の影響なしに文章を書く人がほとんどいない中、それをそのまま踏襲するのではなく、「今こそ、国語の重要性を再認識する必要がある」と主張している。
万年がガーベレンツに学んだこと、及び、その学びの「国語」確立への影響に関し、「グリムの法則」にのみふれておきたい。
グリム童話で知られるグリム兄弟は言語学の専門家でもあり、特に兄のヤーコプは「グリムの法則」と呼ばれる「音韻推移」についての世界的に見ても極めて重要な研究を成し遂げている。音韻推移すなわち異なる言語間における単語を比較することによって音韻変化の法則を導き出す「グリムの法則」に関し、山口の説明からひとつだけ例を引いておく。
 数字の「2」はサンスクリット語、古代ギリシア語、ラテン語ではそれぞれdvi 、duo、 duo、であるが、ドイツ語、英語、オランダ語のゲルマン語では、 zwei、 two、 tweeとなる。ドイツ語の「z」は「t」の発音であることから、ゲルマン祖語twaiが導き出され、そのことは即ち印欧祖語の有声閉鎖音「d」は「t」になるというものである。因みに、有声閉鎖音では他に、「b」が「p」に、「g」が「k」なり、そうした音韻変化は、無声閉鎖音や帯気音にもみられるとされている。もちろん、これだけでは分かりにくいと思われるので、興味のある方は、山口の本をぜひお読みいただきたい。
数字の「2」はサンスクリット語、古代ギリシア語、ラテン語ではそれぞれdvi 、duo、 duo、であるが、ドイツ語、英語、オランダ語のゲルマン語では、 zwei、 two、 tweeとなる。ドイツ語の「z」は「t」の発音であることから、ゲルマン祖語twaiが導き出され、そのことは即ち印欧祖語の有声閉鎖音「d」は「t」になるというものである。因みに、有声閉鎖音では他に、「b」が「p」に、「g」が「k」なり、そうした音韻変化は、無声閉鎖音や帯気音にもみられるとされている。もちろん、これだけでは分かりにくいと思われるので、興味のある方は、山口の本をぜひお読みいただきたい。
最新の言語学である「グリムの法則」を学んだ万年は、明治三十一年、「p音考」という画期的な論文を発表した。万年は古代日本語、サンスクリット語、アイヌ語、沖縄薩摩地方の言葉等を比較研究し、「上古の日本語では「はひふへほ」が「パ・ピ・プ・ペ・ポ」と発音されていて、それが「ファ・フィ・フゥ・フェ・フォ」となり、「ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ」に変化した」という結論を導き出している。この万年の結論は、今日正しい学説とされ、同時に「グリムの法則」に従って、万国語に共通に表れる現象を示した重要な研究とされている。
この論文は一例であるが、「国語」が確立されるためには、高度な学問に依拠した実に地道な研究が必要だったということは、ぜひ述べておきたい点である。
 「p音考」発表の三年前の明治二十八年、万年は『国語のため』という本を出版した。扉を開けると、「国語は帝室の藩屏なり、国語は国民の慈母なり」という万年の言葉が記されているという。「藩屏」、垣であり、防壁であり、守り手である。「帝室の藩屏にして、国民の慈母」、万年の「国語」に懸ける思いが伝わってくる言葉ではないだろうか。この本には、上述の「国語と国家と」、さらに「国語研究に就きて」、「欧州諸国に於ける綴字改良論」、「今後の国語学」等、十四本の論文が収められている。論文のタイトルからも、彼の研鑽、あるいは「国語」への関心が伝わってくる感がある。
「p音考」発表の三年前の明治二十八年、万年は『国語のため』という本を出版した。扉を開けると、「国語は帝室の藩屏なり、国語は国民の慈母なり」という万年の言葉が記されているという。「藩屏」、垣であり、防壁であり、守り手である。「帝室の藩屏にして、国民の慈母」、万年の「国語」に懸ける思いが伝わってくる言葉ではないだろうか。この本には、上述の「国語と国家と」、さらに「国語研究に就きて」、「欧州諸国に於ける綴字改良論」、「今後の国語学」等、十四本の論文が収められている。論文のタイトルからも、彼の研鑽、あるいは「国語」への関心が伝わってくる感がある。
この頃、万年は、フランスのアカデミー・フランセーズのような機関が日本にも必要と考えていたようである。国家が「国語」に関わる機関である。
その構想が具体化し、明治三十一(1898)年、万年は「国字改良会」を発足させる。国字改良会には、加藤弘之、井上哲次郎、嘉納治五郎などが発起人として名を連ねている。国字改良会の意向も踏まえ、「字音かなづかいを発音主義で統一する」という案が打ち出されるが、「発音主義」とは言文一致の考えにつながるものであった。

芳賀矢一
この時期、万年を支え、その後も「国語」確立に向け協力していくのが一番弟子の芳賀矢一であった。万年が教授、芳賀が助教授として帝国大学につくられた「国語研究室」は、日本語研究を行う重要な拠点となっていく。
明治三十三(1900)年には万年を会長として、「言文一致会」が作られた。芳賀矢一、さらには万年の弟子で「広辞苑」で知られる新村出なども名を連ねる会である。言文一致への動きがこうして少しずつではあるが確実に進展し始めていく。
万年の協力者である芳賀矢一は、明治三十三年に「ドイツ・フィロロギー」研究の命を受けドイツに留学する。学んだのは師万年と同じベルリン大学であった。「フィロロギー」は今日の「文献学」とされるが、「文献学」という語は後に芳賀矢一が訳したものだという。万年の「言語学」研究同様、芳賀の「文献学」研究もまた「国語」確立に貢献することになる。
なお、余談になるが、芳賀は漱石と同じ船で渡欧し、やがてロンドンにいる漱石を訪ね、漱石が神経症になっていることを文部省に知らせた人物でもある。
明治三十九(1906)年、芳賀は「漢文の覊絆を脱せよ」という論文を書いている。冒頭、「将来の文体はどうしても、言文一致で無ければならぬとおもう」と述べ、論文の最後では、「漢文の覊絆をふりすてて、文体の上でも、国民特得の文体を作り出す覚悟が無くてはならぬ。それは日々進歩してゆく国民の口語から出て来ねばならぬ」と結んでいる。
同じ年に、万年は「言文一致は果して冗長か」という論文を著した。最初に、「将来の文体は必ず言文一致になるであろう。否な、ならねばならぬ」と述べたこの論文中の万年による以下の主張は誠に興味深いものがある。
芳賀の主張と万年の主張は軌を一にしているが、とりわけ、万年の文章からは、新しい「日本語」の誕生、「国語」の成立を予感させるに十分なものを窺うことができる。それは、前号でふれた水村美苗の『「現地語」が「国語」へという高みに上っていく』ことに通じる主張と思えるからである。
山口が、「明治三十九(1906)年は、言文一致の軸が大きく動いた年であった」と表現しているのは、正鵠を射ていると言うべきであろう。
ほぼ時を同じくして、夏目漱石が明治三十八(1905)年「ホトトギス」一月号に『我輩は猫である』を発表した。そして翌明治三十九年には、その一節が早くも教科書に登場している。これ以降、漱石の作品は多くの教科書に採用され、日本語に大きな影響を与えていくことになる。
山口は、「漱石の文章が教科書に採用されるに当たっては、万年や芳賀矢一などの教科書調査委員会の力もあったからである」とした上で、以下のようにまとめている。
ここで、前号で引用した文章を再掲したい。

夏目漱石
本号における論考を通し、改めて、「万年なしに「漱石」は生まれてこなかった」という山口の言葉をかみ締めている。
同時に前号で私の言葉として述べた『万年なしに「漱石」は生まれてこなかった』をもじれば、『万年と漱石なしに「日本語(国語)」は生まれてこなかったと言えるかもしれない』という言葉も再掲しておきたい。
グローバル時代における英語の重要性は、私も異存はない。一方で、国語の重要性も強調したい点である。
「国語」の成立、「国語」の確立に向けて傾けられた先人の歩み、膨大な努力を考えることは、国語のもつ意義を見つめ直すことにもつながると感じている。
そして、「国語」あるいは「国語力」を考えることは、「湘南学園の明日を考える」ことにもつながると確信している。