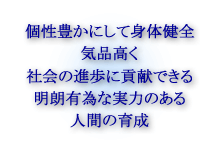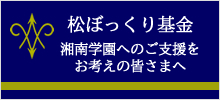シリーズⅡ 「国語力を考える(その5)」
「英語教育と国語力」
正月の風物詩箱根駅伝。箱根駅伝には私なりの思い入れがある。ちょうど十年前、箱根駅伝のコースを歩きたいと思い立った。そのきっかけを作ってくれたのが『風が強く吹いている』(三浦しをん)であった。箱根駅伝には昔から関心が強く、テレビの中継で、テレビのない時代にはラジオでの中継を楽しんでいた。『風が強く吹いている』を読み、権太坂の上りや箱根の坂も含め108kmのコースを自分の足で確かめたい、風景を風を自分の身体で感じたいと思うようになった。2007年12月に読売新聞社前から一歩を進め始め、往路を十日間で踏破した。
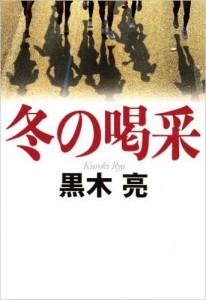 そしてそれから一年半後、復路に向けての一歩を後押ししてくれる作品『冬の喝采』(黒木亮著)に出会った。著者黒木亮は、国際金融を含む経済分野を題材にした小説を中心に多くの作品を著している作家として知られている。同時に、彼は、往年の名ランナー瀬古利彦と同時期に早稲田大学競走部に所属し、瀬古からトップで襷を引き継ぎ三区を走り、そのままトップで襷を繋いだ長距離選手でもある。
そしてそれから一年半後、復路に向けての一歩を後押ししてくれる作品『冬の喝采』(黒木亮著)に出会った。著者黒木亮は、国際金融を含む経済分野を題材にした小説を中心に多くの作品を著している作家として知られている。同時に、彼は、往年の名ランナー瀬古利彦と同時期に早稲田大学競走部に所属し、瀬古からトップで襷を引き継ぎ三区を走り、そのままトップで襷を繋いだ長距離選手でもある。
『冬の喝采』は、黒木亮の自伝的小説であり、彼自身が詳細に記録していた膨大な練習日誌がもとになっている。中学時代に陸上競技(長距離)に出会い、北海道の公立高校から一般入試で早稲田大学法学部に入学した彼は、高校時代からの足の故障を何とか克服し、大学一年の三月に競走部の門をたたいた。当時の中村清監督から準部員という扱いで入部を許可され、その後のひたむきな努力が実り、三年の時は三区、四年では八区を走っている。
競技者にしか分からない競技そのものについての緻密な分析と深い省察、あるいは競技者の内面の細部にわたる描写を交えた600頁を超える長編は誠に興味深いものがあった。そして、その作品の中で黒木亮は、本名金山雅之として登場している。
前置きが長くなった。私がこの作品で強く印象に残っていることに、黒木亮の大学時代における英語への向き合い方がある。同書には以下の一節がある。
当時よく知られた英語教材であるリンガフォンで、一日も欠かさず英語の学習をしていたという彼の「虚仮の一念」という言葉が心に迫ってくる。卒業後都市銀行に就職し、さらに商社等でも活躍し、国際金融小説で脚光を浴びた黒木亮の生き方の根底に「虚仮の一念」で継続した英語学習があるように思えてくる。
余談になるが、この作品には瀬古がしばしば登場する。例えば、「ただし瀬古は、走る練習以外にも、千駄ヶ谷の監督宅近くのアパートから大学までの片道五キロの道を、重い安全靴をはき、両手に石をもって歩いていた」というエピソードなどは、将棋の羽生善治の「努力を継続できる力こそが才能」という言葉にも通じる感を覚えている。
私自身に関し、一言補足すれば、『冬の喝采』の後押しを受け、2009年の10月に芦ノ湖畔をスタートした復路は六日間で大手町のゴールに歩き着くことができた。
ところで、同時通訳者としてさらには大学教授として活躍した方に鳥飼玖美子氏がいる。氏は、英語学習についての視点を記した『本物の英語力』において、外国語を学ぶことは、「未知の世界に遭遇すること」であり、「異質性と格闘すること」とした上で、以下のように述べている。
 鳥飼氏の「自律した学習者」と黒木亮の「虚仮の一念でのリンガフォン学習」が重なるようにも思えてくる。少なくとも受け身の学習、安易な学習態度で英語が身につかないのは言うまでもないことであり、「異質性と格闘すること」という鳥飼氏の言葉からは改めて英語学習への姿勢について身を正される思いがしてくる。
鳥飼氏の「自律した学習者」と黒木亮の「虚仮の一念でのリンガフォン学習」が重なるようにも思えてくる。少なくとも受け身の学習、安易な学習態度で英語が身につかないのは言うまでもないことであり、「異質性と格闘すること」という鳥飼氏の言葉からは改めて英語学習への姿勢について身を正される思いがしてくる。
『本物の英語力』は2016年に出版されたものであるが、それに先立ち同じ鳥飼氏により2006年に出版された本に『危うし! 小学校の英語』がある。四章からなるこの本のそれぞれの章は以下のような表題となっている。
第一章 「早ければ早いほど」幻想を打ち砕く!、第二章 「親の過剰な期待」が英語必修化への道を開いた、第三章 誰が英語を教えるのか、第四章 日本の英語教育はどうあるべきか
長年にわたり英語教育に携わった鳥飼氏の問題意識が窺える章立てであり、本文には専門家ならではの鋭い分析が随所に盛り込まれている。
その中で、氏は、研究者の研究成果を引きながら、英語とフランス語の二カ国語が公用語となっているバイリンガルのカナダを例に母語の大切さを指摘している。
「特に興味深いのは、母語の読み書き能力をしっかり身につけてからカナダに移住した子どもは、比較的短い期間に母語話者並みの読み書き能力に追いつくのに対して、母語が確立する前の幼児期に移住した子どもは発音は容易に習得するものの、読み書き能力を身につけるのは難しく、長い時間がかかるという発見です」。さらに、同じ研究者の研究成果を引き、「母語と第二言語は深層部分でつながっており、双方が影響しあいながら発達していくこと、読み書きなど学習言語には母語の習得が大きく影響すること」をも指摘している。
また、アンケート調査を例に引きながら、子をもつ一般の男女においては、「小学校までに英語を学ばせたい」という親が92%に達するのに対し、帰国生母の会の調査においては、圧倒的多数が「母語が確立してから」と答えているとし、それは、帰国子女は「現実」を知っているからだとしている。あるいは、トーフルについて正確な理解を促している箇所、中学校においては文法の基礎をしっかり身につけることが大切とする主張、さらに教員養成や現職教員の再研修等、教師の力量を高めることの重要性への言及も専門家ならではのものがあるように思っている。
氏は、この本の最後で、「英語教育改革の見取り図」として、小学校、中学校、高校、大学における英語教育の具体像を明らかにしている。具体的内容はその本に譲ることとし、発達心理学の知見を援用しつつ「第二言語の学習は母語のように自然に身につくものではなく、自覚的・系統的に学ぶことが必要」とする氏の見解もまた肯けるものがある。
氏の両著をとおしての主張、すなわち、英語学習においては、文法や読解にも大きな意義があること、英語学習の土台として母語、言い換えれば「国語」が重要であること、自律的に自覚的に地道な努力を継続することが大切であること、こうした点は、改めて傾聴したい内容と感じている。
ところで、私事になるが、暮れに、以前勤務していた高校の卒業生に会う機会があった。卒業後も連絡を取り合っている彼は、現在東京大学大学院で斎藤兆史教授の下で学んでいる。斎藤兆史氏は、英語教育の専門家として、また『英語達人列伝』、『英語達人塾』等の著者としても知られる方である。二年前、彼に斎藤教授の研究室に進むと聞き、勝手ながら斎藤教授には親近感を覚えつつ、上記著書等を読ませていただいている。
 『英語達人列伝』には、新渡戸稲造、岡倉天心、斉藤秀三郎、鈴木大拙、幣原喜重郎、野口英世、斉藤博、岩崎民平、西脇順三郎、白洲次郎の十名が取り上げられている。まさに英語の「達人」としか申し上げようのない上記諸氏が、どのような学びをとおして英語を習得したかについて、専門家ならではの知見をもとに味わい深い叙述がなされている。著者の斎藤氏は、かつての日本には驚嘆すべき英語の使い手がいたとした上で、上記諸氏が英米人も舌を巻くほどの英語力を身につけていたことを具体例をあげながら詳述している。しかも、上記英語の「達人」が、劣悪な条件の中で、さらに、基本的には日本にいながらにして英語に熟達したという共通点をもつことに注目している。同時に、氏は、上記「達人」を、「西洋かぶれになることなく、外国文化との真の交流を実践した人々」と評価している。その本の中に以下の一節がある。
『英語達人列伝』には、新渡戸稲造、岡倉天心、斉藤秀三郎、鈴木大拙、幣原喜重郎、野口英世、斉藤博、岩崎民平、西脇順三郎、白洲次郎の十名が取り上げられている。まさに英語の「達人」としか申し上げようのない上記諸氏が、どのような学びをとおして英語を習得したかについて、専門家ならではの知見をもとに味わい深い叙述がなされている。著者の斎藤氏は、かつての日本には驚嘆すべき英語の使い手がいたとした上で、上記諸氏が英米人も舌を巻くほどの英語力を身につけていたことを具体例をあげながら詳述している。しかも、上記英語の「達人」が、劣悪な条件の中で、さらに、基本的には日本にいながらにして英語に熟達したという共通点をもつことに注目している。同時に、氏は、上記「達人」を、「西洋かぶれになることなく、外国文化との真の交流を実践した人々」と評価している。その本の中に以下の一節がある。
ここで指摘されている「日本独自の言語文化」は、明治以来の「日本語の図書館の充実ぶり」、あるいは、前号で紹介した益川敏英氏による「日本語で最先端のところまで学問ができること」と読み替えることができよう。
また斎藤氏は、仮説としながらも、岡倉天心や斉藤博の学問形成過程を見る中で、漢学修行や漢文の素読が英語習得を促進したのではないかということを述べている。この点については、上述の「達人」の英語力の土台に漢学を含む国語力があるという主張とも捉えることができるような気がしている。関連で、同書における斎藤氏の以下の見解も紹介したい。
控え目な表現ながら、ここでの氏の見解は、英語習得の背景に国語(日本語)力があることは否定できないということを述べているように私には思えるのである。
なお、同じ斎藤氏の著書『英語達人塾』の中で、氏が、我々は、常日頃日本語でものを考えながら生活をしているとした上で、言語は頭の中の漠然とした想念を論理的思考として実体化する道具であり、我々日本人にとっては、日本語を用いているときがもっとも深くて繊細な思考活動を行なっているとしているのは、まさに国語(日本語)力の重要性を述べたものに他ならないと感じている。
両著において、日本語の重要性とともに斎藤氏が強調しているのは、文法の重要性であり、文法及び読解に時間をかけることの意義である。同時に、「退屈な訓練を毎日毎日続けた者のみが、高度な英語力を身につけることができる」とし、地道な努力の積み上げの重要性を力説している。
斎藤氏の主張も、上記黒木亮の「虚仮の一念」や、鳥飼氏の「英語を学ぶことは「格闘」」に通じるものがあるように思えてならない。
ここで前号の最後にふれた水村美苗の主張に入りたい。前号でも述べたように、『日本語が亡びるとき』において水村が重視しているのは、今後のわが国の国語教育ではなく英語教育についてであったことを予め確認しておきたい。
水村の主張そのものに入る前に、おさらいしておきたいことに「普遍語」「国語」「現地語」がある。かつてのラテン語や漢文が「普遍語」であり、巷で人々が使う言葉が「現地語」であった。「現地語」が翻訳等により高められ磨かれ、やがて「国語」としての地位を占めるようになっていく。そのことにより、西洋を例にとれば、「普遍語」であるラテン語による「ラテン語の図書館」が知を独占していたものの、次第に「現地語の図書館」が充実するようになっていく。「現地語」が「国語」へと高められる中、最終的には、優れた知性の持ち主、水村の表現によれば「叡智を求める人」も、「国語の図書館」にしか出入りしなくなったというものであった。
今日の世界を考える上で、水村が何よりも着目するのは、英語の広がりと優位性についてである。水村は、今日、英語が「国際語」というよりは「普遍語」と呼ぶべき地位に向かっていると述べる。特にインターネットの出現及びその普及は、英語の「普遍語」化を決定的にし、今後、今世紀のみならず、将来にわたり、英語の「普遍語」としての地位は揺るがないものになるとの見通しを強調している。
かつて、「普遍語」としての地位を占めていたラテン語や漢文には、学問の言葉としての役割があった。即ち、「普遍語」と学問は、本来、分かちがたく結びついている。今日、「普遍語」とも呼ぶべき地位に向かっている英語が学問の世界において重要性を高めているのは、「普遍語」が学問の言葉である以上、必然の成り行きと見るべきなのであろう。水村が、わが国においても、自然科学はもとより人文科学においても、意味のある研究をしている研究者ほど研究成果を英語で書くようになっているとしているのもその例証と言えよう。同時に、そうした動きがわが国のみではないことは自明であり、水村は、そうした動き、即ち、意味のある研究をしている研究者ほど研究成果を英語で書こうとしていることを「世界の読まれるべき言葉の連鎖に入ろうとしつつある」と表現している。

カレツキ
カレツキは、1933年にケインズの『一般理論』にあたる原理を発見し、論文をポーランド語で出版したが誰の目にもとまらなかった。二年後に彼はフランス語に訳して出版したがやはり影響力をもたず、その翌年(1936年)、ケインズの『一般理論』が英語で出版され経済学の流れを変えていった。カレツキは自らの「知的所有権」を主張すべく、「自分はケインズの三年前に同じ原理を発見した」という論文を発表するが、それもポーランド語で書かれ、「当然のこととして、その論文も、誰の目にもとまらなかった。・・・気の毒なカレツキは、「英語で書かなかった」学者として、のちの世に名を残すことになったのであった」
世界中の学者が、「世界の読まれるべき言葉の連鎖に入ろうとしつつある」中で、現在もそして今後においても、「英語で書かなかった」カレツキのような学者は間違いなく現れないであろう。
英語が「普遍語」としての地位を固めている現在、水村の言葉では「叡智を求める人」は英語で書き、英語で読む、そうした方向に向かいつつある。水村は、「非英語圏でも、名だたる大学は、大学院の授業を英語に移行しようと試み始め」ており、身近な例でも、「日本の大学院、それも優秀な学生を集める大学院ほど、英語で学問をしようという風に動いてきている」と述べる。『日本語が亡びるとき』が出版されたのが2008年、それから十年近い時間の経過の中で、その傾向はさらに強まっているのではないだろうか。
英語が「普遍語」としての役割を強めていくことに伴い、書き手も読み手も「叡智を求める人」であればあるほど、「普遍語」で書き、また読もうとするようになる傾向は容易に予想できよう。そこでもうひとつ予想されるのは「国語」の地位の相対的な低下である。その点に関し、水村は、「叡智を求める人」が「普遍語」に惹かれていくことに伴い、「国語」が「国語」足りえず、「現地語」に堕していく可能性を示唆している。関連して、水村は、「悪循環が本当にはじまるのは、「叡智を求める人」が、「国語」で書かなくなるときではなく、「国語」を読まなくなるとき」であると述べている。
読むことは書くことに比べはるかに楽な行為であるとした上で、「叡智を求める人」が読み手の立場で「普遍語」に惹かれていくことと並行して、書き手も読んでほしい読者に読んでもらえないということから「国語」では書こうと思わなくなり、「国語」で書かれたものはつまらなくなる。「叡智を求める人」は、一層「国語」で書かれたものを読まなくなり、即ち悪循環となっていくというのである。その結果、職業を問わず、「叡智を求める人」は「普遍語」で読もうとする思いが強くなり、「世界で重要なことが起こっているのを知りたいときは英語のメディアに目を通し、自国のスポーツの結果などを知ろうとするときだけ自国のメディアに目を通す」ような状況を呈することが想定されるとしている。そして、そのことはとりもなおさず、「国語」が「現地語」に堕していくことに他ならないのである。
水村は、この点にも関連し、下記のような悲観的な見方をしている。
言うまでもなく、水村の危機感のあらわれであり、<現地語>文学、「ニホンゴ」文学が主流を占めるようになれば、日本語(国語)そのものが亡びへと向かうことになるという懸念も併せて窺える見方であろう。まさに本のタイトル通りの『日本語が亡びるとき』であり、副題の「英語の世紀の中で」という言葉の意図する所も鮮明に浮かび上がってくる感がある。
 さて、英語が「普遍語」の地位を確立しつつあることに関連し、水村の主張でもうひとつ注目したいのは、英語は「普遍語」であると同時に、ある人々にとっては「母語」でもあるという点であろう。
さて、英語が「普遍語」の地位を確立しつつあることに関連し、水村の主張でもうひとつ注目したいのは、英語は「普遍語」であると同時に、ある人々にとっては「母語」でもあるという点であろう。
水村は、インド人、中国人、韓国人、日本人などのアジア人が数学、自然科学、生物学、工学、医学などの分野で世界的に活躍していることについて以下のように分析する。
ここで、改めて、益川敏英氏の、「日本語で最先端のことまで学問ができる」あるいは、斎藤兆史氏の「我々日本人にとっては、日本語を用いているときがもっとも深くて繊細な思考活動を行なっている」という言葉を思い起こしたい。
少なくとも、現在は、日本語(国語)が、「現地語」ではなく「国語」としての役割を果たしており、「国語」が学問としての言葉としての地位を保っているはずである。そして、その日本語(国語)は、明治以降の限られた時間の中で、先人の膨大な努力、苦難の歩みの中で磨かれ高められ確立したものであったということも忘れてならないことであろう。
英語が「普遍語」としての役割をますます高めていく中で、英語を母語としない日本人が、今後英語とそして日本語(国語)とどう向き合うべきか。水村の見解は、益川氏や斎藤氏の言葉とともに、わたしたち一人ひとりへの問いかけとして迫ってくる感がある。
そうした自覚の上で、水村が期待するのは「学校教育」である。もとより水村の期待は最終的には国語教育への期待ではあるが、その前提に英語教育についてのあり方を鋭く問いかけている。水村は、以下のように述べる。
 水村にあっては、英語教育と国語教育はいわば対の関係にある。その上で、英語の世紀に入った以上、国益の観点からも、すべての非英語圏の国家が、優れた英語の使い手を、十分な数、育てなければならなくなったとし、そのための三つの方針を想定している。
水村にあっては、英語教育と国語教育はいわば対の関係にある。その上で、英語の世紀に入った以上、国益の観点からも、すべての非英語圏の国家が、優れた英語の使い手を、十分な数、育てなければならなくなったとし、そのための三つの方針を想定している。
Ⅰ <国語>を英語にしてしまうこと
Ⅱ 国民の全員がバイリンガルになるのを目指すこと
Ⅲ 国民の一部がバイリンガルになるのを目指すこと
水村が、この三つの方針の中のどれを主張するのかは後述するとして、彼女の問題意識についてふれておきたい。
水村は、今、日本語が「亡びる」のに不安を覚える日本人はほとんどいないであろうと述べ、他方、英語ができなくてはという強迫観念をまったく感じていない日本人は死も間近い老人かへそ曲がりの変人ぐらいのものであるとしている。そして、後者に関して言えば、とりわけ、子どもをもつ親は英語への強迫観念が強いと指摘するのである。
事実、英語の世紀が進む中で、子どもが英語を身につけることへの親の期待は高まるばかりといっても過言ではない。一方で、英語にお金をかけることができる親とそうではない親とが存在するのも現実にはある。いずれにしても、「子どもに英語を」という声の高まりの中で、水村が懸念するのは、「学校教育がその声を受け止めようとすればするほど、何かを疎かにせねばならない」というものである。
水村は、2008年に発表された学習指導要領を踏まえ、中学校を例にしながら、「疎かにされているのが国語である」としている。なお、ここではその指摘のみに止めたい。
このような問題意識の上で、水村は上記三つの方針中のⅢこそ、わが国がとるべき道であると強く主張している。
既に述べているように、水村が最も訴えたいのはわが国の国語教育についてではあるものの、国語教育と対になる関係性において、英語教育については上記方針中のⅢをとるべきと主張している。水村が方針のⅢを強く主張する理由、さらに彼女がわが国の国語教育はどうあるべきと考えているかについては次号に譲りたい。