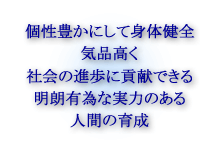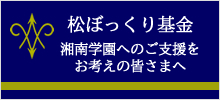シリーズⅡ 「国語力を考える(その9)」
「『リベラルアーツ』とその土台としての国語力 -文系、理系を越えて-」
リベラルアーツ。「教養」、あるいは、「一般教養」と訳されることの多いこの言葉は、わが国において必ずしもなじみのある言葉ではないものの、今後の教育を展望する上で大切な概念ではないかと考えている。
本号では、国語力との関わりにおいても重要と思われるリベラルアーツについて考察していくが、リベラルアーツについての私の考え方を述べる前に、関連して、『学園だより(126号)』にふれたいと思う。
 私は、湘南学園『学園だより(126号)』(2017年3月発行)に、「新たなステージに向けた湘南学園の挑戦」と題して、今後の学園づくりに関する私の考えを記した。
私は、湘南学園『学園だより(126号)』(2017年3月発行)に、「新たなステージに向けた湘南学園の挑戦」と題して、今後の学園づくりに関する私の考えを記した。
その中で、今後に向けての二本の柱として、湘南学園の教育の根本理念としての「建学の精神」の再確認、湘南学園としての「グローバル教育」の構築を掲げた。
ここでは、本号のテーマとの関連で、『学園だより』に記した「グローバル教育」についての私の考え方から始めてみたい。
今日、グローバル教育という言葉は使い手により定義が異なり、意味内容があまりにも広がり過ぎている感がある。私は、グローバル教育については、以下の三点を重視すべきと考えている。「世界標準」、「リベラルアーツ」、「多様性と共生」がそれである。
グローバル教育についての私なりの定義は、読書等から得た知識に加え、昨年八月の米国トップランキング大学視察において、スタンフォード、ハーバード、MIT等を訪問し、種々の学びを得てきたことも与っている。この米国大学視察の折にも、本号のテーマであるリベラルアーツ、あるいはリベラルアーツ教育という言葉をしばしば耳にした。この言葉への統一した定義が十分になされているとは思えないものの、リベラルアーツが米国のみならずわが国の今後の教育を考える重要な概念であることは間違いないと考えるに至っている。

ハーバード大学
リベラルアーツについては後ほどふれることにして、上述の「グローバル教育」に関する私の定義を構成する三点について説明しておきたい。
「世界標準」について言えば、わが国だけで通用する物差しではなく、「世界で通用する物差し(世界標準)」で教育活動を考えたいというのが私の考えである。留学から帰った学園生に留学先での学びについての話を聞き、あるいは、本学園で学ぶ留学生の学びの姿勢や本国での学びについての話を聞く中で、「世界で通用する物差し(世界標準)」が、わが国の教育活動において、今後、より重視されることになるとの感を強くしている。
「多様性と共生」は、21世紀のキーワードとも呼ぶべきものであり、その重要性は増すことはあっても減じることはないと思われる。
もうひとつの「リベラルアーツ」については、本号との関連で、私なりの定義を述べることとする。
「『文系、理系を越えた学び』、かつ、『幅広く深い学び』」というのが私の定義である。
半年ほど前に興味深く読んだ本に『根っからの文系のためのシンプル数学発想術』(永野裕之著)がある。著者の永野氏は、高校時代数学オリンピックに出場した方で、東京大学理学部地球惑星物理学科を卒業した後、同大学院に進み、現在は、個別指導塾・永野数学塾(大人の学習塾)の塾長をつとめている方である。
文系を自認し、数学から身を遠ざけている人にこそ、誰もがもっているはずの数学的発想力に気づいてほしいという願いで書かれた同書の最初に次のような一節がある。
 まさに高校生の現状についての鋭い指摘であり、高校生が抱える課題についての指摘であろうと感じている。
まさに高校生の現状についての鋭い指摘であり、高校生が抱える課題についての指摘であろうと感じている。
永野氏の指摘している高校生の考え方の傾向、学びについてのとらえ方の背景には、わが国の大学入試の現状がある。少数科目による入試、推薦等における学力試験を課さない入試等が、高校生の学び、学ぶ姿勢に少なからず影響を与えていることは事実であろう。
そうした現状は認めざるを得ないものの、現状をよしとするのではなく、現状を変えるためにもリベラルアーツについて検討し、その重要性に注目したいというのが、本号の意図する所である。
リベラルアーツについては、まず、斉藤淳氏の『10歳から身につく 問い、考え、表現する力』から入っていきたいと思う。
斉藤氏は、山形県酒田市に生まれ、高校までを地元の公立で過ごし、上智大学及び同大学院を卒業後、米国イェール大学大学院で博士号(政治学)を取得し、その後イェール大学の助教授をつとめるなど、日米両国の学びに詳しい方である。氏は、その後衆議院議員を経て、現在は、東京自由が丘と渋谷及び故郷酒田で塾を開き、次代を担う子どもの教育に当たっている方でもある。上述の斉藤氏の本は、氏自らの日米両国での学び、さらにイェール大学等で教鞭をとり、また東京と山形で子どもたちを教えている経験を踏まえて書かれたものである。
この本の狙いは、氏がタイムマシンに乗れたら十歳の自分に言いたいという言葉に端的にあらわされている。
「正しく学ぶ方法と、自ら問うことを忘れなければ。君は何にだってなれるんだよ」という冒頭に掲げた言葉である。
斉藤氏は、十歳の時に、自らがやがてイェール大学の大学院で学ぶことになったり、イェール大学で教鞭をとることになったり、衆議院議員になったりということは思いもよらなかったことを顧みながら、一方で、自らの経験を踏まえ、いわば確信をもって上記の言葉を発している。一言補足すれば、塾開設の理由、すなわち「知の喜びと学びの作法を直接子どもたちにつたえたい」という氏の思いも、この本全体を貫いている。
斉藤氏も、上述の永野氏と同様、「大学入学をゴールとして受験勉強をし続ける日本の子どもたちは、・・・たいていの場合、数学や物理が苦手で英語が好きだから文系、あるいはその逆で理系、というように学習科目の得手不得手で進路を決めてきたのではないでしょうか」という問題提起を行っている。
そのような課題認識に立ちながら、氏は、自然科学でも人文科学でも社会科学でも、基本的な学びの作法は同じであるとし、将来、専門分野で成果を収めるためにも、広い分野に関心をもつことが必要であるとしている。
その上で、氏は、今後に向けて大切なこととして、「世界共通の学問のルールを知ること」、「どんな学問をするためにも必要な『問う』力、『考える』力、『表現する』力を養うこと」を挙げている。そして、その準備は、十歳くらいから始めるにこしたことはないと主張するのである。
本のタイトルは、こうした氏の考え方に由来している。日本の子どもに学ぶ喜びを感じさせ、世界に通用する知的基盤を与えるために、リベラルアーツが重要と氏は説いている。
 氏は、最初に、リベラルアーツに「自由の学芸」という訳語をあてている。さらに、リベラルアーツの考え方はギリシアにさかのぼり、中世ヨーロッパにおいて大学制度が広まる中、文法、修辞、論理、代数、幾何、天文、音楽の七科目が基礎教養として課せられていたとする歴史的経緯を踏まえ、リベラルアーツを基礎教養と捉えている。
氏は、最初に、リベラルアーツに「自由の学芸」という訳語をあてている。さらに、リベラルアーツの考え方はギリシアにさかのぼり、中世ヨーロッパにおいて大学制度が広まる中、文法、修辞、論理、代数、幾何、天文、音楽の七科目が基礎教養として課せられていたとする歴史的経緯を踏まえ、リベラルアーツを基礎教養と捉えている。
その上で、氏は、イェール大学大学院で学び、また教員としてイェール大学で教えた経験をもとに、イェール大学の教育の特色について述べている。専門教育と教養教育の双方を大切にするイェール大学では、入学してくる学部生に、古今東西の古典と最先端の学問の両方を修めさせるという。加えて、かつてイェール大学総長を務めたレヴィン氏が挙げた具体例が紹介されている。
新たな課題に立ち向かうには、それまでに答えのない課題に批判的にかつ真剣に取り組んだ経験が生きてくるとする考え方から、たとえば、「未来の物理学者が、第一次世界大戦がなぜ勃発したかを議論することが大切」であり、「未来の生物学者が、シェイクスピアを分析的に読むことが必要」であり、政治や実業の世界で指導者として活躍するためには、情報を分析的かつ論理的に見つめる能力が必要になるという観点から「法科大学院に進学する学生が解析学や離散数学を学ぶことが必要」とする等の例である。
レヴィン元総長の言葉は、専門教育を大切にしながらもリベラルアーツカレッジとしての役割も重視するイェール大学のあり方を明快に説明したものととらえることができよう。
こうした斉藤氏の主張から、氏が大学教育におけるリベラルアーツをどのようにとらえているかは十分に理解できるものがある。一方で、氏は、既述のように、リベラルアーツを大学生に限定している訳ではない。むしろ、この本で強調しているのは、子どもたちへのリベラルアーツの勧めともいうべきものである。子どもたちへのリベラルアーツの勧めとは、言い換えれば、学びの方法、学びへの姿勢に関する子どもたちへの働きかけであり、くり返しになるが、子どもたちが喜びを感じ、世界に通用する知的基盤を培う学びの勧めである。
これからの時代において、答えのない問い、あるいはいくつもの答えがある問いにどのように取り組んでいくか、あるいは、問いから答えを導くだけではなく、問いそのものを考えることの重要性等は、多くの方が指摘するところである。
「わが国の子どもたちは正解をほしがるが、大切なのは正解がない問いに如何に対応するかということ」とする斉藤氏は、学力についても興味深い分析をしている。
いわゆるペーパーテストで測ることのできる学力と測ることのできない学力があるとする氏は、前者は「過去に学んできた達成度」であるのに対し、後者は「「未来」に向けて社会全体を牽引するような、イノベイティブな力」であるとしている。ともすれば、前者に力を入れてきたわが国においても、今後は後者を支援することにも力を注ぐべきという氏の主張は肯けるものがある。
「正解のない問いに如何に対応するか」、「それまでにはない価値を創造する知を如何に育てるか」、そのために必要なのが、まさに氏の言う、自分の頭で「問い」、「考え」、「表現する」力である。そして、自分の頭で「問い」、「考え」、「表現する」力を育むための手法として提示しているのが、子どものためのリベラルアーツという考え方であると読み取ることができるのである。
それでは、「問い」、「考え」、「表現する」力とは何か。簡潔にまとめてみたい。
 最初の「問う」力について、氏は、「学問とは学んで問いかける営みであって、問いかけを発して初めて学問と言える」という表現を用いながら、「問う」力の大切さを強調している。
最初の「問う」力について、氏は、「学問とは学んで問いかける営みであって、問いかけを発して初めて学問と言える」という表現を用いながら、「問う」力の大切さを強調している。
「問う」力を育てるということは、平易に言えば、疑問を持ち質問する子どもを育てるということになろう。氏は、わが国において、「問う」力が育っていないのは、教育活動の方法と生徒の意識ととらえている。
教育活動における問いかける機会の乏しさ、間違いを恐れ発言することをためらう子どもたち、テスト中心の評価等は、いわゆるアクティブ・ラーニングの奨励もあり変わりつつあるとはいえ、依然として残るわが国の教育現場の特徴と言えよう。「質問と間違いは、みんなへの貢献」という意識を子どもたちに育みたいとする氏の提言、あるいは、「質問しやすい雰囲気」を教える側が工夫することなどは、確かに、大いに傾聴したい内容であり、わが国の教育現場においてさらに努力すべきことであろう。
「考える」力については、氏は具体例に踏み込んでいる。学問とは、「抽象化に向けての努力」であり、「抽象と具体を行き来する作業」とした上で、自らの経験を紹介している。
たとえば、小学校三年生時に氏自ら取り組んだ理科の自由研究が詳しく述べられている。素朴な実験であっても、仮説、実験、検証というサイクルを小中学生時代から体験することは、その後に大きな意味をもつという主張は十分に納得できるものがある。また、氏自身が小学校五年生の時に行なった社会科の自由研究をとおして、歴史におけるいわゆる「一次資料」の重要性を学んだことも記されている。
「考える」力を育てるということは、正解をほしがる子どもを育てている教育、正解を覚え込む教育からの脱却である。「考える」力、「抽象と具体を行き来する作業」、すなわち科学的思考や論理的思考は、小学生の頃から大切にすべきことであり、またその時期から育むことができるということを氏は例証している感がある。
最後に「表現する」力については、その力を育むための「読書」に多くのページが割かれている。
読書の意義については、多くの方の指摘するところであり、斉藤氏もまたその重要性を強調する。思考のトレーニングとして読書は極めて有意義であり、本を読み、考え、記録する作業は小学生から始めることができるとし、読書を奨励している。
斉藤氏は、書店や図書館への子どもの導き方を示す一方で、本への書き込みや読書ノートの作成、そして本の選び方まで、小学生からでもできる読書の方法論を詳述している。
ここでは一部の紹介に止めるものの、例えば、古典に早くから親しませることの大切さはその一例である。ただし、古典は単に年代が古い本を指すのではなく、英語のclassicすなわち「第一級の」、「模範的、標準的、典型的」な本を指すとし、分野ごとの本の紹介もなされている。
読書ノートの作成法も、斉藤氏流の読書感想文作成につながる興味深い内容で大いに参考になるが、それ以外で、特に、私が注目したふたつのことにふれたい。
ひとつ目は、子どもに背伸びをさせることの有用性である。
子どもが本を読み、ある分野に興味を示したら、大学生が使っているような教科書で、かつ品質の高いものを選んで目につくところに置いておくことを保護者に勧めている。
その理由を氏は以下のように説明する。
氏は、今わからなくても、「将来わかること」を目標に、置いてある本を何度も読む、問いかけながら読む、そのような本との付き合い方を望んでいる。
ふたつ目は、批判的に読むことの重要性である。
わが国の受験国語とイェール大学の教養教育を比較しながら、わが国の入試問題では著者の主張に同化して読むことを求められるため、批判的に読むという手法が軽視され、結果として批判精神が育ちにくいとしている。今読んでいる本以外にも資料にあたる、あるいは、引用されている文献に当たり、引用が正しいか適切かを点検する等のいわゆる外部参照にも言及しながら、批判的に読むことの意義を述べている。
関連して読書感想文は、書評ととらえて書くべしと主張する。最初に内容の要約、次に著者の主張についての自分の解釈や評価、最後に、どんなひとにおすすめか、あるいはおすすめでないかを書くというものである。
こうした主張は共感できるものがあり、特に、斉藤氏流の読書感想文などは、すぐにでも教育現場で活用できそうな気がしている。
表現することに関連して、論理的かつ伝わりやすい文章を書くための英語の論文作成に関する手法は、わが国のこれからの教育に生かすべき方法論であろう。
すなわち、最初に結論を述べる英語の論文では、まず主題を一文で書き、主題における主張の根拠を示す。各段落の最初では、その段落を一文(トピックセンテンス)にまとめ、残りの部分でトピックセンテンスを補強する根拠を挙げていくという手法である。
読み手は、主題の一文と各段落のトピックセンテンスを読めば、論文の全体像を理解することができ、さらに必要に応じて細部に目を通すことも可能である。一方、書き手にとっても、分かりやすく伝えるための工夫、あるいは論文全体の完成度の高さが求められることになる。
氏は、この英語の文章作法に慣れることで論理的思考力がつき、英語の成績のみならず国語の成績も上がる生徒が多いとしている。氏の経験的な実感であろうし、納得のいく説明である。

イェール大学
子どものためのリベラルアーツを提唱する斉藤氏は、上述の本の中で、日米で学んだ経験、さらにイェール大学を始め、米国の大学で教鞭とった経験を踏まえ、英語教育についても多くのページを割いている。英語を学ぶ意味から実践的な学びに至るまで、誠に興味深い内容であり、関心のある方は、氏の本にぜひ当たっていただきたい。
ここでは、英語の学習法として、氏が応用言語学を踏まえた学習法を支持していること、関連で、まず母語の習得が大切であることを主張していることは、まず指摘しておきたい点である。氏は、英語の大切さを認めながらも、英語はあくまで「手段」であることを強調する。英語を使って、「何を問い、考え、表現するか」こそが大事とし、母語に習熟すること、すなわち国語力が大切であることを訴えている。
斉藤氏の本を通して感じることは、文系、理系を越えて知的基盤を培う学びであり、幅広く深い学びであり、さらに加えて言えば、学ぶことに喜びを感じ、学びがさらなる学びにつながるような学びと言えよう。
ここで、学び全体に関連して、私自身の関心事でもある数学についてふれておきたい。
政治学が専門の氏は、日本風に言えば文系でありながら、数学を深く学び、数学についての造詣が深いこともあり、数学の大切さを力説している。それは、「これからの時代に必要な知識として、数理的思考力の持つ重要性はますます増大していくと思うからです。研究や実務の最先端では数学の知識、もしくは数学に基づいた発想がますます重要になってきています」という氏の言葉からも明らかである。
私自身も、これからの学びを展望する上で数学は重要であると考えている。中世ヨーロッパの大学で専門を学ぶ前提の7つの科目(「seven liberal arts」とも呼ばれる)は、「文法、修辞、弁論」の「三学」、「代数、幾何、天文、音楽」の「四科」から構成されていた。リベラルアーツを「自由の学芸」と定義する斉藤氏も、既述のように中世ヨーロッパにおいて大学に入学する前の基礎教養として7つの科目があると述べている。
周知のように、「三学」は広い意味の国語であり、「四科」は広い意味の数学である。こうして見ると、リベラルアーツの根幹に数学が位置づけられていると考えることができるようにも思えてくる。もとより、「三学」に象徴される広義の国語がリベラルアーツの根幹をなすことは論を俟たない。
今後扱いたいテーマである国際バカロレア(IB)においても数学は必須であり、今後の学びにおいて数学はもっと注目されてよいと私は考えている。
ここで、上述した永野氏の本の中にある、「国語力に関わる国語と数学の興味深い関係」について紹介したい。
文系、理系を越えた学び、前提としての国語力の重要性につながる見解ではないだろうか。
本号のテーマであるリベラルアーツと国語力に関して、福井県立藤島高校で編まれた『近代とは何か』にふれておきたい。
「高校生のための基礎教養(第1集)」というサブタイトルのついたこの本については、本年一月の「学園長からのたより『折々のこと』」で概要については述べているものの、再度簡潔にご紹介したい。
 この本は、福井県立藤島高校の国語科の先生方が中心となり生徒向けテキストとして企画、編集された本である。藤島高校が文科省のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受け、SSH事業に取り組む中で、「教養」と「深く考える力」を養うことを目標に掲げ、この本の編纂に至っている。
この本は、福井県立藤島高校の国語科の先生方が中心となり生徒向けテキストとして企画、編集された本である。藤島高校が文科省のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受け、SSH事業に取り組む中で、「教養」と「深く考える力」を養うことを目標に掲げ、この本の編纂に至っている。
私の感想を最初に申し上げれば、学ぶことの意味を問いかける本であり、そして何よりも学ぶ喜びを味わわせたいという先生方の熱意が伝わる本ということになる。独自教材として発行されたこのテキストが、各方面から評判となり、一般の方々からの購入希望が寄せられる中、東京書籍から出版されることになったということもこの本の内容の充実ぶりを物語っている。
藤島高校では、「教養」を「断片的な知識、経験をつなぎ、高校で習得する知の全体像を俯瞰的に把握する力」と定義し、さらに、教養の核心は、「近代」と「科学」という二つのキーワードに理解を深めることとし、この本を作成している。リベラルアーツの考え方に立ち、いわゆる内外の古典(「classic」いわゆる「第一級の書」)の中から珠玉の文章を集め編まれたこの本は誠に興味深い内容となっている。
例えば、第一章「学び方について」には、五つの観点から学びを考えるとし、脇明子氏、養老孟司氏、立花隆氏、内田樹氏、団まりな氏の文章が引かれ、高校生にとってはもとより、教える側にとっても、「学び」について改めて思索を巡らす内容となっている。その中のひとつ立花隆氏の『東大講義 人間の現在① 脳を鍛える』の文章は、文系の人があまりにも理科の基礎的な知識に疎かったり、理系の人が文系の知識を著しく欠くのは双方共に問題であるとしつつ、文系理系双方を学ぶことの重要性が力説された内容となっている。立花氏は、リベラルアーツ教育という言葉をくり返し使用しながら、その大切さを強調している。
立花氏の文章を含め、この本そのものが、リベラルアーツの大切さを前提に編まれたものであり、その土台に国語力を置いていることも併せて窺える内容となっている。
高校の国語科の先生が中心になり、こうした労作を編まれたことに心より敬意を表しながら、今後の学びを展望する上でリベラルアーツが大切であることを改めて感じている。
本号では、リベラルアーツに関し、「『文系、理系を越えた学び』、かつ、『幅広く深い学び』」とする私なりの定義を出発点として論を展開してきた。
文系、理系を越えた学びは、これからより求められべきものであり、幅広く深い学びも、今後、より大切にされるべきであろうと思っている。そして、その土台をなすのが国語力であることも力説したい点である。斉藤氏の本や『近代とは何か』は、まさにそうした内容の本であると思っている。一方で、両著をとおして、リベラルアーツには、私なりの定義に加えて、学ぶ喜び、次なる学びの意欲を引き出す学びという要素があるようにも感じている。
幼稚園、小学校、中高からなる湘南学園が、それぞれの発達段階に応じて、リベラルアーツをどのように取り入れ、子どもたちの成長に資すかは、さらに検討され工夫されるべき点であろうと思われる。ただし、文系、理系を越えて幅広く学ぶことの意義については十分に受け止めるべきであり、併せて、国語の重要性は強調しても強調しすぎることはないと確信している。国語力の涵養については、幼稚園、小学校、中高それぞれにおいて、さらに、幼小中高の連携・協力を図りながら、その充実が図られなければならないと思っている。
最後に紹介したいのが、わが国を代表するリベラルアーツ大学である国際基督教大学(ICU)のリベラルアーツに関する以下の一文である。
リベラルアーツの真髄を見事に表現した言葉ではないだろうか。
リベラルアーツ。「文系理系を越えた幅広く深い学び、国語力を大切した学び」、加えて、「学ぶ喜びと学びへの意欲を得、自らの成長につながる学び」。幼稚園、小学校、中高からなる湘南学園が目指すべき教育において、その鍵はリベラルアーツに隠されている、その感を深くしている。