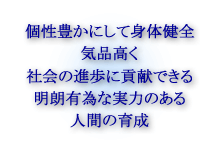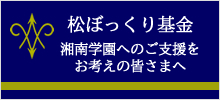シリーズⅡ 「国語力を考える(その11)」
「イギリスの教育 -国語教育を中心に-(Ⅱ)」-教科の中心として英語(国語)-
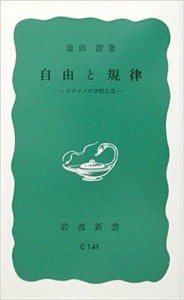 イギリスの教育と言えば、『自由と規律』(池田潔)がまず頭に浮かんでくる。池田氏自らのパブリック・スクールでの生活をもとに書かれたこの本は、パブリック・スクールの紹介のみならず、教育そのものに、またイギリス人の考え方にも考察を加えた内容で、何度も読み返した本の中の一冊である。
イギリスの教育と言えば、『自由と規律』(池田潔)がまず頭に浮かんでくる。池田氏自らのパブリック・スクールでの生活をもとに書かれたこの本は、パブリック・スクールの紹介のみならず、教育そのものに、またイギリス人の考え方にも考察を加えた内容で、何度も読み返した本の中の一冊である。
ご案内のとおり、パブリック・スクールは、イギリスの私立の中等教育学校であり、オックスフォードやケンブリッジにつながる教育機関としてイギリスの教育において大きな役割を果たしてきた。
私は、『自由と規律』をとおして、パブリック・スクールそのものについて、さらに教育について、教師のあり方について等、深い感銘とともに多くの示唆を得た思い出がある。
同じパブリック・スクールを描き、最近出版された本に『パブリック・スクール』(新井潤美)がある。
この本は、パブリック・スクールの史的変遷、さらには、小説などを通してパブリック・スクールがどのように取り上げられてきたか等を描きながら、パブリック・スクールの全体像に迫ろうとした本である。新井潤美氏もまた、女子パブリック・スクールで学んだ経験をもつ方である。氏が、パブリック・スクールに関し、むしろ課題や問題点を具体的に指摘しながら、より多面的にパブリック・スクールをとらえようとしている内容のこの本からも、多くを学ぶことができた。
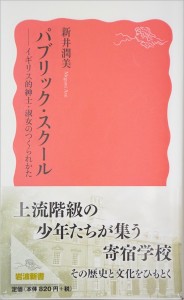 もとより、パブリック・スクールのみがイギリスの教育ではないことは言うまでもない。一方で、新井氏がパブリック・スクールに関し、「様々な変貌をとげており、伝統や精神も変化していること、また、そのイメージが今では批判や揶揄の対象となり、今後生き残るためには様々な困難があるであろう」とした上で、「しかしそれでも、パブリック・スクールがイギリスの文化において今でも大きな存在であり続けることは変わらないだろう」と述べていることは、パブリック・スクールの存在の大きさを改めて提示している感も否めないものがある。
もとより、パブリック・スクールのみがイギリスの教育ではないことは言うまでもない。一方で、新井氏がパブリック・スクールに関し、「様々な変貌をとげており、伝統や精神も変化していること、また、そのイメージが今では批判や揶揄の対象となり、今後生き残るためには様々な困難があるであろう」とした上で、「しかしそれでも、パブリック・スクールがイギリスの文化において今でも大きな存在であり続けることは変わらないだろう」と述べていることは、パブリック・スクールの存在の大きさを改めて提示している感も否めないものがある。
ところで、わが国の大学入試が欧米との比較で注目される中、イギリスの大学入試について、読売新聞に興味深い記事が掲載された。オックスフォード大学日本事務所長アリソン・ビール氏へのインタビューを中心にまとめられたもので、2020年度に導入されるわが国の新テストへの問題意識を背景に書かれた記事である。(2016年10月28日付 読売新聞)
記事の冒頭、「なぜ、人間の鼻の穴は二つなのに、口は一つなのか」「英国では4人に1人ががんで亡くなるが、フィリピンでは10人に1人。違いの要因は何か」という思いがけない問いが登場する。実は、この問いは、オックスフォード大学の面接試験で出た質問であるという。繰り返しになるが、意表をつく、答えに窮する問いと言うべきではないだろうか。
前号でも若干ふれたが、イギリスの大学入試では、高校段階までのいわゆるペーパーテストの成績(GCSE及びAレベル)、志望理由書、高校からの推薦書等、場合によっては適性テストや論文が課され、さらに上述の面接を経て合否が決定される。
記事によれば、アリソン・ビール氏の言葉として、教授は面接試験で、「正解を求めるのではなく、課題へのアプローチ、自分の考えを伝える力、創造性や好奇心の有無を見る」のだとある。さらに、「チュートリアルという個別指導に対応できる潜在力と意欲のある学生を選抜するために行う」ということであった。
イギリスの教育に関連し、今月(2017年7月)出版された苅谷剛彦氏の『オックスフォードからの警鐘』を興味深く読んだ。その中に上述の「チュートリアル」についての箇所がある。氏は、その内容について、「週1回およそ1時間、学生2、3人に先生1人、全8週間行われるもので、毎回エッセイ(論文)の課題が、指定された課題文献と共に出される。課題文献を読んで、毎回A4の用紙に10枚分くらいのエッセイを宿題として提出する」とした上で、チュートリアルについての氏の見解を述べている。
 この苅谷氏の主張は、上記記事でアリソン・ビール氏がわが国の入試と比較して述べる「入試も、知識の量や正誤だけでなく、想像力や批判的思考力などを問うものに転換すべきだ」という主張につながる内容との感を深くした。大学入試のあり方と大学における学び、前提にある中等教育及び大学双方の密度の濃い学びを含め、いわゆる高大接続のあるべき姿を併せて感じている。同時に、このような大学入試、さらには大学教育の土台となるのが、イギリスの教育、特にイギリスの国語教育にあると私は考えている。
この苅谷氏の主張は、上記記事でアリソン・ビール氏がわが国の入試と比較して述べる「入試も、知識の量や正誤だけでなく、想像力や批判的思考力などを問うものに転換すべきだ」という主張につながる内容との感を深くした。大学入試のあり方と大学における学び、前提にある中等教育及び大学双方の密度の濃い学びを含め、いわゆる高大接続のあるべき姿を併せて感じている。同時に、このような大学入試、さらには大学教育の土台となるのが、イギリスの教育、特にイギリスの国語教育にあると私は考えている。
なお、オックスフォード大学のチュートリアルに関しては、自身の入学から卒業までの経験をもとに綴った『わたしのオックスフォード』(川上あかね著)に、入学した川上氏が初めてのチュートリアルに臨む場面がある。
課題図書を示されエッセイのテーマが与えられた後、おずおずと「エッセイの長さ」を教授に尋ねると、長さは決まっていないとした上で、「勉強は、まあ一日十時間ぐらいを目安にするのがいいでしょう」と言われまず衝撃を受ける。さらに、実際のチュートリアルの場面では、持参したエッセイに関する教授の鋭い分析と次々に繰り出される質問に「シドロモドロ」になりながら、「フラフラになって」部屋を後にしたという感想が述べられている。
言うまでもなく、通常の講義に加えての毎週のチュートリアルである。そして厳しい試験も最後に控えている。大学は徹底的に学ぶ場であり、容赦なく鍛えられる場であることがこの本からもひしひしと伝わってくる。一方で、やがて、毎週、A4の用紙に手書きで六ページから十二ページのエッセイを二つ出し続けるというチュートリアルに慣れていく川上氏の様子も綴られている。
 前号から続くイギリスの国語教育に入る前に、上記新聞記事にあるオックスフォード大学の面接に関連した面白い本にふれておきたい。
前号から続くイギリスの国語教育に入る前に、上記新聞記事にあるオックスフォード大学の面接に関連した面白い本にふれておきたい。
その本のタイトルは『あなたは自分を利口だと思いますか?』(ジョン・ファーンドン著 小田島恒志・小田島則子訳)。副題として「オックスフォード大学・ケンブリッジ大学の入試問題」とある。
著者はケンブリッジ大学を卒業し、「現代中国やインドのドキュメントから医療問題や地球の仕組みを解いた科学書、児童書までジャンルを問わぬ博識をもって三百冊以上の本を出しているノンフィクション作家である」という。この本は、オックスブリッジ(オックスフォード大学とケンブリッジ大学)の面接での難問奇問に著者が解答を書き加えたまさに「解答付き問題集」なのである。
この本のタイトル「あなたは自分を利口だと思いますか」もまた面接の質問である。もし、みなさんが受験生であったら、この問いにどのように答えるだろうか。著者は、この質問に謙虚に「いいえ」と答えたら、言葉通りにとらえられて入学を断られるかもしれない。一方で、「はい」と答えたら、自分は正真正銘の馬鹿であると言っているようなものであるとしている。それでは、どう答えればよいと著者は言っているか、それは本に譲ることにし、この本の中で取り上げられている難問奇問から一部を紹介したい。
以下、「O」は、オックスフォードの、「C」は、ケンブリッジの略称である。
オックスブリッジにおける大学入試の面接は「インタビュー」(口頭試問)と呼ばれるという。上記の「インタビュー」の質問は確かに難問奇問と呼ぶことも可能であろうし、面白おかしく捉えることもできよう。一方で、こうした質問に答えることのできる高校生を育てているイギリスの教育もまた注目に値すると見ることもできるのではないだろうか。
本シリーズ四月号で紹介したフランスのバカロレアの「哲学」の問いとは異なるものの、上記のオックスブリッジの「面接」の問いを見ると、手強さという点ではイギリスもなかなかのものと言えそうである。
さて、話を本題に戻したい。
前号から国語教育を中心にイギリスの教育について考察している。
前号においては、イギリスの国語教育に関して、話すことを大切にする国語教育という観点で話を進めた。
イギリスにおける国語教育において「話すこと」を大切にするのは、「学習」が「社会」と深く関わり、その関わりの中で、話すこと聞くことが中心的な役割を担っているからというのがその主な理由であった。さらに、「話すこと」は「聞くこと」と密接につながっており、また「話すこと」は「考えること」と不即不離の関係にあるとみなされているということも注目した点であった。
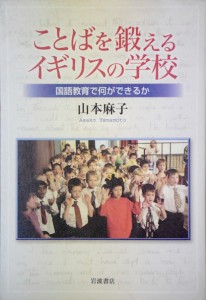 本号では、「読むこと、書くこと」について取り上げることとし、まず、「読むこと」から入りたい。本号においても前号同様『ことばを鍛えるイギリスの学校 国語教育で何ができるか』(山本麻子著)に主に依拠することを予めお断りしておく。
本号では、「読むこと、書くこと」について取り上げることとし、まず、「読むこと」から入りたい。本号においても前号同様『ことばを鍛えるイギリスの学校 国語教育で何ができるか』(山本麻子著)に主に依拠することを予めお断りしておく。
「読むこと」について言えば、イギリスでは、「小さいうちからどんどん読ませる」ことを徹底していること、そして、聞くことにおいても見られたように、「読むことにおいても能動的な面を重視している」こと、さらに、対象とする作品は「文学が中心」であるということは、まず述べておきたい点である。
聞くことにおいてと同様、読むことにおいても、初等教育の段階から高いレベルの内容が要求されている。
初等教育の5歳から7歳の段階で、すでに文学が「読むこと」の中心に位置づけられ、物語、詩、劇、絵本が奨励されている。さらに、印刷された情報、コンピューター画面に映し出された情報の読み方も学ぶ対象となっている。
初等教育の7歳から11歳でも文学の重要性は示されている。
その具体的な例として、著者山本氏は、十歳になったばかりの子息の授業風景を挙げている。150ページほどのテキストを一回の授業で10ページから15ページ進むという授業は、「教師が児童の誰かを指名して、一、二ページほど音読させ、全員にテキストの内容について細かい質問をし、理解できたかどうかをチェックし、難解な語が出てくると、音読中でもストップし、皆に意味を尋ねる」という内容だったという。その授業を見た山本氏は、氏が大学一年次に英文科の授業として受けた「英語講読」の時間と似ていたという感想を述べている。小学生の授業が、自らの大学時代の授業と重なるというところに氏も驚きの念を禁じ得なかった感がある。
初等教育の半ば以降のこの時期には、「読むこと」について、「文学として味わって読む」ことと「情報を収集するために効果的に読む」ことの二つが教えられるという。
後者の情報収集のための読みについては、「調べる対象の題材について、自ら適切な問いを発する」、「事実と意見を区別する」、「提示されている議論を批判的な見地から読む」ということを教えられる。山本氏は、これら三点について、氏が英米の大学院で英語で論文を書く際によく注意されたことだという感想を述べている。
氏は、初等教育段階の子どもが、これらのことを本当に理解しているかはともかく、早い段階からこれらの大切さを教えられ、練習を重ねるうちに次第に分かってくるのであろうという見解を示している。正しい方法を早い時期から学ぶということが後に大きな影響を与えていくことは山本氏ならずとも容易に想像できることであろう。
 中等教育の時期には、「特に英文学史上に名を残すような、十九世紀以前の主要な小説や詩、劇、あるいは、二十世紀前半の主要作品や名声を確立している現代作家や詩人の作品のうちのすぐれたものを読むべき」とされていることからも分かるように、古典を中心とした優れた作品にふれることが求められている。ちなみに中等教育全体では、シェイクスピアの作品は二つは取り上げることとされている。
中等教育の時期には、「特に英文学史上に名を残すような、十九世紀以前の主要な小説や詩、劇、あるいは、二十世紀前半の主要作品や名声を確立している現代作家や詩人の作品のうちのすぐれたものを読むべき」とされていることからも分かるように、古典を中心とした優れた作品にふれることが求められている。ちなみに中等教育全体では、シェイクスピアの作品は二つは取り上げることとされている。
また、この時期の学習、特に作品の鑑賞について、ナショナルカリキュラムでは次のような機会を与えられることが望ましいと記されている。
「作品で使われていることばや考え方が現在に影響を与えている事実について、その重要性を検討する機会。これは例として、ギリシア神話、欽定訳聖書、アーサー王伝説が挙げられる」「異なるメディアを使うことによって書かれたものがどのように変わるかを考える機会、これは、シェイクスピアの原作とテレビ化されたものとの比較などである」。一読してその高度な内容と窺えるものであり、イギリスの国語教育の目指す目標の高さを感じることができよう。
山本氏は、子息が十五歳の頃、英語の授業でシェイクスピアの『ロミオとジュリエット』に取り組んだ事例を紹介している。
学期初めに1960年代に作られた『ロミオとジュリエット』の映画を授業の何コマかをかけて鑑賞し、物語を一定程度理解した上で、脚本の鑑賞へと進んでいく。脚本については、教師の概括を経て詳細に読み込み、その後、学期の半ばを過ぎた頃に学年全体でバスで二時間ほどかけて、上演中の『ロミオとジュリエット』を観劇したという。その上で、映画と実際の舞台について、場面設定、演技、強調点の解釈の仕方などを比較している。このような経験を踏まえ、最後に、『ロミオとジュリエット』のテキストの内容について一幕ごとに試験が行われたという。こうした山本氏の話から、イギリスにおける「読むこと」についての奥の深さを感じないわけにはいかなかった。
「読むこと」について、補足すれば、イギリスにおいては「朗読」も大切にされている。前号でふれた「トーク」の試験、すなわち8、9歳時に、校長や他の教師を前に事前準備した資料をもとに発表し評価を受ける試験と同時期に、「詩の朗読」の試験もあったということを山本氏は述べている。
読むことに関してもう一言だけ補足すれば、多様な読みについてである。
文章読解に関し、子息が十四歳当時の先生が、「正しい答えというものはない」、「解釈は一つとは限らない」、「答えも一つとは限らない」と常に生徒に述べていたことに山本氏は新鮮な印象を持ったという。氏は、ナショナルカリキュラムに目を通し、子息の先生の見解が個人的なものではなく、中等教育の間に培う技能として教師間で共有されていることを知ることになる。
「書くこと」についても、イギリスの教育には、注目すべき点が見受けられる。
「書くこと」と「読むこと」はつながっており、「小さいうちからどんどん読ませる」ことに加え、「小さいうちからどんどん書かせる」ことが奨励されているというのは、まず指摘しておきたい点である。
また、誠に興味深いのは、イギリスでは、五、六歳の頃から「書く」価値を教えられるということである。書くことは、「記憶に留める」「考えを組織立て、発展させる」ために行うのであり、書くことは、「思考すること、調査すること、学習すること」を助けるために行うということを教えられるというのである。初等教育の早い段階から、子どもたちがどれだけ理解できるかは別にして、書くことの価値を伝えるイギリスの教育には驚かざるを得ない。
初等教育の中期以降について山本氏は以下のように記している。
上記はわが国で言えば小学校二、三年生から五、六年生にかけての時期の取組である。書くことに関し、この時期にこれだけ高い目標を掲げ実践していることには瞠目せざるを得ない。同時に注目したいのは、「想像力が必要になるが、逆に書いているうちに想像力が養える」という一節である。私にはこの表現が説得力をもって伝わってくる。
私事になるが、大げさに言えば「自分なりの文章修業」といったものを振り返りながら、「書く力」は「書くこと」によってしか高められないように思っている。何よりも、沢山書くことが大切であり、この点については、「量が質を凌駕する」、あるいは「量が質に転化する」と言ってよいように思っている。もうひとつ付け加えれば、書いた文章に感想を述べてくれる人が身近にいることが望ましいと考えている。私の場合は家族がその役であり、学術論文はさておき、「学園長からのたより」として連載している文章、あるいはかつて校長時代に毎月発行していた「校長室だより」、あるいは、2012年度一年間神奈川新聞に寄稿した文章等、全て家族に事前に目を通してもらい感想をもらっている。私にあっては誠に貴重な伴走者ということになる。教育の場であれば、感想を述べるのは言うまでもなく教師ということになろう。
いずれにしても、「書く力は書くことによって高められる」とする私の考えに立てば、「書いているうちに想像力が養える」とする考え方は、重ねてになるものの十分に納得できるのである。
話を初等教育の中期以降、すなわち「七歳から十一歳の時期のイギリス」という本題に戻したい。
山本氏は、子息が七歳から八歳にかけての時期に「本」作りをした話を述べている。
物語を創作し、A5判で十六ページ、半分は文章で、半分は本文に即した鉛筆書きの挿絵からなる「本」である。
山本氏は、三人の息子さんをイギリスの学校で学ばせた経験があり、教育に関する専門家でもある。氏は、このような本作りはイギリスでは比較的一般的に行なわれているとしている。氏が、その効用を「子どもたちが書く内容の構成の仕方、内容の提示の仕方を学んだり、文字や単語の練習、語彙を豊富にしたり、文法の確認にもつながることだ。そして、友だちと見せ合うことでアイディアを交換することにもなる」と述べているのは誠にその通りと申し上げるしかない。それを行っているのが七、八歳の子どもであるということに改めて注目するとともに、指導を行っている教師の努力、力量にも思いを馳せないわけにはいかない。

シェイクスピア
学校で現代版の映画を見て、内容を理解しつつメモをとり、舞台となる場所や敵対する家族の名前を変え、あるいは仮面舞踏会を仮面ディスコパーティーにするなど設定を変えながら、一方で、原作の筋は忠実に守り、四つの場面をA4判六ページにまとめたという。氏は、「新しい劇を初めから創作するわけではないが、想像力を働かせながら、会話で筋を進める練習にはとてもよいものだと思った」とした上で、「十一歳ぐらいの年齢でも書き方の下地を与えてやればできるものだとあらためて思った」と述べている。
特に、後半の「十一歳でも下地を与えてやればできる」という氏の言葉から、高い目標も手順を踏むことによって到達は可能であるということを確認する思いであった。
四月号の「バカロレア」の「哲学」のところでもふれたように、「どんな分野でもそうだが、格別の才能がなくても、多くの人間は『教えられればできるのだ』」は至言である。この言葉をかみ締めるとともに、併せて、子どもたちの可能性ということを私たちはさらに追求すべきとの感を強くしている。
フランスにおける文学重視、特に「詩」の重視はこのシリーズで以前述べた通りである。イギリスにおいても国語教育における文学重視の傾向はあり、その中で「詩」が、いずれの学習段階でも重視されている。
初等教育の初期においては、好きな詩を書き写すことから始まり、十歳頃からは創作に移行する。さらに初等教育の終わりから中等教育に進むと「詩」はさらに重視されていくようである。
イギリスの国語教育においては、文学的なものに加えてノンフィクション的なものも扱われている。
その例のひとつとして山本氏は新聞記事と報道文をあげている。
英語の時間に読んだシェイクスピアの戯曲『マクベス』をもとに、ダンカン王殺害をもじって「暗殺事件」と題し現代風の新聞記事にするという取組である。
十二歳での取組ということであり、生徒は作業に先立って、お手本として背景情報を含めた「事件」の詳しい「新聞記事」を手渡され、その記事を下地に、それぞれの生徒が工夫して作成するというものである。『マクベス』をもとにした現代風の新聞記事に加え、同じ内容のテーマでテレビのニュース・レポートの作成も行ったとしている。
その例のもうひとつは、実用的な文章の訓練としての手紙形式の文章の練習である。中等教育段階に入って頻繁に取り組むという手紙は、「詫びの手紙」、「依頼の手紙」、「リゾートの売り込みの手紙」などが例としてあげられている。「詫びの手紙」のテーマは、「宿題をやらなかったことに対する教師への詫び状」である。ただし、ただ詫びをいうだけでなく、宿題ができなかった正当な理由、つまり、どうしても避けられない事情があったことを示して、相手もこれなら仕方がない、と思わせるような説得の要素を入れるという条件が課されている。「売り込み」の手紙については、民宿の所有者という立場で「うちの民宿はすばらしいので、ぜひ休暇に使ってほしい」という条件が付されている。こうした手紙を数多く書くことにより、書く力はもとより、生きていく上での様々な力も培われるように感じている。
中等教育段階の十二歳頃には、いわゆる小論文作成も取組に入ってくる。その際、例えば、あるトピックに賛成か反対かを論じる時は、「議論のもととなる事実を書き出す」「事実と考えを分けて整理し、自分の見解を明確にする」「公正な見方をするために、それぞれの立場の長所と短所を根拠としてあげて論じる」ということが予め指導され、それぞれの生徒は小論文作成に入っていく。ここでも国語力を高めることはもとより、連動して、高等教育の準備段階としての中等教育の役割を意識した教育が窺えるのである。
これ以外にもイギリスに関し紹介したい点は数多くあるものの、二つに限定して述べてみたい。
ひとつは、「書くこと」と「読むこと」の関連である。イギリスにおいては、「話すことと聞くこと」が表裏一体であると同様、「書くことと読むこと」もまた表裏一体であることが強調されている。
「話すことと聞くこと」に関しては前号で述べたとおりである。
「書くことと読むこと」に関して、ナショナルカリキュラムには、「『物語』を書く力をつけるためには、『すぐれた小説について学んだ経験を生かす』ことが必要」とされ、また、「『ノンフィクション』を書く力をつけるためには「これまでに広範にノンフィクションを読んできた経験を生かす」等が記され、それに基づく指導が行われている。「書くことと読むこと」が表裏一体であることは私自身も感じていることでもあるが、イギリスにおいては、そのことが、ナショナルカリキュラムにおいてまさに示されているということになろう。
もう一つは、イギリスの初等学校の授業形式、わが国と比較しての教科書の有無についてである。
イギリスの初等学校では、わが国のように検定教科書を使うことはないということである。山本氏の子息が通った学校では、日本で「ノート」と呼ばれるものが、「ブック」と呼ばれていたという。
 イギリスの初等学校では、子どもたち自身が、学習記録帳を自分たちで作っていくのである。授業で配られたコピーやワークシート、さらには授業の内容に関する子どもたち自身の記録、感想、そうしたものが貼りつけられたり、手書きされたりしながら積み重ねられ、学習記録帳になる。それは、「ノート」であるというよりは「ブック」と呼ばれるにふさわしい感がある。なお、教科書のない授業、そして「ノート」が同時に「ブック」であるというのは、シュタイナー教育にもつながる教育上の一手法と言えるかもしれない。
イギリスの初等学校では、子どもたち自身が、学習記録帳を自分たちで作っていくのである。授業で配られたコピーやワークシート、さらには授業の内容に関する子どもたち自身の記録、感想、そうしたものが貼りつけられたり、手書きされたりしながら積み重ねられ、学習記録帳になる。それは、「ノート」であるというよりは「ブック」と呼ばれるにふさわしい感がある。なお、教科書のない授業、そして「ノート」が同時に「ブック」であるというのは、シュタイナー教育にもつながる教育上の一手法と言えるかもしれない。
教師の指示によるものもあろうが、子どもたち自身の創意工夫による記載も多々あるであろう「ノート」。教科書がないことの是非はここではひとまず措くとして、教科書がないことによって、「聞くこと」や「書くこと」には、より注意力、言い換えれば主体性が必要になるのではないだろうか。そこには、「聞く力」に加え、「書く力」がより育まれていくことが十分に想像できるのである。
二回にわたり、イギリスの教育特にイギリスの国語教育について考察してきた。
山本氏の本の中にイギリスの教育における英語、すなわち国語の重要性を述べた箇所がある。「なぜ英語がこれほど大切なのか」と氏は問いかける。そして、英語以外の教科であっても、「英語の力こそが、その教科の内容や考察にとって決定的になるからだ。」と言い切っている。
当たり前といえばこれほど当たり前の言葉はないと受け止めつつも、翻って、わが国の教育においてそれだけ国語が大切にされているかどうかを自問自答せざるを得ない。
「英語以外の教科であっても、英語の力こそが、その教科の内容や考察にとって決定的になる」。この言葉を反芻しながら、教育の土台としての「国語」のもつ意味を問い続けていきたい。
最後に冒頭に引用した苅谷剛彦氏の『オックスフォードからの警鐘』の一節に再度ふれたい。オックスフォード大学で最も重視されている教育形態「チュートリアル」について、苅谷氏は、「強制による主体(subject)づくりの学習」と述べた。
本来目指していたはずの方向からどんどん離れていく感のあるわが国の高大接続、あるいは、ただ子どもたちの活動があればよいかの如く見えなくもない上辺だけのアクティブ・ラーニング論議。こうしたわが国の動きを見る中で、加えて、先月からの二回にわたるイギリスの国語教育についての考察を振り返りながら、「強制による主体(subject)づくりの学習」という言葉の重みを深い感慨を覚えながら受け止めている。