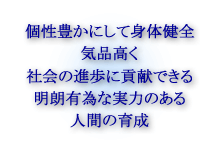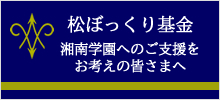シリーズⅠ 「澤柳政太郎のこと(その4)」
 過日、学園でお会いしたある方から、この連載をとおして澤柳が興味深い人物であることを知ったという話を伺った。他にも、「名前は知っていたが」と言われる方もいれば、「大事な人物なんですね。でも名前も知らなかった」と言われる方もおられる。総じて、澤柳は一般にはあまり知られていない人物ということになる。
過日、学園でお会いしたある方から、この連載をとおして澤柳が興味深い人物であることを知ったという話を伺った。他にも、「名前は知っていたが」と言われる方もいれば、「大事な人物なんですね。でも名前も知らなかった」と言われる方もおられる。総じて、澤柳は一般にはあまり知られていない人物ということになる。
成城学園、玉川学園、明星学園のすべて、あるいはそのひとつをご存知の方は少なくないと思われる。それらの学園は澤柳政太郎なしには存在しなかったと言っても過言ではない。一方で、わが国の公教育の確立に関しても、「もし澤柳がいなかったら」と考える場面、政策が多々存在する。澤柳の偉大さについて、新田の言を借りたい。
すでに繰り返し述べているように、湘南学園には、澤柳政太郎の精神が底流に流れている。何より、そのことには感謝と誇りを覚えており、「澤柳をたどる旅は、湘南学園の未来を考える旅」でもあると考えている。
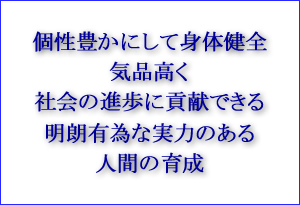
湘南学園 建学の精神
三回にわたる考察において、成城小学校設立における4つの方針の中の「個性尊重の教育」、「自然と親しむ教育」、「心情の教育」、それぞれが目指したものと、本学園の建学の精神の対比を試みた。その対比の中で、上記の3つの方針は、本学園の建学の精神の前半部分、「個性豊かにして身体健全 気品高く」に相当程度重なっていることが明らかになった。
高潔な人格、誰もが認める実務能力と指導力、豊かな国際性を備えた澤柳政太郎は、絶えざる自己研鑽と旺盛な研究心を生涯貫いた人物であり、実務家としても教育者としてもまさに類い稀な人物であった。その彼が後半生をかけた成城小学校の設立の趣旨と本学園の建学の精神が重なることは、本学園の誉れであり、何よりも大切にすべきことと思われる。
ところで、私が澤柳をとおして建学の精神を考えている理由の中に明治学院大学とのかかわりがある。
2008年度から四年間、明治学院大学外部評価委員として大学について考える機会を得た。同時に、委員のひとりとして、まとめ役をつとめられた立命館副総長本間政雄先生、あるいは当時のICU学長鈴木典比古先生とは四年間ご一緒し、多くを学ばせていただいた。実はそれに先立ち、2004年から三年間勤務していた県立舞岡高校でも明治学院大学とは深いかかわりがあった。校長として、高大連携締結に向けてのお願い等で伺い、締結後は交流ということで、当時の学長大塩武先生始め明治学院大学の方々に懇切なご指導を賜わった。
ちょうどその時期、明治学院大学では、「ブランディングプロジェクト」が進行中であった。幸運にも、私はその時期に明治学院大学とかかわりをもつことができたのである。
プロジェクトは当時の学長大塩武先生の強い思いで進められていた。その頃かかわりをもたせていただいたことで、プロジェクトを牽引された佐藤可士和さんの「ロゴマーク作成」に関する講演、さらには同じくプロジェクト推進役のひとり天野祐吉さんのお話等をお聞きすることができたのは僥倖以外の何者でもない。
ブランディングには、当然に象徴となるものが必要になる。それは何であったか。
結論を申し上げれば、ブランディングプロジェクトの中心に据えられたのは、「Do for others」という言葉であった。「Do for others」は、聖書の中にある言葉であり、明治学院大学の創設者ヘボンが生涯大切にした言葉でもあった。ヘボンの信念であり彼の生き方そのものとも言うべきこの言葉に大塩先生は着目されたのである。ヘボンは、宣教師として来日、医師としても活躍し、また、わが国最初の本格的な和英・英和辞書と言われる「和英語林集成」の編纂でも知られている。そして明治学院大学の創設と深くかかわる人物でもある。
大塩先生は、創設者ヘボンが大切にした「Do for others」をブランド再構築の根底に据えられ、明治学院大学のブランディングを推進されていた。その取組の中から佐藤可士和さんの「『MG』のロゴ」が誕生し、「Do for others」が改めて建学の精神としてしっかりと根付くことになったと私は理解している。
建学の精神を基礎に据え、ブランドを再構築するこの一連の取組は、佐藤可士和さんの「『MG』のロゴ」、天野祐吉さんの軽妙な中に本質を衝くお話と共に強く印象に残り、深く心に刻まれた。
その後、校長として勤務した県立湘南高校、あるいは教職課程を担当した北里大学で、学校経営や学生の指導において、建学の精神を再確認することの意義、建学の精神を磨くことの大切さを伝えてきた。「建学の精神」(湘南高校では初代校長赤木愛太郎先生のいわゆる「赤木イズム」、北里大学では学祖北里柴三郎の考え方)に着目しながら、自分なりに学校の発展及び生徒や学生の成長を図ることに努めてきたのは、明治学院大学での経験によるところも大きいのである。
湘南学園には、他に誇り得る優れた建学の精神がある。澤柳をとおして、その建学の精神を見直し、建学の精神に学び、建学の精神を磨くことの意義はとりわけ大きいものがあると考えている。
ここで、本題である成城小学校の設立の4つの基本方針の最後の「科学的研究を基とする教育」の考察に入りたい。
先ほど、私は、「澤柳をたどる旅は、湘南学園の未来を考える旅」でもあると述べた。既述の「個性尊重の教育」、「自然と親しむ教育」、「心情の教育」という3つの方針は、本学園の建学の精神の前半部分、「個性豊かにして身体健全 気品高く」と重なっている。
そして、成城学園のもう1つの方針である「科学的研究を基とする教育」は、本学園の後段部分「社会の進歩に貢献できる明朗有為な実力のある人間」、とりわけ「社会の進歩に貢献できる実力のある人間」とかかわりをもつと考えている。
もとより、本学園の建学の精神に澤柳政太郎と福沢諭吉の影響が見られることは、既に何度も述べているとおりである。建学の精神全体について、とりわけ後段部分については、福沢精神の影響が強いと考えてよいであろう。とはいえ、後段部分にも澤柳の影響が及んでおり、その影響には、本学園の今後を考える上で重要な中身が含まれていることから、以下、論考に入ることにしたい。
「科学的研究を基とする教育」に関し、澤柳は、成城小学校設立の趣意書において、どのように述べているだろうか。澤柳は、小学教育に関する研究は、他の教育よりは盛んであるが、多くは抽象的、或いは西洋丸写しであること、その理由として、学者の研究が付焼刃的なものが多いこと、さらに学者と実際に教育に当たるものの間に大きな溝が存在していることを挙げている。その上で彼は以下のように述べている。
この言葉通り、成城小学校は、「理論化せる実際、実際化せる理論即ち真の意味の研究的学校」、言葉を変えれば、「研究的学校」あるいは「実験学校」として目覚しい成果を収めていく。

澤柳政太郎
研究と実践を両立する上で重視されたのが、児童の発達段階に応じた指導であった。
ひとつの例として「春学年と秋学年の一学年二重学年制」の導入がある。これは、入学に当たっては、前年の九月までに生まれた児童を四月に受け入れ、九月から当年四月までに学齢に達した児童は九月に受け入れるというものである。発育上の差をできるだけ押さえようという考えから取り入れられた制度である。
もうひとつの例として「聴方」の導入をあげておきたい。通常、「聴き話す」よりも「読み書き」が重視されるため、従来の国語科は「読方、読書、綴方、書方」から構成されていた。児童の発達の原理に立てば、「読み書き」よりも「聴き話す」ことの方が先であることを重視する澤柳は、「聴方科」を特設し、そのための教材の開発も行っている。「二重学年制」、「聴方科」、いずれも発達段階に応じたきめ細かな指導が裏付けられる内容ではないだろうか。
成城小学校の教育は児童中心の教育であり、それは何よりも客観的な裏付けを伴った上で行われる教育であった。客観的な裏付けを伴う教育が、「科学的研究を基とする教育」につながることは改めて申し上げるまでもないことと思われる。そのことに関連し、開校後間もなく、澤柳が極めて熱心に取り組んだ事例に児童語彙の研究がある。
澤柳は、児童の知識・能力を把握し、その発達段階に応じて適切な教育を行うことが重要と考えていた。児童語彙の研究は、教育の基盤は「言語」能力にあるということから、小学校入学時の児童の語彙力をできるだけ正確に把握しようと考え、調査研究に及んだものである。
児童語彙の研究に関し、もうひとつ付け加えておきたいのは、澤柳の問題意識が、米国で発行された教育心理学の雑誌を見て芽生えたという点である。米国では三歳児対象に行われた児童語彙調査に関心をもち、わが国においては小学校入学時の児童を対象とすることに大きな意味を見いだし、実行に移している。
外国の研究成果を踏まえて、その成果をわが国の現場の教育実践に生かそうとする姿勢は、今日においても大いに参考になるように思われる。
話は逸れるが、私が校長として勤務した高校にある数学の教師がいた。彼は、あるスポーツに取り組んでおり、自らもプレーヤーとして活躍し、またそのスポーツの部顧問もつとめていた。研究熱心な彼は、外国に出かけたり、外国の専門書等を取り寄せたりしながら強化のための研究に取り組んでいた。当然に英語の文献を読むことになる。
研究熱心なのは当該スポーツだけではなく、専門の数学においてもまた同様であった。国内の研究会にしばしば足を運び、また外国の教科書を取り寄せて研究していた。彼によれば、例えば「微分」の導入においては、米国の教科書の方が分かりやすいということであった。実際に、「米国式」の「微分」導入の授業を見せてもらったことがある。私は「なるほど」と何度も頷きながら授業に聞き入った。実は、その授業参観には、高野連の関係で知り合った全国紙のベテラン記者の方も同席されていた。わが国最難関とされる大学を卒業されたその記者の方が、授業終了後開口一番「あのような授業を受けていれば数学がもっとできたのに」と言われていたのは今も印象に残っている。
「外国の研究成果を踏まえて、それをわが国の現場の教育実践に生かすことは今日においても参考になる」と上述した。「微分」導入の授業はその好例かもしれない。
話を児童語彙の研究に戻したい。
研究の結果、小学校入学時の児童が身につけている語彙数は、当初の二千五百語から三千語という予想を遥かに上回り、平均四千語という結果を得た。澤柳はこの成果を教育実践に生かしていくことになる。同時に、この研究は、成城小学校研究叢書の劈頭を飾ることになった。
研究的学校(実験学校)としての成果を集大成した成城小学校研究叢書は、大正八年から十五年にかけて全部で十五巻発行され、全国にもその成果を発信していった。その中で、大正八年から九年にかけての二年間に発行された本のタイトルのみを以下列挙したい。
『児童語彙の研究』、『算術教授革新論』、『算術新教授法の原理及実際』、『尋常小学校国語読本の批評』、『玩具による理科教授』、『児童心理に立脚した最新理科教授』、『お伽の新研究-聴方教授の提唱-』
短期間にこれだけの本が研究と実践を伴った成果として公刊されている。まさに「理論化せる実際、実際化せる理論即ち真の意味の研究的学校」としての面目躍如と言うべきであろう。
この点に関する新田の言を以下引用したい。
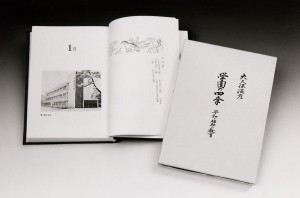
学園の四季
ここで、前号でも紹介した本学園第四代園長大久保満彦先生の『学園の四季』にふれておきたい。
この本の中に「湘南学園論叢」と題する一節がある。
1959(昭和34)年7月14日の日付には、「きょうかねて計画していた『論叢』第一号ができて来た。すでに七月はじめ、わたしはご父兄の皆様に次のような手紙を差出していたが、いろいろの機会にいっそうのご協力をお願いして、学園教育のための研究と教育効果向上の実践につとめねばならない。」と記されている。
「ご父兄の皆様」にあてた手紙には、「今後教員の研究をそだてる意味で、経費御多端の際、恐縮には存じますが、ご家庭で購入していただきますればさいわいに存じます。」と購入依頼の記述がある。教員の成果物である『論叢』の購入依頼、それなりの覚悟がなければできない試みであろう。おそらくお願いするに足る自信があればこその依頼であったのではないだろうか。そして、これこそP(parents)とT(teachers)の協働の手本ではないだろうかと思ったりもしている。
目次を見ると、最初に大久保先生の「親子関係~両親の態度と子どもの反応」という巻頭論文があり、さらに、「幼児の自然観察は如何に指導すべきか」、「学習興味調査(共同研究)~学園児童四・五・六年を対象とした実態的考察~ 小学校教育研究部」という論文、あるいは、「英語科より見たる学習能率の一考察 その一(主として高校生を中心に)、その二」といった論文が掲載されている。

小学校公開研究会
『成城小学校研究叢書』、『湘南学園論叢』、お気づきのとおり、大久保先生は、澤柳政太郎の、そして成城小学校の顰に倣ったものと思われる。研究と実践、澤柳の表現を用いれば「理論化せる実際、実際化せる理論」という取組が本学園でも行われていたわけである。
大久保先生が「ご父兄の皆様」にあてた手紙の中から、ぜひ紹介したい部分がある。

大久保満彦
「学園の教育をよりよくしたいという教員一同の意気込み」、「研究と実践の一体化」、「幼小中高全体での取組」。『論叢』の内容および大久保先生の言葉は、われわれに多くの示唆を投げかけているのではないだろうか。
繰り返しになり恐縮だが、澤柳政太郎の成城小学校設立の方針の4点目、「科学的研究を基とする教育」の真髄が当時の本学園には引き継がれていることが、大久保先生の文章から読みとれるのである。
今号のテーマは、「科学的研究を基とする教育」であった。
それは、「研究と実践の両立」を目指す教育であり、「客観的な裏付けを伴った児童中心」の教育であった。「理論化せる実際、実際化せる理論即ち真の意味の研究的学校」である成城小学校は目覚ましい成果を収め、明星学園創立の赤井米吉、玉川学園創立の小原國芳等の優れた教育者を育てていく。
本稿では、冒頭において、「科学的研究を基とする教育」は、本学園の建学の精神の後段の部分「社会の進歩に貢献できる明朗有為な実力のある人間」、とりわけ「社会の進歩に貢献できる実力のある人間」と関連性をもつことに言及した。
ところで、成城小学校創立が1917(大正6)年、その翌年第一次世界大戦が終結している。世界的に見ても、わが国においても、社会や政治にそれまでとは異なる変化が見られつつあった。民衆の社会や政治に占める意味の重要性、言い換えれば、民衆の社会や政治への影響力の増大が見られるようになる。そのことは、当然に教育と連動することになる。
澤柳が成城小学校で行った取組、それは、研究と実践が一体となったものであり、何よりも児童中心の教育であった。もとより、時代の変化を敏感に感じ取っていた澤柳は、時代の変わり目にあって、次代を担う人間をどのように育てるべきかを真剣に考えていた。義務教育の質を高める、言い換えれば小学校教育の充実を図ることの重要性を澤柳は誰よりも感じていたはずである。澤柳が、成城小学校を実験学校、研究的学校と位置づけていた意味のひとつはそこにある。詳細は次回に譲るものの、子どもの主体性、自発性を重視するダルトン・プランを研究し、成城小学校の教育に積極的に導入したことなども、実験学校としての自覚と同時に、「社会の進歩」に貢献できる、「実力のある人間」の育成と関連があると私は考えている。
なお、研究的学校(実験学校)としての成城小学校の位置づけについては、既に繰り返し指摘しているところではあるものの、その点について澤柳自身が分かりやすく述べている一文を紹介しておきたい。引用文は、後述の『教育問題研究』第六十号(大正十四年三月)に発表された「自分の学校」という文章の一部である。
成城小学校を見て、強く感じるのは、澤柳を含めた成城小学校の教師集団の研究と実践への取組姿勢である。
澤柳のもとで『成城小学校研究叢書』が大正八年から十五年にかけて全十五巻発行されたことは先に述べたとおりである。その後、小原國芳が成城小学校主事に就いてからは、小原が中心となり『教育問題研究』という機関紙が発行されることになる。
研究の成果が十分に検証されてから発信することが望ましいと考え、発信にはやや抑制的だった澤柳と異なり、小原は、成城小学校の成果を積極的に発信したいという姿勢であった。そのこともあり、『教育問題研究』は毎月発行され、澤柳がかかわったものだけでも、大正九年四月から昭和二年八月までに89号発行されている。研究と実践の中身が如何に濃かったかが窺える頻度と内容である。澤柳は、ほとんど毎号寄稿していたと言われるが、最初の四号までに澤柳が寄せた論文を紹介しておく。
澤柳の精力的な執筆も目を見張るものがあるが、他の教師と共に毎月発行し、研究と実践の成果を問い続ける教師集団の取組には頭が下がる思いである。
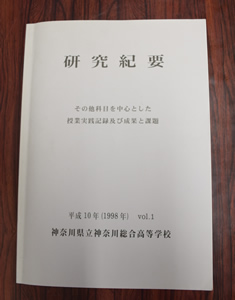
神奈川総合高等学校 研究紀要
開校三年目に「研究部」設立の提言があり、翌年、新たな校務分掌として設置された。「研究部」は、当時としては珍しかった学校評価を行い、また全国向けの研究発表大会を主宰した。さらに、「調査・研究」、「教育活動の成果の集積」もその役割に入っていた。単位制ならではの数多くの学校設定科目がある中、授業実践記録をまとめた『研究紀要』を発行したことも「研究部」の取組のひとつであった。
学校設定科目(その他科目)は、それまでには見られない新たな科目であり、担当者は自主教材を作成しながら、授業に工夫を凝らしていた。その授業実践の記録、教材を集積したものが『研究紀要』である。ちなみに、創刊号(vol.1)には、当時150以上設置されていた科目の半数近くを占める学校設定科目の中から、「作品購読」、「比較文化」、「プログラミング」、「ソルフェージュⅠ」、「基礎演技」等10科目について掲載されている。
公立ということで異動が避けられない中、異動があっても当該科目の授業を継続することができるように、また、他校においても活用していただけるようにという狙いで、『研究紀要』は発行された。したがって、その中身は、授業計画、授業内容、使用教材等を網羅した極めて実践的な内容から構成されていた。
私も含め当時の神奈川総合高校の教師集団の思いが窺える『研究紀要 vol.1』(1998年)の冒頭の一部を引用したい。
幸いにも当初の教師集団の思いはその後も引き継がれ、扱うテーマや内容は一部変更がみられるものの、『研究紀要』は、現在まで毎年発行が継続されている。
開校準備そして立ち上げと私が関わった五年間は、私自身が「研究部」の設立を提言したこと、設立後は研究部のチーフとして新たな試みに力を注いだことと併せ、何よりも研究と実践の両立を目指した日々に他ならなかったと今改めて思い起こすことができる。そして、その五年間が私にとってかけがえのない財産となったことも間違いのないことである。
成城小学校設立の方針の4番目「科学的研究を基とする教育」は、本学園の建学の精神の後半部分「社会の進歩に貢献できる明朗有為な実力のある人間の育成」、特に、「社会の進歩に貢献できる実力のある人間の育成」と関連していると本号の論考からも私は考えている。
「社会の進歩に貢献できる明朗有為な実力のある人間の育成」のためには、教える側の教師個々人が、そして教師集団が何をなすべきか、成城小学校の取組並びに大久保先生の文章は、私の神奈川総合高校でのささやかな経験とともに、われわれの今後に重要な問いを投げかけているのではないだろうか。
やはり、「澤柳政太郎をたどる旅は、湘南学園の未来を考える旅」と言えそうである。