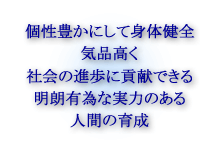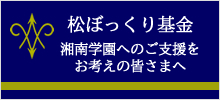シリーズⅠ 「澤柳政太郎のこと(その5)」

澤柳政太郎
「湘南学園の明日を考える」というタイトルの下、シリーズⅠとして四回にわたり澤柳政太郎を取り上げてきた。澤柳について考察する中で、特に、私自身大いに誇りにしている本学園の建学の精神への影響には、改めて多くの気づきを得ることができ、また、湘南学園の今後を考える上での貴重な示唆を得ることができた。
本号においては、教員を支える教育政策について及び学問研究あるいは研究者のあり方についての彼の考え方、関連して「澤柳事件」にふれ、さらに今後の本学園のグローバル教育との関わりも含め、彼の豊かな国際性にもふれてみたい。なお、澤柳については本号をもって稿を閉じたい。
今月初めに北里大学の教え子から教員採用一次試験の結果についての連絡が入った。うれしい知らせもあれば、捲土重来を期すという連絡もあった。
八月は、教員採用二次試験の月でもある。十数年前県教育委員会に勤務した数年間は採用する側の立場で、あるいは北里大学で学生を指導した際は教員を目指す学生をサポートする側の立場で、教員採用試験に関わってきた。採用する側の立場では会場準備から試験まで多忙を極める月であり、送り出す側の立場では、二次試験に向けての模擬授業や模擬面接の指導で学生と向き合う月であった。このように、八月は、教職希望者、教職希望者を指導する者、採用に関わる者、それぞれにとっての「暑い(熱い)月」」なのである。
北里大学では、教職課程担当として、都県や政令市の採用担当の方と話をする機会が少なからずあった。どの採用担当の方も、意欲のある優秀な人物を迎えたいという点では意見が一致していた。そして、学生対象の説明会においても、採用担当の方は、その点を力説されていた。
昔もそうであったように、現在も教職を目指し、熱心に研鑽に励んでいる人々が大勢いることは紛れもない事実である。一方で、昨今の教師を取り巻く厳しい環境、民間の景気動向等は、教員採用に影を落としているように思っている。
教育が国家百年の大計であることは誰もが認めるところであろう。その教育を担うのは教師であり、教育において教師の果たす役割は非常に大きいものがある。意欲ある優秀な人物を教育界に受け入れるための条件整備に国も地方公共団体も、そして私学も、今こそ本腰を入れて取り組むべき時期にあるのではないだろうか。
澤柳政太郎は、明治二十四年に大日本教育会夏期講習会で、「教員ハ愉快ナル職務ナリ」という講演を行っている。当時澤柳は新進気鋭の文部大臣秘書官であり、新田によれば、「小学校教員が自らの職業に誇りと喜びと安心を持つように激励するため」の講演であった。
事実、彼はその講演において、教育は有益な仕事である、教育は困難な仕事であるからやり遂げた後の達成感が大きい、個人の創意工夫の余地がどの職業よりも大きい、能力と仕事の結果が家柄や肩書に左右されない等の理由を述べ、講演の狙いに沿う話を行っている。一方で、講演の締めくくりにおける澤柳の話を新田は以下のように解釈している。
新田の解釈による上記引用箇所は、報酬に関しては措くとして、今日にも当てはまる面が否定できない内容にも思えてくる。「教員たちが安心し、誇りをもって職務に専念できる」ための教育政策、条件整備の必要性。講演から百十余年経った現在に澤柳の声が届いてくる感がある。
ところで、わが国教育界に多大な貢献を行い、誰もがその存在の大きさを認める澤柳ではあったが、彼の人生が順風満帆だった訳ではなかった。例えば、中学を卒業したばかりの長男勇太郎を病気で失ったことはその一例である。また、「修身教科書機密漏洩事件」もその一例になろう。後に復職するものの、この事件で彼は文部省を一度は辞任することになる。事件のあらましは以下の通りである。
大木喬任文部大臣の下で秘書官をつとめた澤柳は、大木が文部大臣を辞任し、枢密院議長に就いたことに伴い、秘書官を辞し、大臣官房図書課長に就いた。
大木は、大臣を辞めた後も、澤柳の学識や見識に深い信頼を寄せ、澤柳に教育に関する最新の情報等を学ぼうと考えていた。一方、澤柳も大木の度量の大きさに深い尊敬の念を抱いていた。大木の誘いもあり、大木の邸内にあった空家に移り住むようになり、庭伝いに交流をもつようになったという。

大木喬任
大木は修身教科書に一家言をもち、自ら教科書を編集したいというほどの強い関心をもっていた。大臣として多くの検定教科書を見てきた大木は、退任後も、修身教科書への関心が高く、状況を澤柳に尋ねたという。澤柳は、検定の標準と現時点での検定合格書一覧を書いたメモを大木に渡したが、大木はそのメモうっかり書斎の机の上に置いたまま部屋を離れてしまった。たまたまその時に大木を訪問した新聞記者が書斎で待たされている間にそのメモを見つけ、密かに写し取り、通信社に通知した。このスクープは、各新聞社に大々的に報道されることとなった。結局、大木は枢密院議長を辞任し、澤柳もまた文部省に辞表を提出し、依願退職となった。
この事件を巡っては、澤柳に同情する声が多かったという。そうした声に対し、澤柳は、一切の責任は自分にあり、その時は気づかなかったものの明らかに機密漏洩であるとし、同情論を排している。ただし、今回の経験を将来に生かしたいと述べた上で、退職後は、あらゆる招聘を断り、読書や翻訳に没頭し、いわば修行僧のような生活を送ったと言われている。
「清廉潔白」「公平無私」は、澤柳が生涯貫いた姿勢である。
澤柳は、教育者として、また教育行政担当者として、常に多方面へ関心をもち研究を怠らなかったことは既述のとおりである。同時に、新田の言によれば、「相手が大臣であろうと政府高官であろうと、間違っていると思われるものには正確な資料を提示して反論するのを怠らなかった。」、「理を尊び、非理を糾す姿勢は、個人的な感情に左右されず、また相手の役職地位の上下に拘わらず、一貫して常に変わるところがなかった。」
そうした澤柳の姿勢は、教育学研究者に対しても同様であった。
たとえば、明治四十二年に著した『実際的教育学』において、澤柳は、「予を以て見れば教育学は他の科学に比し最も幼稚なるものであると思ふ」、あるいは、「科学的価値のある研究は之を見ることが出来ない」等と述べ、当時の研究者の姿勢を辛辣に評している。一方で、彼は、従来の教育学があまりにも現場と没交渉であることにも懸念を示している。
この本の出版は、大きな反響を呼び、教育学研究者からの強い反発を招いた。教育学研究者からすれば、自分たちの存在が全否定されたようにも受け取れる内容であったからであろう。
澤柳は、当然にそれを予測し、寄せられた反発、意見には,ひとつひとつ丁寧に根拠を挙げて説明し、論理の不整合や、学問についての知識の不足等については徹底的に反撃したと言われている。澤柳は、『実際的教育学』を著した後、「教育学批判」と題した連続講演でも、当時の高名な教育学研究者の著作について、次々に厳しい批判を行っている。
こうした澤柳の姿勢の背後にあるものを新田は以下のように評している。
澤柳は、何度も述べているように、わが国の教育の発展を誰よりも願っていた人間である。彼が文部行政において取り組んだ種々の政策からも、成城小学校における実践からもそのことを読み取ることができる。その彼の教育学研究者に対する上記の言動も、そのことと軌を一にしている。すなわち、新田の言を借りれば、「研究と教育に責任のある人たちが是非とも発奮して日本の教育界の発展のために努力してくれるようにというのが、澤柳の一連の教育学批判の狙いであり、また願いであった。」
上述の研究者に対する姿勢に関連し、ここで「澤柳事件」について簡潔に記したい。
澤柳は、大正二年五月に京都帝国大学総長に就いた。澤柳を高く評価していた当時の文相奥田義人による強い推薦によるものであり、課題の多い京都帝大の再建を託しての登用であった。課題の主たる理由に不適任教授の存在があった。老齢により研究が疎かになっている者、私立への出講や出版優先等で研究者・教育者としての責務を果たしていない者が散見された。一方、西田幾多郎のように、極めて高い業績を上げながら、東京帝大の本科ではなく選科卒で、留学経験がないという理由で教授に任命されるのを拒まれているという事実もあった。

京都帝国大学
澤柳が教授会の抵抗を押し切って西田幾多郎を教授に任命したことは既に記した通りである。一方で、澤柳は、新田によれば「老齢で教授としての責務が果たせない人、大学教授には不適任だが民間に出れば素晴らしい活躍が期待できる人たち、ジャーナリズムでの名声と収入を追求する人たち」に教授を勇退し適切な職に移るよう、個別に交渉し説得したのである。その結果、当時、分科大学であった京都帝大において、医科大学1名、理工科大学5名、文科大学1名の計7名の教授が澤柳の説得を受け入れ勇退した。
以上が事実である。この勇退勧告と結果は、文部省関係者や学界の指導者から全面的に支持され、京都帝大の当該三分科大学からも特別異議が出ることはなかった。これで終われば、「澤柳事件」はなかったことになる。
しかし、一人の勇退勧告もなかった法科大学が、勇退勧告が法科大学にも及ぶことを懸念し、「意見書」を提出することになる。いわゆる「事件」の発端である。その意見書の最大の論点は、教授の罷免は教授会の同意を得る必要があるかどうかということであった。
澤柳は、当時の法律「大学令」にその規定はないので、その要求には応じられないこと、大学教授には第一流の学者として研究と教育に全力で臨み前進を怠らないでほしいこと、自分は政府権力者などの干渉や世間の圧力によって教授の任命や罷免を行うようなことは断じてしないこと、精神身体上などの故障等で研究心が衰え努力も追いつかなくなり学問上の進境に見込みがなくなったら後進に道を譲ってほしいこと等を回答した。澤柳は教授会には誠意をもって対応し、会合を重ね、また文書による回答にも応じた。しかしながら、結局、合意には至らず、最終的に澤柳は法科大学教授一同の辞表を受け取り、澤柳自らも辞表を書き、奥田文相の判断を仰ぐことになった。
奥田文相は「教授ノ任免ニ付テハ総長カ職権ノ運用上教授会ト協定スルハ差支ナク且ツ妥当ナリ」という覚書を示し、その覚書に双方が同意し事件が決着した。教授会は全員が辞表を撤回し、澤柳が辞職するということで幕を閉じたのである。
私は「澤柳事件」について論評する立場にはなく、また論評できる力量も持ち合わせてはいない。ただし、“澤柳の生き方、彼の研究と実践双方への真摯な取組姿勢、『実際的教育学』、「教育学批判」等における主張”と“七人の教授への勇退勧告”には一貫したものがあるように感じている。また、この一連の経緯を「澤柳事件」という呼称で表現することにもいささか疑問を呈したい感も否めないものがある。
なお、澤柳と東京帝国大学で同期であり、わが国の国語(明治期の日本語)確立に多大な貢献を行った上田万年の言葉を引用し、「澤柳事件」については筆を擱きたい。
「澤柳君が京都帝国大学に於て一大廊清を断行せんと試みて失敗したのは一つには当時の文部大臣奥田義人氏の不誠意に基く事もその原因の一つをなすけれども、澤柳君が事を余りにも急ぎ過ぎた事にも起因する」

(海外視察)スタンフォード大学
話は変わるが、八月七日から一週間の日程で、株式会社アイエスエイの主催する「米国ワールドランキングトップ大学視察旅行」に本学園から参加し有意義な視察を行うことができた。
米国のハーバード大、MIT、スタンフォード大、カリフォルニア大バークレー校等の著名な大学に加え、カレッジや高校を含む教育機関を訪問するという、非常に中身の濃い充実した内容の視察旅行であった。今後のグローバル教育の構想、展開はもとより、今後の教育そのものをどのように構想、展開するかという点についての知見を得、大いに啓発された。世界を視野に、世界に学ぶことの重要性を深く認識した視察旅行で得た収穫を今後の湘南学園の教育にぜひ生かしていきたいと考えている。
世界を視野に、世界に学ぶということは、澤柳の重視した点でもあった。
当時、画一的な、あるいはいわゆる注入主義的な教授法が支配的であった中、生徒が自ら学ぶことの重要性を主張する考え方が生じつつあった。そうした中で、澤柳が着目した教育のあり方にダルトン・プランがある。

ヘレン・パーカースト
ダルトン・プランとは、米国の女性ヘレン・パーカーストが創始した教育計画である。ニューヨークに生まれたパーカーストは、師範学校卒業後、小、中、師範学校等で教鞭をとり、またイタリアの女性教育家モンテッソーリの教育にちなむモンテッソーリ法を学ぶためにイタリアに留学している。パーカーストは、マサチューセッツ州ダルトン町において、独自に開発した教育計画に基づく教育施設を開いた。この計画、より具体的には、「児童一人一人が自らの問題を発見しそれに自発的に取り組む」という教育案は、ダルトン町に因み「ダルトン・プラン」と呼ばれるようになった。
パーカーストは、ダルトン・プランによる教育を実践するため、ニューヨークに移り、「Children’s University School」(日本語では「児童大学」)と呼ばれる私立小学校を設立した。
澤柳は成城小学校において、ダルトン・プランを採用し、子どもの主体性、自発性を重視する教育の展開を図ることになる。導入に当たっては、彼の下で教師として活躍した赤井米吉の助力も得ながら、ダルトン・プランを十分に研究している。
やがて、ダルトン・プランは、赤井米吉による翻訳あるいは成城小学校での優れた実践を踏まえた『教育問題研究』における論考等による発信もあり、全国に広まっていった。
私がここで感じるのは、ダルトン・プランの導入にも見られる澤柳の先見性である。
同時に注目したいのは、澤柳がダルトン・プランに興味を抱いたきっかけとその後の行動である。彼は、大正十年八月から翌十一年六月にかけて行ったヨーロッパ、アメリカの視察旅行の途中、ロンドンで読んだ記事でダルトン・プランに強い興味を抱いた。そして、ニューヨークを訪れた際、「児童大学」を訪れ、直接パーカーストに会い、その実践を自分の目で確かめ、関係の文献資料も入手している。「児童大学」訪問により、強い興味は強い確信に変わり、導入に向けての帰国後の研究に至っている。

澤柳政太郎
ダルトン・プランに関し、もうひとつ着目したいのは、導入に当たり拙速を戒める澤柳の進め方である。澤柳は、自分の目で確かめ、研究を積み、十分に咀嚼し、準備を重ねた上で新たな方法を取り入れている。ともすれば、必ずしも準備が十分とはいえないままに矢継ぎ早の改革が導入されがちな昨今の教育改革の動きに鑑み、澤柳の進め方は、今日のさらには今後の教育を考える上で大いに参考にすべき点であるように感じている。
従来の画一的、あるいは注入主義的な教育から脱し、自主性、自発性を重視した教育への転換、まさに澤柳の先見性であり、わが国の教育への貢献と言うべきであろう。のみならず、昨今の教育を巡る論議との関わりにおいても参考にすべき内容を含んでいる感がある。
グローバル教育とも関連し、英語教育と澤柳について若干ふれておきたい。
澤柳は、日本や中国の古典に詳しく、西洋文学にも通じており、英語とドイツ語の読書力は抜群であったと言われている。既述のように、国際会議における英語演説等が高く評価されていた彼は、英語に堪能であったばかりでなく、英語教育にも強い関心をもち、わが国の英語教育発展に寄与している。
上述の大正十年からのヨーロッパ、アメリカの旅行において、彼はロンドンに立ち寄った折、当時ロンドン大学講師であったハロルド・パーマーを日本に招聘することに成功している。澤柳自身、当時のわが国の中学校英語教育を根本的に改善したいと思っており、パーマーに対する周囲からの強い推薦と相俟って、パーマー招聘に本腰を入れることになった。それまで改革にふさわしい人物を招くことができなかったのは、政府が予算を支出しなかったためであったことを踏まえ、澤柳は、松方コレクションで知られる松方幸次郎に財政的な支援を依頼し了解を得た上で、交渉を成立させている。
音声学と文法学が専門のパーマーは、大正十一年文部省英語教授顧問に就き、翌十二年には彼を所長とする英語教授研究所が設立された。パーマーが教育の中心に据えた「オーラル・メソッド」は、戦前の英語教育に影響を与えたのみならず、戦後の「オーラル・アプローチ」法導入の基礎となっている。なお、英語教授研究所は現在の一般財団法人語学教育研究所に引き継がれ、同研究所による「パーマー賞」は、英語教育における権威ある賞として今日に及んでいる。
こうして見てくると、澤柳によるパーマー招聘の意義が如何に大きかったかが窺えよう。そして、ここにおいても澤柳の先見性やわが国の教育への貢献を感じるのである。

小針誠『<お受験>の歴史学』
英語教育に関して言えば、澤柳は、成城小学校に英語の授業を取り入れている。
ここで、『<お受験>の歴史学』という興味深い本にふれておきたい。この本は、私立小学校を中心に据えながら、明治期における私立小学校の誕生と歴史的変遷、社会との関わりや公立小学校との対比、私立小学校の現状と今後の展望をも記した労作である。
この本の中に、大正期の公立小学校(1919年)と成城小学校(1922年)における教科目別の週間授業時間数の比較の表がある。それを見ると公立小学校ではもちろん「英語」の授業はないのに対し、成城小学校では一年生から六年生まで、週2時間「英語」の授業が行われている。著者の小針誠は、成城小学校に関し、時代に先駆けた創立時の4つの方針やダルトン・プランによる自学自習等特色ある教育活動を評価しつつ、併せて各学年に「英語」の授業が設けられていることに注目している。
いずれにしても、大正期において、澤柳が英語教育の重要性を感じ、成城小学校に取り入れていることは指摘しておきたい点である。
なお、本学園の英語教育に関しては、創立当初に英国人の先生が教えられていたとも伺っており、早くから小学校において英語の授業があったことが想像される。本学園の歩みに最も造詣の深い内藤喜嗣氏によれば、ご自身の体験から、戦時中こそ英語の授業は行われなかったものの、昭和20年10月からは、本学園小学校で英語の授業が行われているということである。本学園小学校も英語教育については長い歴史を有している。
ところで、湘南学園小学校の英語教育に関し、ユニークな実践が行われていたことを示す資料がある。
『湘南学園五十年史』(昭和58年発行)を繙くと、「小学校の教育」と題する頁の「学習指導」という項目に「英語教育」についての記述がある。やや長くなるがそのまま引用したい。
フォニックス法、語・句・文型へのプログラム、文法的なきまりの擬人化、いずれも興味をそそる英語教育が展開されていることが窺える文章である。また、この文章からは、小学校における英語教育に相当力を入れていることに加え、中学高校における英語教育を意識しながら小学校の英語教育が展開されていることが感じとれるのである。
本学園の英語教育に関しては、『湘南学園三十年史』(昭和38年発行)から、もうひとつの証言を紹介したい。
『湘南学園三十年史』に見られるこの主張は、子どもの発達段階をふまえた望ましい英語教育のあり方に関する傾聴すべき内容である。そして、今後の小学校における英語教育のあり方を考える上でも参考になる考え方であろう。
小学校における英語の教科化が目前に迫る中、本学園における先人の取組、また英語教育についての主張等は、今こそ大いに学ぶべき姿勢であろう。同時に、「澤柳政太郎のこと(その2)」で述べた、「外国語学習の前提として、しっかりとした日本語の土台が重要である」という私自身の考えをここで改めて提起しておきたい。国語力の育成・強化を重視しながら、総合学園としての本学園ならではの小中高をつなぐ英語教育をぜひ追求したいと考えている。
なお、現在の本学園小学校における英語授業に関しては、ネイティブの先生と担任によるTT(チームティーチング)の授業が各学年週一時間行われ、成果を得ていることを申し添えておきたい。
最後に、亡くなる四か月前の昭和二年八月、トロントで行われた第二回世界教育会議における澤柳の演説にふれたい。なお、会議では英語で演説を行っている。
彼は、この演説の中で、「世界平和」に言及し、さらに「世界人」という言葉をしばしば用いながら、「人種、国境を越えた相互信頼」の重要性を力説している。演説の中から以下の一節を引いておきたい。
「子供達に他国に関する公平なる智識を与へ、彼等が自国の特質を認め尊敬するやうに、他国の其をも認め尊敬するように教え込むのが必要である」

澤柳政太郎
こうした考え方は、「世界平和」、「世界人」、「人種、国境を越えた相互信頼」という上述の彼が重視した言葉と併せ、グローバル社会と呼ばれる今日において、そして21世紀において最も本質的で重要なものと言えよう。まさに、そのような考え方に立っていたのが澤柳政太郎であった。
もうひとつだけ紹介したい澤柳の言葉がある。
大正自由教育研究の泰斗で本学園70周年記念誌の座談会にも参加している中野光が、『大正自由教育研究の軌跡』において、澤柳が述べた興味深い言葉を紹介している。それは、「学校は大きくなってはいけない。小さすぎてもいけないが適正規模の学校が教育の場として望ましい」という言葉である。
本学園は、手前味噌になるかとも思われるが、「教育の場として望ましい適正規模の学校」であると思っている。澤柳が述べた学校規模についての考え方も、今後の学園を考える上での励みにしたい。
本号冒頭にも述べたように、「湘南学園の明日を考える」ための論考の最初に澤柳政太郎を取り上げたが、その理由を四月に書いた文章の冒頭で以下のように記した。
「私は、今後の湘南学園を考える上で、特に澤柳政太郎の生き方、その教育理念、教育実践、わが国の近代教育確立において果たした業績等は、大いに参考になると考えています。澤柳政太郎から何を学ぶか、それは、湘南学園が新たな高みを目指すために不可欠であると考え、最初のテーマとしました」
シリーズⅠ「澤柳政太郎のこと」の最後にあたり、「澤柳政太郎から何を学ぶか、それは、湘南学園が新たな高みを目指すために不可欠である」ということを改めて強く確信していることを申し述べ、シリーズⅠの稿を閉じたい。