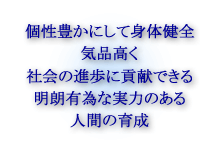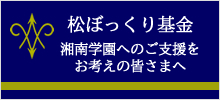シリーズⅡ 「国語力を考える(その12)」
「国語力を磨く-教師への問いかけ-」
「国語力を考える」も本号で12回目を迎えることになる。前号までの連載を振り返りながら、冒頭引用の言葉は誠に重いものがあると受け止めている。例えば、フランスにおける徹底した仏語(国語)教育、あるいはイギリスにおける英語(国語)に高い比重を置いた教育を見る中で、国語力を高める、国語力を鍛えることの重要性を感じないわけにはいかない。出口氏の言葉にもあるように、日本語を自明ととらえず、「磨く」ことにもう少し関心を向けるべきではないだろうかとの感をもっている。
シリーズⅡにおいて、「国語力を考える」というテーマを設定したのは、教育活動の全ての土台に国語力があるという私自身の関心事からであった。連載をとおし、教育活動の全ての土台に国語力があるということ、同時に国語の重要性は、強調しても強調しすぎることはないということを改めて確信するにいたっている。
本号では、出口汪氏の『やりなおし高校国語』を手がかりに『国語力』について入っていきたい。著者出口氏は、同書によれば、大学で教鞭をとり、また予備校講師等を勤めている方である。同書には、「現代文講師として、予備校の大教室が満員となり、受験参考書がベストセラーになるほど圧倒的な支持を得ている」とある。
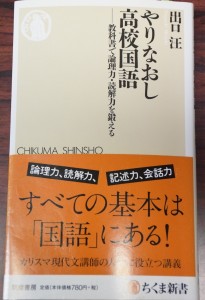 「国語力」の重要性を強調する出口氏が、高校の国語教科書の意義に着目し、著した本が『やりなおし高校国語』である。この本は、高校の国語教科書には汲めども尽きぬ泉があるという出口氏の考え方を前提に、高校生はもとより、社会人の方々にも高校の国語教科書を手にとってほしいという願いで書かれたものである。
「国語力」の重要性を強調する出口氏が、高校の国語教科書の意義に着目し、著した本が『やりなおし高校国語』である。この本は、高校の国語教科書には汲めども尽きぬ泉があるという出口氏の考え方を前提に、高校生はもとより、社会人の方々にも高校の国語教科書を手にとってほしいという願いで書かれたものである。
本の帯に記された「すべての基本は「国語」にある」という言葉は、出口氏の立場を端的に表現したものと言えよう。氏によれば、読解力や記述力、思考力や感性を磨き高める「国語力」は、人生において極めて重要な「力」であり、それがゆえに大いに「役立つ」ものでもあるとしている。氏は、「国語力」を高めるための最適の教材で、かつ名文の宝庫が高校の国語教科書であるとし、そこに高い意義を見出している。
このような前提で、氏は、同書を高校の授業風に一年を三学期に分けた構成にしている。一学期のテーマは、「「論理」の基本を身につける」である。そのテーマに沿って、山崎正和『水の東西』、清岡卓行『失われた両腕』、森鷗外『舞姫』が取り上げられている。さらに、二学期は、「自分勝手な「読解」からの解放」とし、丸山眞男『「である」ことと「すること」』、夏目漱石『こころ』を、三学期は、「「時代背景」を理解して、読む」とし、小林秀雄『「無常」ということ』、中原中也『サーカス』、葉山嘉樹『セメント樽の中の手紙』をそれぞれ取り上げながら、作品を解説している。なお、この出口氏が本の中で取り上げた作品の引用文は、漱石全集からのものが一部入っているものの、それ以外は、いずれも『国語総合』『精選 現代文B』等、筑摩書房の教科書からの引用となっている。あくまで、教科書を基に著された本ということになる。
出口氏は、まず、国語教科書には二種類の教材が含まれるとする。ひとつは、論理的な読解により考える力を養う教材であり、もうひとつは、人生や世の中の深淵と直に向き合わせる教材である。その上で、前者の評論は、「筆者の主張を論理的に読み取るもの」、後者の文学や哲学は、「答えのない深い問題を凝視し続けるもの言い換えれば教養につながるもの」であり、その二つは相反する方向性をもつものと考えるべきであるとする。
氏は、もし教科としての国語が役に立たないと認識されているとすれば、それは、相反する方向性をもつ二つの教材を教える側も教えられる側も無自覚に同じ国語の教材として扱っているからであると断じている。
さらに、「近代」という言葉をどのように読み解くかが国語に関する鍵であるとする氏の指摘も興味深い。
ここで思い出したいのは、本シリーズ「その9」で取り上げた福井県立藤島高校の国語科の先生方が生徒向けに編まれた労作『近代とは何か』というテキストである。詳細は繰り返さないものの、「教養」と「深く考える力」を養うために編まれたこの本においては、「科学」とともに「近代」が重要なキーワードとして挙げられている。何より、『近代とは何か』というテキストのタイトルが、「近代」という言葉のもつ意味の重要性を示しており、「国語」(「国語力」)と「近代」の相関性をも見え隠れさせる内容ともなっている。

森鴎外
出口氏も、「近代」をどう読み解くかに繰り返し言及しており、併せて、国語の学習において、近代が現代にどのようにつながるかという視点が必要ということも重視している。確かに、取り上げられた作品の中の『舞姫』や「こころ」、あるいは『「である」ことと「すること」』においては、「近代」についての理解なしにこれらの作品を読み解くことは不可能であろうと思わざるを得ない。
氏が取り上げた作品に関する解説の具体的内容についても一部紹介しておきたい。
例えば、『水の東西』では、本文中の「鹿おどし」と「噴水」をキーワードに日本文化と西洋文化を対比し、一方で、「「イコールの関係」と「対立の関係」、あるいは抽象と具体に着目する中で、論理的に読み取る手法を丁寧に解説している。
また、「鹿おどし」と「噴水」について、「時間」と「空間」との対比で、あるいは、「見えない水」と「見える水」との対比でとらえながら、グローバル社会の中で、日本文化の性格を外国人に分かりやすく伝える具体例として、それらの対比を例示している。氏の指摘するグローバル社会における「教養」の重要性との関連においても、上記の例示は高校生にとって大いに参考にすべき内容と感じている。
また、教科書における古典的作品とも呼べる『舞姫』、『こころ』については、圧倒的な量の紙幅が割かれ、丁寧な解説が加えられている。それぞれの作品に即しながら、さらには、「近代」とは何かにも目配りをしながら、氏が重視する「作品を正確に、客観的に、深く読解する」ための手立て、根拠が明解に示された解説との感をもった。

夏目漱石
国語の教科書は名作の宝庫であるとする氏の名作についての見解も誠に興味深いものがあった。
名作は、時代を超えた普遍的な価値を持つ作品であり、誰が読んでも面白いものであり、人に深い感銘を与えるものであり、それが面白くないのは、単に作品を読めていないからと言うのである。
氏によれば、「名作が面白くないとすれば、それは読解力の不足であり、作品を正確に、客観的に、深く読解することなく、自分の狭い価値観から作品を歪めて解釈し、断罪しているから」であり、「このような国語教科書の読み方をしている限り、真の学力が身につくはずはないのである」と結論づける。併せて、氏は、生徒の読解力不足に関しては、「教師はそのことにおいて責任がある」としている。
氏のこの本を読みながら、高校の国語教科書には豊かな鉱脈が眠っていると言う感を深くしている。同時に鉱脈を鉱脈たらしめるためにも、教師の役割は大きなものがあり、十分な教材研究、自己研鑽に加え、教師間の研修もまた重要であるとの思いも併せもった。
確かに、教師の役割は誠に重要であり、力量の向上に大いに期待しつつ、出口氏に触発されて私自身が思うところを若干述べてみたい。それは、現行のわが国の国語教育についての感想である。
本シリーズの考察をとおし、わが国の教育、ここでは「国語力」に限定して述べるものの、「鍛える」面がもう少し必要なのではないだろうかという感を抱いている。それは、出口氏も主張するように、私自身、教育活動の全ての土台に国語力があると考えているからであり、今後の教育において、国語力(「話す、聞く、読む、書く」)を高めることが必要であるとの考え方からである。
前号までに既述したフランスやイギリスを見ても、「国語力」を高めることを国として意図的に取り組み、いわば「鍛え」ながら国語力を育成しているように感じている。フランスのバカロレアの「哲学」の問題に向き合わせるに至る幼児期からの徹底した仏語(国語)教育、あるいはイギリスのナショナルカリキュラムに基づく幼児期からの英語(国語)教育の中身の濃さ等に比して、まだまだわが国において「鍛える」点が不足している感は否めないものがある。
実は、そのことは、高等教育をどのように捉えるか。言葉を換えれば大学教育をどのように位置づけるかということに関係してくる。
フランスやイギリスから感じることは、高等教育の前段に中等教育があり、とりわけ中等教育段階においては、高等教育を強く意識した教育が行われているということである。関連して、フランスにおける仏語(国語)教育、イギリスにおける英語(国語)教育においては、「話す、聞く、読む、書く」)を総合的に高めるという意味での「国語力」の育成が図られていることも留意したい点である。
 前号でも紹介した『オックスフォードからの警鐘 グローバル化時代の大学論』において、著者の苅谷剛彦氏は、東大で18年、さらに2008年からはオックスフォードで教鞭をとっている経験からいくつかの点を指摘している。
前号でも紹介した『オックスフォードからの警鐘 グローバル化時代の大学論』において、著者の苅谷剛彦氏は、東大で18年、さらに2008年からはオックスフォードで教鞭をとっている経験からいくつかの点を指摘している。
氏は、欧米と比較しながら、本来、大学は「学問をするところ」であり、「高度な、新しい知が生み出され、それを学べるところ」であり、「将来を支える人材を育成する」専門機関であるとする。それに対し、日本では、その点が極めて弱いと言わざるを得ないとしている。さらに、たとえば、「就活」に関し、「海外の大学に通っている学生と比べて、半年から1年分学習の時間が少ないのですから、日本は人材育成の面で、大変な時間とお金の無駄遣いをしているとしかいいようがありません」と指摘している。こうした苅谷氏の指摘は、ひとり氏のみならず、彼我の大学を知る人には共通の危機感であると私自身受け止めている。
今後のわが国を考える上で、高等教育をどのように位置づけるか、高等教育をゴールと見据えながら中等教育と高等教育の接続をどのように図るか、これらは非常に重要な課題と受け止めるべきである。それは、とりもなおさず、わが国が他国に伍していくためには、高等教育を最終目標にした中等教育の充実が何より国語教育に求められるべきという点に通じるようにも考えている。
私自身、繰り返し述べているように、教育活動の土台に国語力があるとする立場であり、「すべての基本は「国語」にある」とする出口氏の主張には共感を覚えている。とりわけ、国語教育の専門家として、高校の国語教科書を切り口に論じる「国語教育」及び「国語力」についての主張は興味深いものがあった。
そして、氏の主張に関連して、冒頭に引用した言葉はとりわけ強く胸に響くものがあった。
「私たちはなまじ日本語が話せるからといって、自分の国語力を磨かないままでいいのだろうか」
この言葉が問いかけるものは、わが国の国語教育にとどまるものではなく、同時に、国語の教師にとどまるものではないと思っている。もちろん、「社会人にも高校国語教科書を」と出口氏が述べているように、冒頭引用の言葉は、教える立場の者以外に当てはまることは言うまでもないと思っている。
ただし、ここでは敢えて教える側に限定して考えてみたい。教科を超えて、そしてまた幼児教育から高等教育まで教育階梯を超えて教師に求められるものが、この引用の言葉にはあると私は思っている。
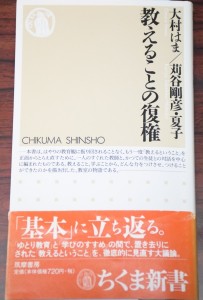 わが国の国語教育を代表する大村はまが、「教師と国語力」について述べた一文がある。大村はま、苅谷剛彦、苅谷夏子の共著『教えることの復権』にある一節である。大村自身が、「珍しい組み合わせの三人を著者にした本」と呼ぶ同書は、2003年に出版されている。いわゆる「ゆとり論議」の中で、「教えること」を正面から真摯に見つめ直したいという立場で編まれた一冊である。苅谷剛彦氏は本号でも引用した教育社会学者であり、苅谷夏子氏は大著『評伝 大村はま』の著者でもある。そして、苅谷夏子氏は大田区立石川台中学校時代の大村の教え子であり、苅谷剛彦氏、苅谷夏子氏はご夫妻である。
わが国の国語教育を代表する大村はまが、「教師と国語力」について述べた一文がある。大村はま、苅谷剛彦、苅谷夏子の共著『教えることの復権』にある一節である。大村自身が、「珍しい組み合わせの三人を著者にした本」と呼ぶ同書は、2003年に出版されている。いわゆる「ゆとり論議」の中で、「教えること」を正面から真摯に見つめ直したいという立場で編まれた一冊である。苅谷剛彦氏は本号でも引用した教育社会学者であり、苅谷夏子氏は大著『評伝 大村はま』の著者でもある。そして、苅谷夏子氏は大田区立石川台中学校時代の大村の教え子であり、苅谷剛彦氏、苅谷夏子氏はご夫妻である。
ここでは本の内容にはふれることはしないものの、第三章における大村と苅谷夏子の対談から「国語力と教師」についての大村の発言を拾ってみたい。
大村の話を受けて、「最後までって退職するような時期までですか」と尋ねる苅谷氏に答えている。「そう。七十三歳まで練習していたの、こっそりと。先生方はそんな時間はかけられない、忙しくてとおっしゃるけれど、忙しくてもそれが本職ならしかたないでしょう」
単元学習でも著名な大村はまが、そのための資料収集や授業準備にどれだけの時間と労力を割いたかは多くの人の知るところである。その大村はまがテープレコーダーを用い、
「私は最後まで子どもへの話は練習していた」と言うのである。私は探すべき言葉がないようにさえ思われた。
その大村の「いわゆる国語の力が、どの教科の教師にも必要ですね」という言葉は、ずっしりとした重みで伝わってくるように思っている。
大切にしたい言葉であり、とりわけ教師が自らに問いかけるべき言葉ではないだろうか。