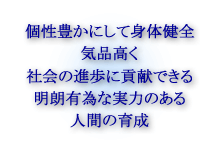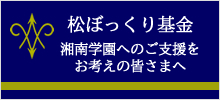シリーズⅡ 「国語力を考える(その1)」
大村はまと水村美苗 - 「言葉の力」と「国語力低下への懸念」と-
 前号でもふれたように、八月に米国トップランキング大学視察旅行に参加し、西海岸ではUCバークレー、スタンフォード、東海岸ではハーバード、MITを始めとする大学、さらにはリベラルアーツカレッジや高校等を訪問した。多くの学びを得るとともに、今後の教育を展望する上で大きな刺激を受けた。
前号でもふれたように、八月に米国トップランキング大学視察旅行に参加し、西海岸ではUCバークレー、スタンフォード、東海岸ではハーバード、MITを始めとする大学、さらにはリベラルアーツカレッジや高校等を訪問した。多くの学びを得るとともに、今後の教育を展望する上で大きな刺激を受けた。
今回の視察旅行を通じ、自身について言えば、会話力を含む英語力不足を自覚し、英語力向上の必要性を感じてきた。会話を含む英語力向上の必要性、英語教育の更なる充実は、本学園に求められていることでもあると思っている。一方、今後の教育を考える上で、国語力が重要であることを改めて確認する旅行でもあった。米国の大学入試(AO入試)では、エッセイ(志望動機書)の重要性が極めて高いことを今回の視察で強く認識した。様々なことへの挑戦と実践の実績、深い思索、冷静な自己分析、自らの将来への展望等が集約されたものが、米国の大学入試(AO入試)におけるエッセイ(志望動機書)である。生き方そのものが凝縮されたものがエッセイであり、生半可な内容では勝負にならないということも十分に理解できた。入試におけるエッセイの作成はもとより、大学入学後は、大量の文献を読み、レポートを作成し、プレゼンを行う日々になる。深く思索し、自分の考えをまとめ、相手に伝え、対話する、その過程で、重要なのは、思考の基盤となる国語力であろう。欧米に留学するにしても、国内の大学で学ぶにしても、さらにその前段としての小中高における学びにおいても、国語力の重視、国語力の強化は、わが国においてもっと注目されるべきと考えている。
グローバル教育という言葉がそこかしこから聞こえてくる昨今である。内容の吟味よりも、如何に早く、如何に多く英語を導入するかに関心が集中している感もある。グローバル教育を考える上で、英語が重要であることは論を俟たないところである。一方で、昨今、英語重視を叫ぶあまり、国語に注目すること、国語力の向上の重要性については、あまり顧みられていない感が否めないでいる。国語力(日本語力)(読むこと、書くこと、話すこと)の育成・強化はもっと議論されるべきであり、そのための対応も図られるべきであると思っている。
 私自身、「グローバル教育」と「国語力の強化」は相対立するものではなく、グローバル教育を支えるものとして国語力があると考えている。本学園においても、小中高を見通した英語教育の充実は重要であると考えており、その点にはしっかりと取り組んでいきたい。併せて、本学園においては、今後、グローバル教育の吟味及びその内容の改善・充実と関連させながら国語力強化に力を注いでいきたいと考えている。
私自身、「グローバル教育」と「国語力の強化」は相対立するものではなく、グローバル教育を支えるものとして国語力があると考えている。本学園においても、小中高を見通した英語教育の充実は重要であると考えており、その点にはしっかりと取り組んでいきたい。併せて、本学園においては、今後、グローバル教育の吟味及びその内容の改善・充実と関連させながら国語力強化に力を注いでいきたいと考えている。
ここで、少し自身のことにふれておきたい。私の大学及び大学院における研究テーマは、「ヒューマニズム」、「ヒューマニズム教育」であった。ヒューマニズムは、一般には、「人道主義」と訳されることが多いと思われる。しかしながら、歴史的に考察すると、最もふさわしい訳語は「古典研究」ということになる。非常に簡潔に申し上げれば、「ヒューマニズムとは、ギリシア・ローマの古典研究である」と表現しても誤りではないと考えている。
一言申し添えれば、ヒューマニズムには、「言葉(言語)を磨くことで人間性を磨く(人間性を高める)」という要素があり、言葉(言語)というものに高い価値を置いているという側面をもっている。
私自身の研究テーマとも関連し、「言葉」の重要性、「教育における言葉の意義」については、個人的に多少なりとも関心をもってきた。
なお、ヒューマニズム(humanism)を「人道主義」と訳すことに関し、フランス文学者でヒューマニズムに造詣の深い渡辺一夫は、ヒューマニズム(humanism)がヒューマニタリアニズム(humanitarianism)と混同されているからであろうと述べている。やや専門的になるので、ここではその指摘のみに止めたい。
 今回、「国語力を考える」というテーマを扱うのには、大きく三つの理由がある。ひとつ目は上記の個人的な関心事とも関連して、言葉というものの重要性について自分としての考え方を述べてみたいということがある。ふたつ目として、英語を重視するあまり国語力が軽視され、その結果として国語力が低下することへの懸念がある。
今回、「国語力を考える」というテーマを扱うのには、大きく三つの理由がある。ひとつ目は上記の個人的な関心事とも関連して、言葉というものの重要性について自分としての考え方を述べてみたいということがある。ふたつ目として、英語を重視するあまり国語力が軽視され、その結果として国語力が低下することへの懸念がある。
本号では、ひとつ目の言葉の重要性については、わが国における国語教育において多くの優れた業績を収めた大村はまを、ふたつ目の国語力低下への懸念については、『日本語が亡びるとき』の著者としても知られる水村美苗を取り上げながら、概括的な話をしてみたい。
理由の三つ目は、この八月に本学園で行った「全学教研」に関わる問題意識である。本学園の全教員が一堂に会して研修・研鑽を深める「全学教研」の今年のテーマは、「“つたえる力”を高める。~自分から他者、そして世界へ~」であった。つたえる力のもとになるのは言葉であろう。そのこととも関連し、本学園が今取り組んでいるグローバル教育の柱のひとつに「国語力」を高めることを据えたいということもテーマと関係している。
そのような前置きで、本題に入っていきたい。
大村はまは、わが国の国語教育に大きな足跡を記した人物として知られている。生涯一教師として国語教育と向き合い、工夫を凝らした授業で子どもたちの国語力をつけることに一生を捧げた大村は、言葉の力を信じ、言葉の力をつけることを追求し続けた人でもあった。
その大村が、言葉のもつ意義について述べた以下の一節がある。
 食べ物との対比というわかりやすい喩えの中で、言葉の重要性が浮かび上がってくる文章である。「ことばの力は、人間の、人間としてのもとの力」という表現に、言葉のもつ意義、言葉を豊かにすることの意義を感じないわけにはいかない。
食べ物との対比というわかりやすい喩えの中で、言葉の重要性が浮かび上がってくる文章である。「ことばの力は、人間の、人間としてのもとの力」という表現に、言葉のもつ意義、言葉を豊かにすることの意義を感じないわけにはいかない。
何より、大村はま自身が人間としてのもとの力である「ことばの力」を信じ、「ことばの力」を伝えることに生きがいを感じ、「ことばの力」を教え子に伝えていったと思っている。
「国語力を考える」というテーマに関し、大村はまについては次号以降でまたふれていくが、ここでは、大村が最初に教鞭をとった諏訪高等女学校時代のエピソードをあげておきたい。
初任の同校で、大村は、日々の授業への真摯な取組に加え、一人ひとりへのきめ細かな添削指導、さらに生徒全員のノート点検と感想記入等、国語教育に全精力を傾けていた。もとより、大村にあっては、国語教育に全精力を傾ける姿勢が生涯変わらなかったことは改めて述べるまでもないことと思われる。その諏訪高女の教え子に作家の藤原ていがいる。藤原ていは、作家新田次郎の妻であり、『国家の品格』を始めとする作品で知られる数学者藤原正彦の母である。藤原ていは、第二次世界大戦の敗戦直後、現地に止まった夫と離れ、新京(長春)から朝鮮半島を経て幼い子どもの手を引き帰還する旅を描いた『流れる星は生きている』の著者としても知られている。
生死の境をさまよいながら、生まれたばかりの女の子を背負い、二人の幼い男の子を連れて日本までたどりつくという作品を読み、極限の状態を何度も乗り越えるその精神力に感嘆の念を覚えずにいられなかった記憶がある。
藤原ていに関し、大村はまが深く信頼を寄せた教え子苅谷夏子による『評伝 大村はま』から一節を引きたい。

藤原てい
*出典:ウィキメディア・コモンズ
同書には、藤原ていが、大陸からの逃避行におけるいわゆる極限状態に置かれた時に、「諏訪湖のほとりで静かな、厳しい顔をして国語を教えた大村はまのことを思った」ということが、藤原自身の言葉とともに紹介されている。
国語教育を通しての大村との関わりは、藤原にとって生きる支えにもつながる根本的な力となっていたことが窺えるエピソードではないだろうか。『評伝 大村はま』の副題には、「ことばを育て 人を育て」とある。やがて、藤原は、「ことばを「なりわい」」とする作家になっていく。
もう一人、「国語力を考える」というテーマで注目したい人物に水村美苗がいる。
私が水村美苗に出会ったのは、今から八年前のことになる。たまたま自宅近くの市立図書館で手にした雑誌が発端であった。雑誌は『新潮』(2008年 9月号)である。偶然手にとったその本に『日本語が亡びるとき 英語の世紀の中で』という作品があった。衝撃を受けながら一気に読み終えた。やがて同名のタイトルで、単行本が筑摩書房から出版された。因みに、『新潮』(2008年 9月号)には、単行本の冒頭の3章が予め掲載されている。
『新潮』をそして単行本を読み、言葉について、書くという行為のもつ意味について、その国の言葉(国語)で文学や高度な学問が書かれることがいかに貴重かということについて、さらには、日本語の成り立ちについて、翻訳のもつ意義について等に関し、瞠目し、深く考えさせられた。
水村の主張に関連し、その後読んだ『漢文の素養』(加藤徹)においては、特に国力と国語力の関係についての項が強く印象に残っている。
水村の主張に関連し、もう一冊挙げておきたい本がある。『日本語を作った男 上田万年とその時代』(山口謡司)である。最近読んだこの大著を通し、明治期における日本語(国語)の成り立ちについての多くの知見を得た。同時にそこに注がれた莫大なエネルギーを考えつつ、先人の偉大な業績に感嘆せずにはいられなかった。
水村美苗そして『日本語が亡びるとき』については、次号で詳しくふれるとして、本号では、水村の以下の主張のみをあげておきたい。
漱石を高く評価し傾倒する水村は、「日本語が真の「国語」として存在し続けるためには、日本人は、まず近代文学の古典ぐらいは読めるように育つべきだと思うんです」と述べ、さらに続けている。
私は、水村の「良質な本が読み継がれないということは、文化自体が存在しないに等しいこと」という言葉を重く受け止めている。
「良質な本が読み継がれなくなる」という懸念が杞憂に終わってほしいと願いながらも一抹の不安を禁じ得ないでいる。そして何よりも、懸念を杞憂に終わらせるためにも「国語力」への関心が必要と思っている。
今後の教育を考える上で、また個人の成長や人間性の完成に関連して、さらに文化の継承を考える上でも、「国語力」を問うことは現下の重要なテーマととらえ、シリーズⅡとして「国語力を考える」を設定した。その考察は、以下次号に譲りたい。