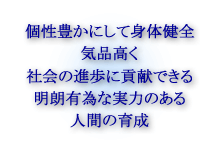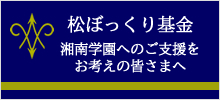シリーズⅡ 「国語力を考える(その2)」
「国語とは」、「国語成立前夜」
 今月12日、藤沢ロータリークラブにお招きを受け、卓話をする機会を得た。卓話とは30分程度の短めの講演である。この日は、昨年度ロータリークラブの交換留学生としてスウェーデンで一年間学んだ本学園卒業生渡部ゆうさんの帰国報告もあり、私は15分程度話をさせていただいた。
今月12日、藤沢ロータリークラブにお招きを受け、卓話をする機会を得た。卓話とは30分程度の短めの講演である。この日は、昨年度ロータリークラブの交換留学生としてスウェーデンで一年間学んだ本学園卒業生渡部ゆうさんの帰国報告もあり、私は15分程度話をさせていただいた。
私の卓話のタイトルは「心に残る言葉」。その中で、尊敬する今道友信先生の言葉も紹介した。東大名誉教授で美学、倫理学がご専門の今道友信先生は残念ながら四年前にお亡くなりになった。今道先生とは幸運にも学生時代に学外のドイツ語教室で最初の出会いを得た。紅露文平氏が主宰する紅露ドイツ語教室での出会いである。紅露氏自身は必ずしも有名な方ではないと思われるが、その教室の講師陣はまさに「綺羅星のごとく並ぶ」という表現がふさわしい顔ぶれであった。知人の紹介で知ったその教室で、たまたま、今道先生の指導を受けることになったのは、先生の本を多少読んでいた私にとって望外の幸せであった。夢を見るような気持ちで授業をお聞きしたことを覚えている。今道先生については書きたいことがたくさんあるものの、本号でふれたいのは、紅露文平氏のことである。
紅露文平氏の思い出は枚挙にいとまがない。まず、服装がいつも同じ。大学の卒業式で教授が着るガウン風の上着。加えて、氏によれば、食事も毎日同じものを食べるということであった。「私くらい偉くなると」という言葉が枕詞のように登場し、「私くらい偉くなると」、服装や食事は同じになるというのである。「偉いこと」と「同じ」ということに論理的整合性はないとも思えるのだが、何となくそのように思わせる不思議な迫力の持ち主であった。氏は言うまでもなくドイツ語の専門家であり、ドイツ語には強烈な自負が感じられた。
ドイツ人から、「あなたのドイツ語は見事だがドイツにどれだけ居たのですか」とよく聞かれる。その度に、「ゲーテは日本に来たか。それなのに紅露文平が何故ドイツに行かなければならないのか」と答えていると言われたことなどはその一例である。
紅露氏の授業もあった。教わったとおりに答えなければならず、文字一語もゆるがせにできない厳格な授業であった。
一方で、氏が日本語をとても大切にされていたことも印象深い。たとえば、旧漢字について話をされたことがあった。「體」は「骨」篇に「豊」と書くから初めて意味をなす。それが何ですか、「体」とは。「イ」(人偏)に「本」では、「カラダ」という意味を有しない。何故、「体」などという文字にしたのかと嘆かれるのであった。この話のみならず、日本語に寄せる思いは他の場面でもしばしば感じることであった。ドイツ語を学びながら日本語を考える、そんな時間を過ごしたドイツ語教室であった。
 さて、ここで、先月言及した水村美苗に話題を転じたい。『日本語が亡びるとき』を読み、内容のみならずその文章にも興味を覚え、さらに『母の遺産』を読み、水村の人物そのものにも興味が湧いた。しかし、著者略歴等では、12歳でアメリカに渡り長く暮したこと、イェール大学、大学院で仏文学を学んだこと。プリンストン大学で日本文学を講義したこと等、断片的なことしか記されておらず、ネットを含めた情報でも、付け加えることと言えば夫君が有名な経済学者であること程度しかなかった記憶がある。水村美苗について知りたいとは思うものの、情報については隔靴掻痒の感があった。
さて、ここで、先月言及した水村美苗に話題を転じたい。『日本語が亡びるとき』を読み、内容のみならずその文章にも興味を覚え、さらに『母の遺産』を読み、水村の人物そのものにも興味が湧いた。しかし、著者略歴等では、12歳でアメリカに渡り長く暮したこと、イェール大学、大学院で仏文学を学んだこと。プリンストン大学で日本文学を講義したこと等、断片的なことしか記されておらず、ネットを含めた情報でも、付け加えることと言えば夫君が有名な経済学者であること程度しかなかった記憶がある。水村美苗について知りたいとは思うものの、情報については隔靴掻痒の感があった。
そうした中、2014年、朝日新聞夕刊の「人生の贈りもの」というコーナーに5回連続のインタビュー記事が掲載された。その記事で、まず、生年が1951年ということを知った。育った環境等は全く異なるものの、同じ1951年生まれということを知り、同じ時代の空気を吸ったことに親近感を抱いた。記事をとおして、生い立ちから学問形成、作家への歩み、さらには作品へのコメントも含め、様々な角度から水村に理解を深めることができ、隔靴掻痒感はようやく解消されたのであった。
水村の『日本語が亡びるとき』には、「英語の世紀の中で」という副題がついている。水村の日本語が亡びることへの危惧は、英語が水村の言う「普遍語」になりつつあることへの懸念と対をなしていることをまず述べておきたい。
 それでは、「普遍語」という聞きなれない用語の意味から入っていきたい。
それでは、「普遍語」という聞きなれない用語の意味から入っていきたい。
水村は、言葉を「普遍語」「国語」「現地語」の三種類に分けている。「普遍語」とは、「話し言葉」ではなく、「書き言葉」であり、かつてヨーロッパのラテン語が、あるいは東アジアの漢文がそうであったように「学問の言葉」でもあると定義している。水村は、加えて、普遍語で重要なのは、ひとたび普遍語をマスターすれば、国境を越えて、人類の叡智が蓄積された<図書館>への出入りが可能になることであるとしている。ヨーロッパのラテン語が、東アジアにおける漢文が、国境を越えた<図書館>というのは見事な比喩と言うべきであろう。
次に現地語についての水村の定義をみてみたい。「現地語」とは、「普遍語」が存在している社会において、人々が巷で使う言葉であり、多くの場合それらの人々の「母語」であるとしている。
それでは、「国語」はどのように定義できるのだろうか。水村は以下のように定義している。
私たちは、現在、日本語(国語)で書かれた本を読む際、日本語(国語)の存在が自明であるかのように思っている。ところで、上述の水村の定義によれば、国語は「国民国家」の誕生と密接不可分、すなわち、国民国家誕生以前には国語は存在しないことになる。事実、わが国における国語は、国民国家誕生の明治期に確立されている。わが国のみならず、諸外国においても、国語と国民国家とは、水村の述べるように深く「絡み合って」いるのである。
後述するが、わが国の国語確立に多大なる貢献を行った人物に上田万年がいる。ドイツ留学を終えた明治二十七(1894)年、帰国後最初に行った講演のタイトルは「国語と国家と」であった。この講演の内容、上田の問題意識においても国語と国家は不可分の関係にあったのである。
なお、国語の確立に関しては、以下の文章を引いておきたい。
 ここで、『漢文の素養』(加藤徹)にふれておきたい。
ここで、『漢文の素養』(加藤徹)にふれておきたい。
話は逸れるが、友人に優れた読書家がいる。専門の数学はもとより、文学や歴史、哲学等にも造詣が深い。まさにリベラルアーツ、すなわち幅広い教養、文系・理系を越えた学びを体現している感のある人物である。一知半解を嫌い、一知半解とは無縁な彼の出身大学は国際基督教大学。私の知り得る限りという狭い範囲にはなるものの、彼を含むICU出身者を見ると、わが国におけるリベラルアーツ大学の代表はICUであるような気がしている。彼には本について稀に尋ねることがある。七、八年前、最近読んだ本でよかったものとして挙げてくれたのが『漢文の素養』であった。その本を手にし、彼の目の確かさを感じたものである。
話を元に戻したい。この本は、漢字の伝来から始まり、日本語そのものがどのようにつくられていったかといういわば日本語の歴史、さらに、漢文がわが国の歴史や文化のみならずわが国の発展や国力の充実に深く関わったこと、そして、わが国には漢文の素養、すなわち漢文を教養として身につけることを重んじてきた伝統があること等にふれながら、今後に向けての漢文の意義と可能性にもふれた内容となっている。学ぶことの多いその本の中で、加藤は以下のように述べている。
加藤のこの分析は、水村の分析に近いものがある。同時に、高位言語すなわち東アジアでは漢文が、西欧ではラテン語が叡智の宝庫であり国際語としても使われたという件は、水村の国境を越えた<図書館>に通ずるものがある。
さらに、加藤は、「言語文化の三層構造が解消されるのは、近代に入って、「国民国家」が誕生してからである。国民国家とは、国民・国語・国軍の三点セットからなる近代国家を言う」と断じている。国民国家と国語の関係が、ここでも簡潔明瞭に述べられていると言えよう。
水村や加藤が指摘するとおり、現在われわれが使用している日本語(国語)は自明のものではなく、国民国家形成の明治期に確立されている。そして、その日本語(国語)確立に多大なる貢献をしたのが上田万年であった。

上田万年
上田万年(1867~1937)。「かずとし」が正しいようであるが、本人は「まんねん」と表記している。「シリーズⅠ」で取り上げた澤柳政太郎とは東京帝国大学文科大学同期。親しい友人であり、一時は文部省で一緒に仕事をしている。東京帝国大学国語研究室初代主任教授。弟子には『広辞苑』で有名な新村出らがおり、作家円地文子は娘である。
なお、上田と日本語の確立については、『日本語を作った男 上田万年とその時代』(山口謡司)に多くを負いながら、論を進めていきたい。
上田万年は慶応三(1867)年一月七日(新暦では二月十一日)に現在の新宿区に生まれた。その二日前の慶応三年一月五日、同じ新宿区に生まれたのが夏目漱石であった。山口は、上田万年と夏目漱石の関係を以下のように例えている。
二日違いで、しかも同じ現在の新宿区という極めて近い場所に生まれた万年と漱石は、日本語(国語)の誕生にも深く関わっていたのである。「万年なしに「漱石」は生まれてこなかった」をもじれば、「万年と漱石なしに「日本語(国語)」は生まれてこなかった」と言えるかもしれない。
ここで、明治期に日本語(国語)が確立する以前のわが国の実際をみてみたい。国語が確立するには、書き言葉の洗練が必要であり、その前提には言文一致がある。さらに、関連で標準語(共通語)の必要性も生じてくる。実際はどうであったか。
 話し言葉を例にとれば、井上ひさしの『國語元年』がいみじくも示すように、地域により、身分により使用している言葉はばらばらであった。
話し言葉を例にとれば、井上ひさしの『國語元年』がいみじくも示すように、地域により、身分により使用している言葉はばらばらであった。
『國語元年』。明治七年を舞台にした戯曲であり、主人公南郷清之輔は、「全国統一話し言葉」の制定を命じられた文部省の役人である。ところが、南郷の家には義父、妻、使用人、書生等がおり、薩摩弁、長州弁、江戸山の手弁、山形弁、京都弁等々十種類もの言葉が飛び交う有様。お膝元の南郷家で方言が飛び交う様子を巧みに織り込みながら、「全国統一話し言葉」の制定が如何に難しいことであるかがユーモラスに描かれている。
作品中に公家風の怪しげな男が登場し、「古来から言語を改めることは大事業どして、これまで成功したんは二つしかおへん。一つは始皇帝の漢字改革、もう一つが仏蘭西革命による仏蘭西語改革どす」と述べる所がある。井上ひさしが公家風の男を通して、その難しさにふれた場面と言えよう。その後、南郷は上司に叱責され精神に不調を来す。劇の最後、登場人物一人ひとりの最後が示される場面。「南郷清之輔 二十年後の明治二十七年秋、東京本郷の癲狂院で死亡」。面白さと深さ、言葉を自在に操る井上ひさしの真骨頂が窺える戯曲である。
 あるいは、明治時代のある時期まで、学問をすることは原書を読むこととほぼ同義であった。翻訳書は少なく、学問を修めるには原書を読む力が必須、言い換えれば英語ができなければ学問はできなかったのである。そもそも学術書を日本語で書けるのかどうかは非常に疑問視されていたというのが当時であった。
あるいは、明治時代のある時期まで、学問をすることは原書を読むこととほぼ同義であった。翻訳書は少なく、学問を修めるには原書を読む力が必須、言い換えれば英語ができなければ学問はできなかったのである。そもそも学術書を日本語で書けるのかどうかは非常に疑問視されていたというのが当時であった。
また、初代文部大臣としても知られる森有礼が「英語をわが国の公用語とすべし」と主張したことは有名な話である。山口謡司によれば、森は、イェール大学のウィリアム・ホイットニーに「不規則動詞を規則化して、英語を日本の国語にするというのはどうだろうか」という手紙を送って意見を聞いたという。森は、かなり具体的に英語の公用語化を考えていたことになる。
それ以外にも、表記について言えば、漢字を廃止してひらがなだけで日本語を表記すべきという主張、あるいはローマ字で表記すべきとする主張があった。前者は明治十六(1883)年に「かなのくわい」(くわい=会 筆者注)、後者は明治十八(1885)年に「羅馬字会」を設立し、それぞれ運動を進めている。前者には一万人の会員が、後者には八千人の会員がいたとされ、著名な人物を要職に据え会誌を発行するなど活発に活動していた。
このような状況を見ても、日本語(国語)の確立がいかに難事業であったか、現在の私たちの想像を越えるものがある。
日本語(国語)確立に向けて、どのような努力が払われるのか、以下次号に譲りたい。