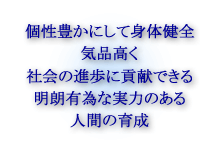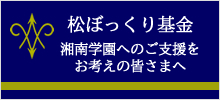シリーズⅡ 「国語力を考える(その4)」
「『国語』の成立と翻訳」 -『日本語が亡びるとき』(水村美苗)を中心に-
 十二月はノーベル賞授賞式の月である。今年もわが国から医学・生理学賞に大隅良典東京工業大学栄誉教授が受賞の栄に浴された。ノーベル賞について言えば、2010年に根岸英一氏がノーベル化学賞を受賞された。当時私は根岸氏の母校湘南高校の校長をしており、生徒にぜひ根岸先生のお話を聞かせたいとの希望をもった。多くの方のお力添えもあり、授賞式直前の2010年十一月にご来校いただき、全校生徒に貴重なご講演を賜わった思い出がある。根岸先生にはその後もご交誼を賜わっており、先月には湘南学園にお立ち寄りいただき、園内をご案内申し上げた。ノーベル賞のご縁と言えば、北里大学在職中の2015年、大村智北里大学特別栄誉教授がノーベル医学・生理学賞を受賞され、学内の一員として喜びの和に加わらせていただいたことも記憶に新しい。
十二月はノーベル賞授賞式の月である。今年もわが国から医学・生理学賞に大隅良典東京工業大学栄誉教授が受賞の栄に浴された。ノーベル賞について言えば、2010年に根岸英一氏がノーベル化学賞を受賞された。当時私は根岸氏の母校湘南高校の校長をしており、生徒にぜひ根岸先生のお話を聞かせたいとの希望をもった。多くの方のお力添えもあり、授賞式直前の2010年十一月にご来校いただき、全校生徒に貴重なご講演を賜わった思い出がある。根岸先生にはその後もご交誼を賜わっており、先月には湘南学園にお立ち寄りいただき、園内をご案内申し上げた。ノーベル賞のご縁と言えば、北里大学在職中の2015年、大村智北里大学特別栄誉教授がノーベル医学・生理学賞を受賞され、学内の一員として喜びの和に加わらせていただいたことも記憶に新しい。
ところで、このシリーズでは国語力をテーマにしている。国語力の前提には当然のことに国語(日本語)の存在がある。われわれが目にする国語(日本語)が自明のものではなく、とりわけ明治以降の先人の多くの苦難の上に成立したことは改めて思い起こしたい点であり、その点について論を進めているところでもある。本号では、国語(日本語)成立に翻訳が果たした役割について論を進めていくが、その前に、最近目にした本にふれておきたい。
一時話題になったドラマに「ドラゴン桜」がある。漫画にもなっており、私も全てではないもののテレビであるいは漫画でこの作品にふれたことがある。この作品に関連し、ドラゴン桜公式副読本というサブタイトルのある『16歳の教科書 なぜ学び、なにを学ぶのか』という本を知った。文庫本の帯には「全国学校図書館協議会選定図書」とある。国語や数学や理科などの教科に関し、「なぜ学び、なにを学ぶのか」について、それぞれの分野を代表する方が高校生向けに講義をするという内容の本で、例えば、国語については金田一秀穂氏が講師をつとめている。
 金田一氏は、国語力を「言語能力」と「コミュニケーション能力」からなるものとした上で、何よりも事実を正確に伝えることが重要であると述べている。その上で、氏は、「ほんとうの国語力を身につける」というテーマに言及し、情緒を切り捨て、事実と論理だけで文章を組み立てていくことが、ほんとうの国語力を高めていくポイントと指摘している。氏は、その上で、「一枚の絵を言葉で書いてみる」という問いを提出する。目に見えるものを自分の意見を一切入れずに言葉に変換するというのである。そのことにより、物事を正確に言語化することの難しさ、あるいは言葉という表現ツールの限界を知ることとなり、それこそが国語力を磨く第一ステップであるとしている。確かに絵を言語化するというのは簡単なことではなく、国語力の第一ステップという指摘には共感を覚えた次第である。
金田一氏は、国語力を「言語能力」と「コミュニケーション能力」からなるものとした上で、何よりも事実を正確に伝えることが重要であると述べている。その上で、氏は、「ほんとうの国語力を身につける」というテーマに言及し、情緒を切り捨て、事実と論理だけで文章を組み立てていくことが、ほんとうの国語力を高めていくポイントと指摘している。氏は、その上で、「一枚の絵を言葉で書いてみる」という問いを提出する。目に見えるものを自分の意見を一切入れずに言葉に変換するというのである。そのことにより、物事を正確に言語化することの難しさ、あるいは言葉という表現ツールの限界を知ることとなり、それこそが国語力を磨く第一ステップであるとしている。確かに絵を言語化するというのは簡単なことではなく、国語力の第一ステップという指摘には共感を覚えた次第である。
最後に氏が、国語辞典の例をあげながら、言葉を定義する、あるいは言葉を使って正確に説明するということは、数学の問題を解くことに似た作業であり、数学と異なり正解はひとつではないものの、方程式が解けたときと同じくらいの興奮や喜びがあるとしている点にも惹かれるものがあった。
同じ本の中に、数学分野を担当している高濱正伸氏が、「数学力は国語力」と述べている一節がある。数学にとって国語力が大切であるという指摘は、金田一秀穂氏の主張とも重なる点であろう。
国語力の重要性は私自身感じているところではあるが、学習の基礎に国語力があるということを改めて考えさせられる本であった。
ここで本号との関連で、ノーベル賞の話にもうひとつふれておきたい。2008年にノーベル物理学賞を受賞された方に益川敏英氏がいる。氏は、新聞紙上で英語教育のあり方についてご自身の考えを述べている記事の中で、「母語で学ぶ強み」について発言している。
「日本語で最先端のところまで勉強できる」、「自国語で深く考えることができる」、「日本語で十分間に合う」、こうしたことも、明治のある時期までは想像もつかないことであった。当時にあっては、学問をするということは原書で学ぶこととほぼ同義であったからである。そうした中で、邦語の学術書が世に出ることになる。冨山房創業者の坂本嘉治馬がその立役者であった。
 1886(明治十九)年、坂本嘉治馬が出版社冨山房を創業する。邦語をもって学術書を書くことは可能かどうかが議論されている当時にあって、坂本は、早大総長を務めた天野為之の『経済原論』を出版して大成功を収めることになる。天野が早稲田において原書を用いず日本語で行った講義が好評を博し、それをまとめたものが『経済原論』であった。同著について、天野自ら、「私は幸運にも私の処女作に成功し、冨山房も処女出版に成功した訳である」(『日本語を作った男 上田万年』山口謡司)と述べている。
1886(明治十九)年、坂本嘉治馬が出版社冨山房を創業する。邦語をもって学術書を書くことは可能かどうかが議論されている当時にあって、坂本は、早大総長を務めた天野為之の『経済原論』を出版して大成功を収めることになる。天野が早稲田において原書を用いず日本語で行った講義が好評を博し、それをまとめたものが『経済原論』であった。同著について、天野自ら、「私は幸運にも私の処女作に成功し、冨山房も処女出版に成功した訳である」(『日本語を作った男 上田万年』山口謡司)と述べている。
なお、坂本嘉治馬について一言補足すれば、このシリーズにおいて何度も紹介している上田万年との関わりがある。前号でふれた上田万年の『国語のため』は、坂本の冨山房でから出版されており、その後、万年と坂本は非常に親しくなったようである。上田万年は、晩年には、毎夏鎌倉の大仏裏にある坂本の家に避暑に出かけたということである。
いずれにしても、天野の新たな企画の成功も後押しとなり、この頃からようやく邦語での学術書が世に問われ始めたようである。
益川氏の「自国語で深く考えることができるのはすごいことだ」という言葉から、われわれは、今日、国語(日本語)で書かれた文献がいかに整っているかということに改めて気づかされるものがある。同時に、益川氏の言葉は、明治以降の先人の努力の大きさ、先人の努力の中で、国語(日本語)がいかに磨かれ高められてきたかということをわれわれに教えてくれるようにも思えるのである。
前号では、上田万年を中心に国語成立についての考察を行った。その中の大きなテーマは、「言文一致体」であり、「漱石の文体は、万年が望む言文一致体であった」という言葉が前号の結語とも言うべきものであった。
本号では、水村美苗『日本語が亡びるとき』に依拠しながら、水村の主張、特に翻訳と国語(日本語)の成立の関わりについて考えていきたい。
 水村美苗は、前々号でもふれたように国語を考える前提として、普遍語、現地語、国語という三つの概念を置いている。普遍語は、かつての東アジアにおける漢文や、かつてのヨーロッパにおけるラテン語のように、書き言葉であり、学問のための言葉であるとしている。現地語は巷で人々が使う言葉であり、「口語俗語」あるいは「母語」といわれるものである。それでは、国語はどのように定義できるだろうか。
水村美苗は、前々号でもふれたように国語を考える前提として、普遍語、現地語、国語という三つの概念を置いている。普遍語は、かつての東アジアにおける漢文や、かつてのヨーロッパにおけるラテン語のように、書き言葉であり、学問のための言葉であるとしている。現地語は巷で人々が使う言葉であり、「口語俗語」あるいは「母語」といわれるものである。それでは、国語はどのように定義できるだろうか。
水村は、ふたつの捉え方で国語を定義している。ひとつ目の定義は、国語とは、「国民国家の国民が自分たちの言葉だと思っている言葉」とするものである。
この定義は、前号でも見たように、わが国の国語は明治期すなわちわが国が国民国家を形成する中でつくられたものであることからも頷けるものがある。さらに、これも既にふれているように、加藤徹が『漢文の素養』において、「国民国家とは、国民・国語・国軍の三点セットからなる近代国家を言う」としている見解も水村の定義を補っている。
国語についての水村のふたつ目の定義については、以下再掲したい。
ふたつ目の定義、即ち翻訳と国語の関係については、まず、ヨーロッパにおける動きから述べてみたい。
水村は、翻訳という行為の重要性、影響力を強調する。翻訳の本質を上位レベルにある言葉から下位のレベルにある言葉へ、叡智や思考のしかたを移すことにあるとし、とりわけ、初期において、その任に当たった人物として、ダンテやルター等をあげている。
ダンテはイタリア語において、ルターはドイツ語において、いわゆる「国語」成立の基礎をつくった人物であることで知られている。ダンテにはトスカナ方言で書かれた『神曲』があり、ルターには新約聖書のドイツ語訳がある。一方で、二人は、ラテン語による作品も著している。すなわち、「国語」成立の基礎をつくった彼らに共通するものとして、普遍語であるラテン語への通暁があったことは指摘しておきたい点である。
ダンテやルターもそうであったように、普遍語に通じ、現地語でも書いた人々、水村の表現における「二重言語者」は、翻訳をしながら結果として現地語を普遍語の高みに近づけるべく、現地語を押し上げる役割を果たしていくことになる。

ルター
水村は、現地語が国語になる過程を図書館に例えている。
ヨーロッパにおいては、ある時期までは普遍語からなる「ラテン語の図書館」しか存在しなかったものの、やがて「現地語の図書館」が出現するようになったというのである。
一千年に及ぶ叡智の蓄積のある「ラテン語の図書館」は、圧倒的な質と量を誇り、いわば知を独占していた。しかしながら、やがて、普遍語から現地語への翻訳を通じ、「人類の叡智」は、少しずつ「現地語の図書館」に移されることになる。現地語が次第に磨かれ高められ「国語」へと向かう中で、「現地語の図書館」は、さらに充実するようになる。その結果、かつては「ラテン語の図書館」にしか出入りしなかった優れた知性の持ち主、ここでも水村の表現によれば「叡智を求める人々」は、双方の図書館に出入りするようになり、最終的には「現地語の図書館」にしか出入りしなくなっていく。そして、そのときが「国語」の本当の成立になったと水村は結論づけている。
水村によれば、ヨーロッパにおいて、現地語が「国語」になるためには、二重言語者による普遍語から現地語への翻訳が多大なる貢献をしているということになる。
実は、翻訳の重要性はわが国にもあてはまることであった。
明治期、わが国が独立国家として国力を高めるためには、いわゆる西洋に学びながら西洋の文物を取り入れることが必要であった。当然に西洋の学問の摂取が求められ、必然的に翻訳という営みが重要になっていった。
当時のわが国で翻訳を担ったのは、アジアの普遍語である「漢文」に通暁した人々であった。水村は、当時翻訳を担った優れた知性の持ち主を「叡智を求める人々」と表現した上で、以下のように述べている。
水村は、福沢諭吉について、蘭学さらには英語への取り組み、咸臨丸での渡米から帰国の折に日本で初めて『ウェブスター大辞書』を買って帰ってきたこと等にふれながら、諭吉の西洋語との関わりを述べている。そして、諭吉の造語として「演説」「賛成」等を挙げた上で、翻訳とわが国の「国語」の成立について以下のようにまとめている。

二葉亭四迷
翻訳が国語成立に果たした意義に関連して、水村は二葉亭四迷を例に挙げている。
東京外国語学校でロシア文学を深く学びロシア語を自らのものにした四迷は、前号でも取り上げたように言文一致体からなる『浮雲』を著し、また、それまでの翻案とは異なり、逐語訳の正確な訳によるツルゲーネフの『あひヾき』の翻訳を行ったことで知られている。水村は、それぞれの業績を「日本初の近代小説の作者」、「初めて文学の翻訳たるものの意味を知らしめた人物」とした上で、「日本初の近代小説を書いた人物が、日本初の小説の翻訳家であったのは、偶然であるよりも必然であった」と述べ、翻訳の意義、さらには翻訳が国語(日本語)さらには近代文学に与えた影響について言及している。
福沢諭吉を始めとする上述の二重言語者である諸人物が国語の成立に貢献したように、水村は、西洋語の<図書館>に出入りするようになった人物により、わが国の近代文学が多大の恩恵を蒙ったとしている。
水村は、英文学を学んだ漱石はもとより、「英語を驚くほどしかも速く読んだ芥川龍之介、丸善に借金を返せなくなったほど洋書買いまくった大佛次郎、ヴィクトル・ユーゴーの英訳をむさぼるように読んだ中里介山、英語を流暢に読んだ谷崎潤一郎」といった表現でそれぞれの文学者を紹介しながら、近代文学の発展に寄与した人物と西洋語の関わりについて述べている。
彼らは、必ずしも翻訳そのものは行わなかったにせよ、西洋語に学びながら、国語をそして近代文学を高めるために多大の貢献を行ったとしている。
言文一致体の成立、翻訳という作業に献身した人々、翻訳には手を染めなかった人物も含め西洋語を学びながら近代文学を高めた文学者たち、こうした要素が相俟って国語(日本語)が確立していくことになる。
1951年生まれの水村は、十二歳で父の仕事の関係で米国に渡った。米国での生活になじめない彼女は、1960年代前半、ニューヨーク郊外の一軒家で、ルビを頼りに水村の母が母の伯父から譲り受けたという日本語の近代文学全集をひたすら読んだという。その全集は1926(大正十五)年に発行された改造社の『現代日本文学全集』であった。アメリカには『ペンギン・クラシックス』があり、フランスには『プレーヤード叢書』がある。従って、1960年代前半、西洋人の文学好きの少女にとっては、文学を読んで日々を過ごすことが可能だったとした上で、以下のように述べる。
 水村のこの言葉は、国語(日本語)の成立についてのみならず、国語(日本語)が急速に高みに到達していることについてまでをも述べている一節にも思えてくる。
水村のこの言葉は、国語(日本語)の成立についてのみならず、国語(日本語)が急速に高みに到達していることについてまでをも述べている一節にも思えてくる。
漱石が『我輩は猫である』を「ホトゝギス」に発表したのが1905(明治三十八)年であったことを思うと、それから二十年程で優れた近代文学全集が出版されていたことに驚きを禁じえない。繰り返しになるが、国語(日本語)が急速に高みに到達しているとの感に打たれるのである。
近代文学のみならず、学術書(翻訳書、日本人による日本語のオリジナル文献)も含め、「国語(日本語)の図書館」は、その後、充実に充実を重ねていく。そのことが、上述のノーベル賞受賞の益川氏の言葉につながっていくのであろう。
源氏物語以来の文学の伝統、あるいは江戸時代を中心とした明治以前の文化の高さはあるにしても、漱石以降約100年という限られた時間における「日本語(国語)の図書館」の充実ぶりは、評価しても評価しきれないものがあると感じている。もとより、それは、国語力にも大いに関係していることは疑いのないことと思われる。
ところで、タイトルの『日本語が亡びるとき』が示すとおり、水村は、日本語の今後に大きな懸念を抱いている。そして、水村の日本語の将来への懸念に関し、興味深いのは、彼女がこれからの国語教育ではなくこれからの英語教育のあり方に注目している点である。結論を先に申し上げれば、日本語が亡びるか亡びないかは、わが国の今後の英語教育にあるというのが水村の見解なのである。水村の主張にもう少し耳を傾けながら、英語教育にもふれつつ国語力についてさらに考えていきたいと思う。