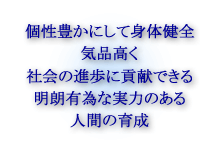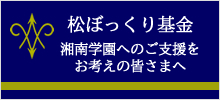第238回 <言葉の力>を回復するために(続)
 前回の続きで、ある書籍について紹介します。
前回の続きで、ある書籍について紹介します。
インターネットの浸透やコロナ禍のストレスも受けて、人びとの不安や息苦しさが深まり、日本の社会には空疎な言葉や敵対・憎悪に満ちた言葉が氾濫しています。ハラスメントやいじめが頻発し、ヘイトスピーチが横行し、信じ難い発言が政治家から発せられ、SNS上で社会的弱者が標的になる過酷な実例もたくさんあります。
その中で<言葉の力>の回復を願う筆者は、先人の苦闘に学びながら自分に問いかけ、読者に語りかけます。近著の『まとまらない言葉を生きる』(荒井裕樹著、柏書房)という本について更にご紹介します。
息苦しい言葉があふれる社会でも、言葉には本来もっと力があると信じ、日常の出来事や長年関わる人との交流から得た言葉や、心に残る本の一節を丹念にたどっていく内容です。
荒井氏は大学教員であり、「障害者文化論」を専門とする文学者です。障害者運動に関わる人たちと接して共に生きる時間を数多く体験した方です。
自分を表現することが苦手だった筆者は、学生時代に「とても誠実な自己表現をする人たち」に出会って視野を広げます。「自分らしい言葉」で社会の理不尽と闘ったり、世間の冷たい風をいなしながら、人生を楽しむ人たちでした。教員免許取得へ向けた知的障害者施設での辛い体験も、その後の出会いの積み重ねを経てつかみ直されていきます。差別や偏見と闘う人たちが祈る思いで紡いだ表現に惹かれ、自分達を励ます力も持つ言葉を心に留めていきます。
 東日本大震災では、安易な励ます言葉が許されない状況下で、多数の人たちに向けられた言葉は「網み目が粗く」なり、「被災者」といっても実際にいるのは独りひとりが個別の事情を抱えた人間であることが確認されます。どんな状況においても「誰かの言葉に励まされる経験」は確かにあるから、誠実な「言葉探し」を続けるしかないのです。
東日本大震災では、安易な励ます言葉が許されない状況下で、多数の人たちに向けられた言葉は「網み目が粗く」なり、「被災者」といっても実際にいるのは独りひとりが個別の事情を抱えた人間であることが確認されます。どんな状況においても「誰かの言葉に励まされる経験」は確かにあるから、誠実な「言葉探し」を続けるしかないのです。
荒井氏は、障害者運動に関わる人たちは差別や人権について突き詰めて考えており、その言葉は私たちの人生も照らし出し、自分の生活に引き寄せて考える機会になると述べます。身近な所で社会から「見放されている」といつも感じる人たちが呟いた言葉や紡ぎ出した言葉に着目してほしいと説かれるのです。
この本にはそうした人びととの出会いや学んだことが記されています。例をあげれば、水俣病の患者、ハンセン病回復者、精神科医療を告発する患者、脳性マヒ者の運動家、戦時中の体験を語る障害者、障害者運動家の妻として苦労した女性、家族のALS発病を受けて支援活動を行う女性などが登場します。
 また、休職者を非難していた自分がうつ病になって苦しむ人や、育休終了後に保育園の目途が立たない女性など、身近な難問に直面する人たちも登場し、その言葉にも切実な説得力が感じられました。
また、休職者を非難していた自分がうつ病になって苦しむ人や、育休終了後に保育園の目途が立たない女性など、身近な難問に直面する人たちも登場し、その言葉にも切実な説得力が感じられました。
周囲からの「黙らせる圧力」がいかに当事者を追い詰めるか。若い世代にまで浸透する「自己責任」(その氾濫には政治の責任がある)という危険な言葉に対して、どう抗っていくかも筆者は論じます。
この社会は「安易な要約主義」の道を突っ走っているのではとも問いかけます。とにかく短く、わかりやすく、白黒はっきり、敵と味方を区別しやすく、感情の整理を付けやすくする言葉や安易なキャッチフレーズが重宝され、世間にあふれていると警告されます。
コロナ禍がこの傾向に拍車をかけ、数字化されたデータばかり注目されるが、当事者の苦しみの内実はそれぞれ違うし、日々更新される数字の裏には「要約」など出来ない独りひとりの人生があることについて、いつも注意すべきではないかと諭されます。
 私自身も仕事で私生活で「安易な要約主義」に陥ることがあることを反省します。同時に荒井氏の課題提起を自分なりに整理して学び、今後の指針として生かしていきたい気持ちで読み進めました。皆さまにも是非ご一読をお薦めいたします。
私自身も仕事で私生活で「安易な要約主義」に陥ることがあることを反省します。同時に荒井氏の課題提起を自分なりに整理して学び、今後の指針として生かしていきたい気持ちで読み進めました。皆さまにも是非ご一読をお薦めいたします。
本の結びで筆者は、“私たちは皆、「要約」できない人生を、うまく言葉にまとめられないまま、とにかく今日という日を生きています。その「まとまらなさ」こそ愛おしいと思います。願わくば、その愛おしさを読者の皆さんと分かち合えますように。・・・・・・”と記していました。
こうした人間観は、どんな人間との出会いの場面でも心に留めたい見方であると感じられます。若者や子どもと対話したり助言をする場面でも、親や教員がふまえておくべき視点であると思われました。
 学園長通信は今年度も、毎週水曜日を基本に発信してきました。多くの皆様方に読んでいただき、心からお礼を申し上げます。
学園長通信は今年度も、毎週水曜日を基本に発信してきました。多くの皆様方に読んでいただき、心からお礼を申し上げます。
新年は1月12日(水)から通信を再開します。真冬が近づく中で、皆様くれぐれもお身体に気をつけられ、良いお年をお迎えください。