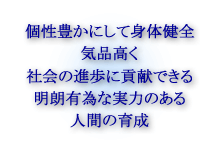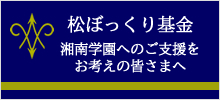湘南学園UPDATE~教職員の学び合い~
新学期を迎えて 〜 猛暑と向き合った夏を振り返る
まもなく夏休みが終わり、授業が再開します。日中は依然として厳しい暑さが続いており、猛暑日になることもありますが、朝晩には少しずつ涼しさが感じられるようになりました。吹く風に心地よさを感じるたびに、季節が少しずつ移り変わっていることを実感します。皆さま、お元気でこの夏をお過ごしになったでしょうか。
この夏は、記録的な猛暑に加え、豪雨、地震、津波といった自然災害が世界中で頻発しました。「今までで一番暑い夏でした」というフレーズは、もはや毎年のように耳にするようになりました。「冷房なしでは寝られない」「日傘がないと歩けない」「30度と聞くと涼しいと感じる」「ついに40度を経験した」といった声が聞かれるように、私たちの生活は大きく変わりました。35度という数字を見ても驚かなくなってしまったのは、温暖化による気候変動が私たちの感覚をも変えてしまった証拠でしょう。この状況は日本だけでなく、世界中で起こっており、豪雨による洪水や干ばつによる砂漠化などを見ると、地球が悲鳴を上げていることが痛感されます。「地球の声を聴いていますか?」という問いに、私たちはどのように答えればよいのでしょうか。国連で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)は、2030年までに持続可能な社会に近づくことを目指していますが、私たち一人ひとりの行動が、その達成に欠かせないことを改めて認識する必要があります。
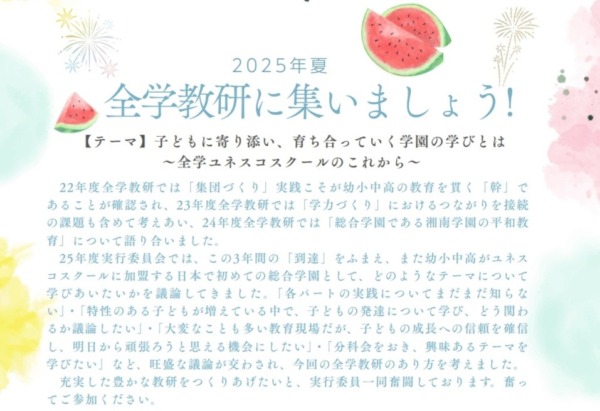
全学研修会で探求した「子ども中心の学び」
8月28日、幼稚園から高校までの教職員と理事が一堂に会し、全学研修会(全学教研)を開催しました。今年のテーマは、「子どもに寄り添い、育ち合っていく学園の学びとは〜全学ユネスコスクールのこれから〜」。これは、幼小中高すべての校種がユネスコスクールに加盟した記念すべき年に、今後の教育のあり方を確認し合う大切な機会となりました。
この研修会の目的は、単なる情報共有にとどまりません。私たちは、各校種の「子どもの育ち」を持ち寄り、教職員自身も子どもとの関係性の中で共に成長する場を探求しました。また、教育現場で直面する多様性や個性化といった現実を共有することで、自分たちの関わり方を再発見する貴重な時間となりました。子どもたちの権利と成長を起点に、教職員自身が問いを持ち寄り、語り合うことで、思考と実践を深める場となるよう工夫しました。

講演と実践発表から得た気づき
午前9時30分、中高ホールに集まり、研修会が始まりました。まず、大阪緑涼高校の藤田隆介先生をお招きし、「生徒理解と教師の仕事」というテーマでご講演いただきました。先生は、これまで出会った生徒たちとの関わりや見方、働きかけ、そして彼らがどう変わっていったかについて、一人ひとりとの温かいやり取りのエピソードを語ってくださいました。「どの子も変わる可能性を秘めています。本気で関わる大人の存在が大きな影響を与えます」という先生の言葉は、私たちの心に深く響きました。息苦しさが増す現代社会だからこそ、子ども一人ひとりをしっかり見て、話を大切に聴き、寄り添っていくことの重要性を改めて感じました。
講演後は、グループに分かれて活発な意見交換が行われ、参加者たちは熱心に感想を語り合いました。その後、研修会は幼稚園の実践発表へと続きました。幼稚園の実践は、湘南学園の教育のベースとなる大変価値あるものです。すべての活動に貫かれている「いろんな花を咲かせたい」という理念は、教師の姿勢にも表れています。「信じて待つ、見守る、子どもが主役、子どもが選ぶ、子どもが決める、子どもに任せる」といった、大人に求められる姿勢がすでに実践されているのです。幼稚園の発表を聞くたびに、私たちは「教育の目的は何か?」という原点に立ち返り、深く考えさせられます。常にその問いを意識しながら教育が行われているのが、湘南学園の幼稚園です。発表後には、カフェテリアで昼食をとりながら感想を共有し、さらに交流を深めました。

総合学園の強みを活かした分科会
午後は、「学力」「発達支援」「ユネスコスクール」の3つの分科会に分かれ、小・中高のレポート発表とグループワークを行いました。この分科会では、お互いの教育実践や取り組みについて知るだけでなく、校種間の連携、情報共有、そしてお互いを認め合い、助言し合う場面も見られました。今後の教育をさらに推進するための発言が活発に行われ、大変有意義な時間となりました。異なる校種の教職員が時間をかけて話し合う場を持てることは、まさに総合学園である湘南学園の大きな強みです。
湘南学園の教育理念と未来への展望
研修会の閉会式では、講演者の藤田先生に加え、助言者としてお招きした鎌倉女子大学の小藤俊樹教授から貴重なご意見をいただきました。先生は、ご自身の経験も交えながら、学園の教育実践を高く評価してくださり、授業改善の視点についてもご教示くださいました。そして、幼稚園から高校まで、子どもの良いところも課題も引き継いでいける一貫した教育が共有されていることから、「総合学園としての一貫教育〜子ども中心の学び」こそが、湘南学園の特色であると改めて明確になりました。これは、昨年、聖心女子大学の永田佳之教授が評価してくださった「傾聴の風土、対話の文化」の上に位置づく、湘南学園ならではの価値です。
長年にわたって築き上げてきた「対話の文化」と「傾聴する風土」を基盤に、これからも「子ども中心の学び」を大切に育んでいきたいと考えています。
ユネスコスクールは、「平和の案内役」としての使命を自覚し、平和の砦を築き、世界の平和を実現するために活動を進めていきます。また、持続可能な社会を目指すESD(持続可能な開発のための教育)を推進する拠点として、環境や社会、経済、文化を豊かに保ち、私たちの子どもや孫、地球の未来を奪わないよう、自らの生活を見直し、行動を変えていかなければなりません。
湘南学園は、このユネスコスクールとしての取り組みを湘南地区全体へと広げ、100周年に向けてさらなる発展を目指していきます。皆さまのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。