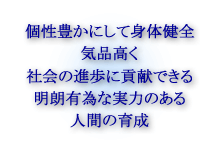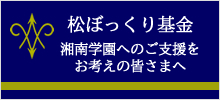シリーズⅡ 「国語力を考える(その6)」
「英語教育と国語教育」-水村美苗の考え方を中心に-
「国語力を考える」をテーマにした「シリーズⅡ」は、今回で6回目を迎えることとなった。このテーマに関し、私は、前回までの論考を踏まえながら、今後の教育におけるリベラルアーツの重要性に鑑み、その前提としての「国語力」を展望したいと考えている。
今日グローバル教育という言葉が盛んに使われている。ただし、この言葉は使い手により定義が異なり、意味内容があまりにも広がり過ぎている感がある。私は、グローバル教育において重視すべき点として三点を考えている。それは、「世界標準」であり、「リベラルアーツ」であり、「多様性と共生」である。この三点については、別の機会に改めてふれることとして、「リベラルアーツ」の重要性、およびリベラルアーツを支える「国語力」という捉え方を着地点としながら、シリーズⅡをもうしばらく継続したい。
 改めて申し上げるまでもなく、本欄は、一義的に、「湘南学園の明日を考える」ためのものである。すなわち、上述のグローバル教育において重視すべき三点、あるいは、「リベラルアーツ」の重要性及びそれを支える「国語力」という考え方は、本学園の今後の方向性と重なっている。
改めて申し上げるまでもなく、本欄は、一義的に、「湘南学園の明日を考える」ためのものである。すなわち、上述のグローバル教育において重視すべき三点、あるいは、「リベラルアーツ」の重要性及びそれを支える「国語力」という考え方は、本学園の今後の方向性と重なっている。
もとより、「世界標準」や「リベラルアーツ」を重視するという今後の本学園のあり方は、本学園が英語教育にさらに力を入れていくということにも関係している。幼稚園、小学校、中高からなる総合学園として、幼小中高の連携、教員配置の工夫等、総合学園としての特性を十分に生かしながら、英語教育の充実を図っていきたい。ただし、英語力を高めるためには国語力が肝要と考えており、国語力を前提とした英語教育の充実を図っていきたいということを一言申し添えておきたい。併せて、リベラルアーツの重視は、当然に、文系、理系という枠組みをこえた、教科横断的な、より本質を追求する学びを深めることにつながるはずである。そして、そうした学びにおいては、何よりも国語力が今まで以上に重要になると考えている。国語力の涵養においても、幼小中高からなる本学園の特性は生かされるはずであり、堅固な「国語力」を土台とした英語教育を含む教育活動の充実が本学園の目指す方向性であることを予め述べておきたい。
さて、前号との関連の話に戻りたい。
既に何度も使用しているこのシリーズのキーワードに「現地語」「国語」「普遍語」がある。
水村美苗の主張にも関連して、「植民地と言語」というテーマを設定することとし、その具体例として、幕末の世界情勢と当時わが国の置かれていた状況を考えてみたい。
水村美苗は『日本語が亡びるとき』において、歴史を冷徹に見れば幕末の日本が米国の植民地になるということはありえなかったことではないと述べている。水村は、「歴史を冷徹に見れば」とのみ記しているが、こうした考え方は、一人水村のみならず、当時の歴史を見れば否定できない側面をもっている。
 例えば、『世界史の散歩路 史料が語る世界の歴史』の中で、著者の綿引弘氏は、ヨーロッパ列強によるアジア植民地化のなかで日本が独立を守ることができた理由を外的要因と内的要因の二つの観点から説明している。
例えば、『世界史の散歩路 史料が語る世界の歴史』の中で、著者の綿引弘氏は、ヨーロッパ列強によるアジア植民地化のなかで日本が独立を守ることができた理由を外的要因と内的要因の二つの観点から説明している。
外的要因としては、米国には南北戦争があり、ロシアにはクリミア戦争の敗北や国内の農奴解放問題があったこと、さらにドイツ・イタリアには自国の統一運動があり、フランスもこの動きに巻き込まれていたことをあげている。さらに、イギリスは、インド大反乱あるいは中国の太平天国の乱に力を割かれ、日本侵略に勢力を集中する余力がなかったとしている。
内的要因としては、「幕末の志士が、日本をめぐるアジア情勢を鋭く認識し、ヨーロッパ列強の植民地化に対して警鐘を乱打し、日本の近代化に努力した点もあずかって力になっていた」としつつ、高杉晋作、久坂玄瑞の主張を紹介しながら、彼らの国際情勢を見る目の確かさを高く評価している。
歴史にもし「if」があればということになろうが、仮に上記の外的要因あるいは内定要因が違っていれば、わが国が全く別の状態に置かれていた可能性は否定できないのである。
いずれにしても様々な要因の中で独立を守ったわが国が、仮に米国の植民地となっていたと仮定すると、言語に関して言えば、植民地に典型的な二重言語状態になっていたであろうとするのが水村の主張である。
植民地に典型的な二重言語状態とは、宗主国の支配層を取り巻く植民地人(植民地人の中で有力な地位を占めている者)は、宗主国の言語に精通しながら現地語での読み書きもするという状態を指す。仮に幕末に日本が米国の植民地になったとすれば、当然に優れた日本の人材は英語に習熟し、英語で読み書きをすることになったことが容易に予想できる。水村は、宗主国(この場合は米国)の植民地(この場合は日本)における選抜制度が出自や貧富等を問わない公平なものであればあるほど、「日本人の優れた人材は、英語を読み書きする二重言語者となり、ことごとく『英語の<図書館>』に吸い込まれてしまうようになる」としている。
仮にわが国が植民地になっていたとしても、その後の日常生活においては、当然に日本語が使われていたであろう。しかしながら、現在われわれが使っている磨かれ高められた「国語としての日本語」ではなく、「現地語としての日本語」に止まった可能性は否定できない。既に何度か引用した益川敏英氏の「日本語で最先端のことまで学問ができる」ことなどは夢のまた夢ということになっていた可能性は高いのである。
そのような例をなぜ申し上げるかというのは、シンガポールとの比較で日本を考えてみたいという問題意識からである。
シンガポールは、言うまでもなく英国の植民地であった。今日シンガポールは、公式にはマレー語が「国語」であり、マレー語を含む、中国語、タミル語、英語の四カ国語が「公用語」となっている。

シンガポール
シンガポールにおいては、国民教育の時間の多くが英語に割かれ、英語での授業は、小学校、中学校、高等学校と上のレベルに行くにつれて増え、大学に至ってはほとんどの授業が英語で行われているとしている。そうした中で、民族語は政府による保護により「公用語」としての地位が与えられ、学ぶことが奨励されているにもかかわらず、事実上は「現地語」に留まっているというのである。
水村の以下の指摘は、現地語と国語を考える上で誠に重要な点であろうと思われる。
水村のこの見解から、シンガポールを国民総バイリンガル社会として理想的に見るというわが国においてしばしば述べられる捉え方は、やはり一面的である感は否めない。<話し言葉>を中心に見ればそうであっても、<書き言葉>に関しては明らかな違いがある。シンガポール人が真剣に出入りするのは英語の<図書館>であり、シンガポール人の作家はふつう英語で書くというのはその例証となろう。公用語であり「国語」でもあるマレー語が学問のための言葉ではないということは、日本語(国語)の図書館が完備しているわが国の状況とは決定的に異なっているということになる。こうしたことは、わが国とシンガポールを比較する上で見落とせない視点であろうと思っている。
ここで、前号での英語教育の三つの方針を確認したい。水村は、英語の世紀に入った以上、国益の観点からも、すべての非英語圏の国家が、優れた英語の使い手を、十分な数、育てなければならなくなったとし、その上で提示したのが以下の三つの方針であった。
Ⅰ <国語>を英語にしてしまうこと
Ⅱ 国民の全員がバイリンガルになるのを目指すこと
Ⅲ 国民の一部がバイリンガルになるのを目指すこと
水村の結論は、既に述べているようにⅢであった。
ところで、水村はⅡの方針に関し、「英語第二公用語論」と重ねながら論を展開している。
「英語第二公用語論」は、2000年1月、当時の小渕首相の下での「二十一世紀日本の構想」懇談会が出した構想であり、「英語の実用能力を日本人が身につけるのは不可欠であること」「長期的には英語を第二公用語とすることも視野に入れること」を主な内容とするものである。この構想には賛否両論が寄せられ大きな話題となった。
 この構想については、ロシア語の同時通訳者として、さらにエッセイストとしても活躍した米原万里が、『米原万里の「愛の法則」』において、水村とほぼ同趣旨の指摘をしている。それは、今回の「英語第二公用語論」は、明治期に森有礼が英語を国語にすべきと主張し、その後北一輝がエスペラント語を、あるいは戦後志賀直哉が仏語を公用語にすべきと主張したその一連の流れの中にあるとするものである。米原は、植民地になった国がやむなく宗主国の言葉を公用語にすることはあっても、自分たちが使っている言葉を投げ出し、よその国の言葉を公用語にするというのは非常に珍しいとし、さらに、「こういうおめでたさ、つまり、自分の言語とか文化を簡単に軽んじるというか、重要視しない、こういう能天気な気持ちでいられるというのは、ある意味では、天然の国境にずっと囲まれていた気楽さからくるものだと思います」と述べている。
この構想については、ロシア語の同時通訳者として、さらにエッセイストとしても活躍した米原万里が、『米原万里の「愛の法則」』において、水村とほぼ同趣旨の指摘をしている。それは、今回の「英語第二公用語論」は、明治期に森有礼が英語を国語にすべきと主張し、その後北一輝がエスペラント語を、あるいは戦後志賀直哉が仏語を公用語にすべきと主張したその一連の流れの中にあるとするものである。米原は、植民地になった国がやむなく宗主国の言葉を公用語にすることはあっても、自分たちが使っている言葉を投げ出し、よその国の言葉を公用語にするというのは非常に珍しいとし、さらに、「こういうおめでたさ、つまり、自分の言語とか文化を簡単に軽んじるというか、重要視しない、こういう能天気な気持ちでいられるというのは、ある意味では、天然の国境にずっと囲まれていた気楽さからくるものだと思います」と述べている。
天然の国境論も含め、米原の主張と大筋では同じ立場をとりながら、水村は、森や北や志賀の主張と今回の「英語第二公用語論」の違いを「日本語を維持しながら英語も」という点にあるとしている。
水村は、「英語第二公用語論」の立場に立つ船橋洋一氏による「英語が世界の公用語となっている中で、その認識が不足し、結果として下手なままにとどまる日本人の英語がいかに日本の国益を損ねているか」という主張は十分理解できるとしながらも、方針のⅡである「国民の全員がバイリンガルになるのを目指すこと」には反対する。
一言補足すれば、水村は、「英語第二公用語論」は立ち消えになったとしつつも、その前提にある「多くの人が学校教育を通じて英語ができるようになればなるほどいい」という考え方は、方針Ⅱの「国民の全員がバイリンガルになるのを目指すこと」につながるとしている。
Ⅱに反対する理由の詳細は省くものの、ひとつには、わが国の地理・風土、歴史、産業構造、今後の移民の見通し、外国企業の参入見通し等の分析を通して、Ⅱを目指す必要はないとするものである。反対理由としてそれ以上に注目したいのが、国語及び英語についての水村の考え方である。
 国語については、既に見てきたことからもお分かりのように、国語の図書館の充実をも踏まえながら、日本人に重要なのは何よりも国語(日本語)であり、国語(日本語)教育にこそ力点を置くべきと主張する。一方、英語については、少数の卓越した英語の使い手を育成することに主眼が置かれている。すなわち、今後わが国に必要なのは、「国民全体への国語教育の充実」と、圧倒的な英語力をもつ「優れたバイリンガルの育成」にあると主張している。
国語については、既に見てきたことからもお分かりのように、国語の図書館の充実をも踏まえながら、日本人に重要なのは何よりも国語(日本語)であり、国語(日本語)教育にこそ力点を置くべきと主張する。一方、英語については、少数の卓越した英語の使い手を育成することに主眼が置かれている。すなわち、今後わが国に必要なのは、「国民全体への国語教育の充実」と、圧倒的な英語力をもつ「優れたバイリンガルの育成」にあると主張している。
ここで、水村の述べる「優れたバイリンガルの育成」についてふれておきたい。
今後のわが国に必要な「優れたバイリンガル」には、国益を代表し、交渉の場で堂々と意見を述べることのみならず、時には自国批判を行うことも厭わず、また意地悪な質問には諧謔を交えて切り返すことのできるような英語力を求めている。同時に、インターネットでブログが飛び交い、政治そのものが世界の無数の人の<書き言葉>で動かされるこれからの時代にあっては、優れた英語の「書き手」であることが何よりも重要としている。そうした「優れたバイリンガル」をどのようにして必要な数だけ養成するか。水村は、全ての国民に同じ英語教育を行うことや、市場の力に任せることでは養成できないと断じている。すなわち、英語教育においては、日本が大切に守ってきた平等主義とは訣別し、Ⅱの方針ではなく、Ⅲの方針により、国策として少数の<選ばれた人>を育てるほかはないと主張するのである。
それでは、国民全体にはどのような英語教育を行うべきか。水村の結論は、「学校教育では、英語を読むとっかかりを与え、その先は、英語は選択科目にすべきである」というものである。もちろん、それ以上英語を勉強したい人は、学校の外で自主的に英語を学べばよいのであり、そのための方法は数多くあり、しかも安価で実践が可能であるとしている。付言すれば、水村は、併せて、他の言語の学習も奨励している。
 英語教育に関連し、インターネットの時代に必要なのは、「片言でも通じる喜び」などではなく、「読む能力」であり、「読む能力」こそが外国語を学ぶ基礎であるということが強調されている。
英語教育に関連し、インターネットの時代に必要なのは、「片言でも通じる喜び」などではなく、「読む能力」であり、「読む能力」こそが外国語を学ぶ基礎であるということが強調されている。
既述のように、水村の主張には、「教育は時間とエネルギーの配分であり、英語教育に時間をかければかけるほど、何かを疎かにせねばならない」という考え方が背景にある。
日本の学校教育においては、英語には「ここまで」という線を引き、「日本人は何よりもまず国語(日本語)ができるようになるべきであるという前提に立つべし」と水村は主張する。
「人間を人間たらしめるのは、国家でもなく、血でもなく、その人間が使う言葉であり」「日本人を日本人たらしめるのは、日本の国家でもなく、日本人の血でもなく、日本語なのである。それも、長い<書き言葉>の伝統をもった日本語なのである」とし、「<国語>こそ可能な限り格差をなくすべきである」と水村は述べる。そして、それは、<自分たちの言葉>である日本語など自然に学べるだろうと文部科学省や多くの日本人が考えているとすればそれは大いなる誤りであるとする彼女の考えに基づいている。
国語教育と関連して、水村は、米国における自らの体験を披瀝している。
水村によれば、米国では、地域の差、貧富の差、能力の差に応じ、全くレベルの違う授業が行われているとした上で、自らが通ったハイスクールの教育に言及する。数学や理科は難易度を自分で選べたものの、<国語>だけは、過去の成績をもとに上中下の三種類のクラスに振り分けられていた。上級のクラスではギリシア神話やホメロスまで遡って古典の教養を身につけさせられ、中級のクラスはアメリカ文学とともにシェークスピアやディケンズが読まされていた。
それとは別に、ふつうの授業にはついてゆけない一握りの生徒を集めた下級のクラスがあり、生徒間では「ダム・クラス(dumb class)」―――「お馬鹿さんのクラス」と呼ばれていたという。水村は、「英語ができない私はそこに入れられた」とし、そこでの授業は英語で書かれた文学の伝承などとは無縁の読み書きに主眼が置かれたものであり、「誰が書いたともわからぬ、生徒たちと同じ年ぐらいの主人公が生徒たちとおなじような日常生活を送っている物語―――しかも生徒たちが理解できる文章で綴られた物語が入っている教科書であった」と述懐している。
水村は、1998年にパリのシンポジウムに講師として招かれ、「日本近代文学―――その二つの時間」というタイトルのフランス語による講演を行っている。その講演後に、シンポジウムに参加した女性が歩み寄り、「日本文学のような主要な文学( une littérature majeure)を書いているあなたとは比べられませんが・・・」という感想を寄せた。水村は、「主要な文学」という言葉が強い印象として残り、その後脳裏を離れなかったと述べている。
そして、それから十年後、水村は、米国アイオワ大学主催の国際創作プログラムに参加した。約一ヵ月間、アジア、アフリカ、中東、東欧、西欧、北欧、南米の作家と起居を共にするというプログラムであった。そのプログラムをとおして、水村は、地球のあらゆるところで、作家が自分たちの言葉で書いているということに改めて気づいていく。併せて、今、地球上にある六千ともいわれる言葉の八割以上が、今世紀末までに消滅するという予測があったことを思い起こすのである。
脳裏を離れなかった「主要な文学」という言葉。水村は、その言葉の意味するところを、パリから十年後のアイオワで見いだしたのであった。
それは、「日本語が「亡びる」のを嘆くことのできる近代文学をもっていた事実である。しかも、その事実が、世界の読書人のあいだで一応知られているという事実である」ということであった。
水村は、傍証として、世界で一番権威があるとされる百科事典『ブリタニカ』の「日本文学」の最初の部分を引く。
一万六千語近くからなるというこの項目の執筆者はドナルド・キーンであるという。それはさておき、水村は、日本文学が「主要な文学」であること、同時に日本近代文学が極めて高い水準にあることに改めて気づいていく。高い水準については、「そのような日本近代文学が存在しえたこと自体、奇跡だと言える」という彼女の言葉からも窺えるものがある。
「主要な文学」である日本文学、奇跡とも呼べる高みをもつ日本近代文学。そのような文学をもつわが国における現行の国語教育に関し、水村は、「戦後から歳月を経るうちに、どこか「お馬鹿さんのクラス」に似た国語教育を、次第に、すべての国民に与えるようになっていったのである」と疑問を呈している。さらに、水村の言葉は続く。
それでは、引きつがれて<読まれるべき言葉>とは何か。水村は、「日本の国語教育は日本近代文学を読み継がせるのに主眼を置くべきである」と繰り返し強調する。具体的には、すべての生徒に翻訳や詩歌を含めた日本近代文学の古典を次々と読ませることを求めている。
水村は、子どもの頃に濃度の高い文章にふれれば、今巷に流通している文章がいかに安易なものか肌でわかるようになるはずとする。そして、『日本語が亡びるとき』の最後において、「私たちが知っていた日本文学とは、日本語とはこんなものではなかった、そう信じている人が少数でも存在している今ならまだ選び直すことができる」とまで述べるのである。
水村の主張には、いろいろな受け止め方があると思われる。
私自身、英語教育の専門家でもなければ、国語教育の専門家でもない者として、英語教育はあるいは国語教育はかくあるべしというものを持ち合わせているわけではない。英語教育そのもの、国語教育そのものについて論評する立場にはないものの、「教育は時間とエネルギーの配分であり、英語教育に時間をかければかけるほど、何かを疎かにせねばならない」とする水村の主張は一考に値しよう。
また、冒頭の「現地語」「国語」「普遍語」にも関連して、今日「普遍語」化しつつある英語の世紀において、「国語」としての日本語が、「現地語」に堕してしまう可能性に警鐘を鳴らす水村の考え方もまた傾聴すべき内容と感じている。
 このシリーズで述べているように、現在われわれが使っている国語は、先人の膨大な努力の中からつくられたものである。そのことからしても、「国語」について真摯に向き合うことはわれわれの責務であろうと思っている。水村は、近代国家の成り立ちを分析したベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』に言及する。まず、水村は、この本の核心を「国家は自然なものではない」と一言で要約し、同様に、『日本語が亡びるとき』の前半部分を自ら「<国語>は自然なものではない」と一言で要約している。現在、われわれが日常使用している「国語」が「自然なものではない」ということは、絶えず念頭に置きたいことである。
このシリーズで述べているように、現在われわれが使っている国語は、先人の膨大な努力の中からつくられたものである。そのことからしても、「国語」について真摯に向き合うことはわれわれの責務であろうと思っている。水村は、近代国家の成り立ちを分析したベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』に言及する。まず、水村は、この本の核心を「国家は自然なものではない」と一言で要約し、同様に、『日本語が亡びるとき』の前半部分を自ら「<国語>は自然なものではない」と一言で要約している。現在、われわれが日常使用している「国語」が「自然なものではない」ということは、絶えず念頭に置きたいことである。
冒頭述べたように、このシリーズにおいては、前回までの論考を踏まえつつ、「リベラルアーツ」の重要性、およびリベラルアーツを支える「国語力」という捉え方を着地点にしたいという展望をもっている。リベラルアーツは、これも上述のように、文系、理系という枠組みをこえた、教科横断的な、より本質を追求する学びと深く関わっており、その根底には「国語力」が据えられるものと確信している。その意味においても、やはり、国語(日本語)の重要性を指摘せざるを得ない。
英語教育について言えば、いわゆるグローバル化の中で、「英語力」と「発信力」を高めることが今日の重要なテーマであるということは私自身感じているところである。ただし、大事なことは、英語は目的ではなく手段であるということではないだろうか。英語をとおして何が表現できるか、あるいは何を表現したいのか。その中身こそが大切であろうと思っている。ともすれば、「英語、英語」の大合唱の中で、英語を学ぶことが目的化している感もある現状を冷静にとらえながら、英語教育を構築していきたい。
「教育とは、家庭環境が与えないものと、市場が与えないものを与えること」。『日本語が亡びるとき』の中で印象に残った言葉である。水村のこの言葉を反芻しつつ、本稿を閉じたい。