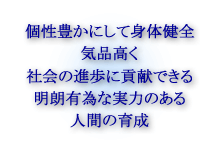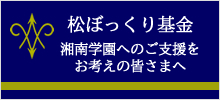シリーズⅡ 「国語力を考える(その8)」
「フランスの教育が問いかけるもの-バカロレアを中心に-」
現在のわが国の教育に関するテーマのひとつに2020年度導入予定の新たな大学入試制度がある。国語における記述問題導入は新たな入試のポイントのひとつであり、受身の学びから脱却し主体的な学びを目指す中での動きととらえることも可能である。
記述問題に関し、2016年11月27日付日経新聞には、「日曜に考える 新テスト記述式の迷宮 高大接続の理念どこに」と題する論説副委員長の署名記事が掲載された。同記事においては、記述式導入の議論が本質からそれていくことへの懸念が示され、併せて、導入例として提示されている40字~80字程度で記述式と言えるのだろうかという疑問も呈されていた。記述問題については、今後最終的な結論が出ることになると思われるが、高大接続を含め、その結論がわが国の教育にプラスに働くことのみを期待している。
ところで、以下の問題を見ていただきたい。
ご覧になり、どのような感想をもたれるだろうか。ちなみに、この問題は2010年度に実施されたフランスのバカロレア(厳密には「普通バカロレア」)の「哲学」の問題である。
ご存知のとおり、フランスのバカロレアは、後期中等教育の終了試験であり、大学入学のための資格試験としての国家試験である。すなわち、フランスの高校生が必ず受けなければならない試験がバカロレアなのである。毎年六月に行われるバカロレアの最初の時間は、決まって「哲学」の試験。フランスの高校生(日本の高校三年生相当)は、バカロレアの初日の一時間目に、上述のような「哲学」の問題に取り組んでいる。なお、バカロレアは、1808年、かの有名なナポレオン1世の勅令によって制定されて以来200年以上の歴史をもつ試験でもある。
私が大学で教えている教職希望の学生に「哲学」の問題を提示することがある。学生から返ってくる答えは、「とても手がでません。どうしたらこんな問題に解答できるのでしょうか」というものである。
日本では高校生はおろか大学生さらには大学院生も白旗をあげそうな上述のような「哲学」の問題が、なぜフランスの高校生には解答できるのか。多くの方が疑問に思われるであろうこの点についてはこの後考えていきたい。
なお、念のために申し添えると、フランスの「バカロレア」と「国際バカロレア(IB)」は全く異なるものである。本稿では言及しないものの、今後の教育を考える上で極めて重要と思われる「国際バカロレア」については、別の機会にぜひふれたいと思う。
 最近興味深く読んだ本に『哲学する子どもたち バカロレアの国フランスの教育事情』(中島さおり著)がある。昨年暮れに出版されたこの本の著者中島さおり氏は、日本の大学で仏文学を学び、パリ第三大学博士準備課程を修了し、翻訳家、エッセイストとして活躍されている方である。パリ郊外に在住の中島氏には、フランス人の夫との間に生まれた二人の子どもがおり、氏は同書において、子どもの教育をとおして見えてきたこと、考えたことも含め、日仏の教育を深く掘り下げながら、バカロレアや「哲学」に言及している。この稿のバカロレアに関する内容は、中島氏の著書に多くを負っていることを予め申し上げておきたい。
最近興味深く読んだ本に『哲学する子どもたち バカロレアの国フランスの教育事情』(中島さおり著)がある。昨年暮れに出版されたこの本の著者中島さおり氏は、日本の大学で仏文学を学び、パリ第三大学博士準備課程を修了し、翻訳家、エッセイストとして活躍されている方である。パリ郊外に在住の中島氏には、フランス人の夫との間に生まれた二人の子どもがおり、氏は同書において、子どもの教育をとおして見えてきたこと、考えたことも含め、日仏の教育を深く掘り下げながら、バカロレアや「哲学」に言及している。この稿のバカロレアに関する内容は、中島氏の著書に多くを負っていることを予め申し上げておきたい。
ここで、バカロレアに入る前に、世界各国の入試制度についてふれてみたい。
昨年六月に読売新聞教育部から『大学入試改革』という本が出版された。サブタイトルに「海外と日本の現場から」とあるように、わが国の2020年度大学入試改革を視野に入れながら、豊富な海外取材を踏まえた各国の入試制度比較がこの本の中心になっている。同時に、大学入試と高校教育とは相互に関連していることから、入試制度及び入試改革をテーマにしつつ、わが国の今後の教育のあり方を問う内容にもなっている本である。
同書では、一点刻みあるいはいわゆる一発勝負の入試を行っている国はむしろ少ないことが示され、筆記試験重視の傾向が強かった東アジアにおいても、近年、台湾や韓国ではAO入試へのシフト化傾向がみられることが指摘されている。欧米においては、大学入学資格試験、あるいは共通試験が実施され、資格を取得すれば無試験で入学できたり、あるいは共通試験の成績と調査書・面接等で進学先が決まるのが一般的であることは同書の述べていることであり、またすでに周知のことでもある。
 同書において、フランスのバカロレアについては、「試験は必修十科目程度と、二科目程度の選択科目を受験する。記述式が中心で、例えば、「哲学」の試験は、「我々は幸福のためにはあらゆることをすべきか」など、三テーマから一つを選んで、四時間をかけて論述する」と説明されている。
同書において、フランスのバカロレアについては、「試験は必修十科目程度と、二科目程度の選択科目を受験する。記述式が中心で、例えば、「哲学」の試験は、「我々は幸福のためにはあらゆることをすべきか」など、三テーマから一つを選んで、四時間をかけて論述する」と説明されている。
中島氏は、バカロレアに関し、以下の三点をポイントにあげている。「『哲学』以外の試験も論述か口頭試問であること」、上述の『大学入試改革』(読売新聞教育部)にもあるように、「受験科目数が多いこと」、「自由選択科目があることも含め、受験に無関係の教科がないゆえ、「受験勉強」が「高校の勉強」と別のものにはなり得ないこと」がそれである。
一点目について言えば、たとえば、2016年のバカロレアの歴史の問題が、「歴史家と第二次世界大戦の記憶」、「歴史家とアルジェリア戦争の記憶」、「ドレフュス事件以来のフランスにおける大きな政治的危機におけるメディアと世論」、この中からひとつを選んで論述せよという問題であったことはその例証となろう。さらに、問題には、「授業で習ったことを根拠にして」書けという指示があり、まさに学校で学んだ内容が問われていることを中島氏は強調している。
二点目については、たとえば理系の場合、フランス語、グループ研究、歴史・地理、数学、第一外国語、第二外国語、哲学と体育(ただし、体育は平常点で、特別な試験はない)。理系科目は物理・化学が必修。その他に地学・生物学か工学か環境学・農学のなかから、もう一科目を必ず選択しなければならない。そのうえで、特別科目としてまた別の理系科目を選ぶか、すでに選んだものを重複して選ぶかする。以上が課されるとしている。受験科目の多さが確認できる内容といえよう。
三点目については、バカロレアには自由選択科目があり、受験しなくても構わないが、高得点を収めると加算され、低得点の場合は考慮されないということで、得意なものがあれば受験したほうが有利な制度になっている。理数系の場合は、自由選択科目は、第三外国語、手話、ラテン語、ギリシャ語、体育、美術、音楽、馬術、社会文化からなり、この中から最大二科目まで選んで受験できるということである。
確かに、二点目と三点目を合わせると、上述の「受験に無関係の教科がないゆえ、「受験勉強」が「高校の勉強」と別のものにはなり得ない」ということが説得力をもって伝わってくる。
さらに、バカロレアについては、高校を会場として試験が行われること、高校の教育がバカロレアに直結しているため予備校や塾があまり発達しないこと、大学入試ではないので受験に一銭もかからず、したがって大学の収入源にはなり得ないことなども挙げられている。
さらに、中島氏は以下のように述べている。
中島氏によれば、詳細な説明は省くものの、フランスの高校生の進学先は、バカロレアを待たずに五月ごろ、過去二年間の成績をもとにだいだい決まるのだという。とはいえ、バカロレアが重要でないというわけではなく、バカロレアに合格しないと進学はできなくなり、また、成績が特に良いと進学先の変更の余地もあるとしている。
フランスの高校生がよく勉強すること、絶えずある小試験の平常点が重要であることに関連しての話になる。
「学園長からのたより」のもう一つのシリーズ「折々のこと」(2016年12月号)で、現在湘南学園に留学しているフランスの高校生マリーヌさんを紹介した。私がお会いした折、マリーヌさんは、カミュの『異邦人』を読み大いに心を動かされたこと、心理学に関心があり、関連する本を読んでいることを話してくれた。一方、日本語の勉強にも力を入れ、日本語の力も大きく向上していることを私自身感じとることができた。その折、マリーヌさんは、本学園の同級生が定期試験の結果に一喜一憂することが不思議だと述べ、勉強の目的はもっと先にあると思うということを話してくれた。
バカロレアという易しくはないハードルが控えているフランスの高校生。ハードルを越えるために求められる日々の地道な努力の積み重ね。改めてマリーヌさんの日頃の学習への真摯な取組姿勢、定期試験に一喜一憂することへの感想等の背景を理解する思いである。
バカロレアの内容面についての話から、「哲学」及び「国語力」の話に戻りたい。
冒頭に掲げたバカロレアの「哲学」。高校生はもとよりわが国の多くの人が白旗を揚げる問題をフランスの高校生はなぜ解答することができるのか。この点について中島氏は述べている。
日本の高校生が(高校生だけではないが)頭を抱えてしまう問題に、フランスでは、高校生だれもが取り組むことができ、一定のレベルの答案を書くことができるのは、ひとえに教育であるということを氏は述べていることになる。
敢えて結論のみ申し上げれば、それは、フランスと日本の教育の違いであり、さらに言えば、国語教育の違いということになると私は考えている。バカロレアにおける「哲学」の問題について考えることは、国語教育あるいは国語力について考えることと密接に関連しており、まさに「国語力を考える」という本シリーズにふさわしいというのが私の問題意識である。
ここで、本題からそれ、私事にふれたい。
今から四十年近く前のことになる。当時、私は、イタリアのヒューマニズム教育を研究テーマに長い学生生活を送っていた。あるとき、イタリア文化会館で近藤恒一先生による「イタリアのヒューマニズム」に関する連続講座があることを知り、喜び勇んで馳せ参じた。
近藤先生は、哲学がご専門でイタリア留学のご経験も含め、イタリアの哲学に造詣が深く、当時、邦語文献としては私にとってバイブルのような本であったエウジェニオ・ガレンの『ヨーロッパの教育』の翻訳も担当されていた。先生の講義は誠に興味深く、毎回その講座に通うのが楽しみであった。時に私が疑問点を先生にお聞きすると、たちどころに丁寧に分かりやすくご説明くださった。
その講座に当時の私よりは二回りほど年長と思われる方が参加されていた。物腰や雰囲気、服装等がどことなく洗練されており何をされている方だろうと思っていた。何回目かの講座終了後に話を伺う機会があった。新聞社に勤務されパリ支局から戻られた方と知った。実は、その頃、その方がご自身のフランスでの経験をふまえた本を出版されていた。私が初めて実感を伴ってフランスの教育を知ったのはその本をとおしてであった。『小さい目のフランス日記』(根本長兵衛著)がその本である。
 本題に戻りたい。
本題に戻りたい。
フランスの現地校に通う子どもをとおして見たフランスの教育について書かれた根本氏の本の中で、私が特に注目したのが国語教育に関する部分であった。
共に小学校低学年に在学する兄と妹が、学校から帰るなり、ひたすら詩を暗記・暗誦する、そのようなことが日常なのだという。暗誦する詩人も既に名を成した人物たち。小学校低学年の子どもに、やたらに文章を丸呑みさせて役にたつのだろうかと最初は思った氏も、レシタシオン(暗誦)重視のフランスの国語教育の方が、個性尊重とか、子どもらしさとかを強調し、やたらにオリジナリティーをもてはやすわが国の教育よりも合理的なのではないか、と思うようになったという。
その上で氏は、「いい文章を読ませ、たくさん暗記させる。どんな天才少年でも、いきなり自由自在にピアノが弾けたり、オリジナリティーに満ちた油絵を描けたりするはずがない。国語習得も同じで、まず訓練、ひとの文章をおぼえ、まねることから始まる」と述べている。
フランスの教育を考える上で興味深い本に『指導者(リーダー)はこうして育つ フランスの高等教育 グラン・ゼコール』(柏倉康夫著)がある。
柏倉氏は東大仏文卒でマラルメの専門家であり、NHK論説主幹、京大大学院教授を経て、放送大学名誉教授であり、フランス共和国国家功労賞シュヴァリエを受けている方である。氏は、1974年から足かけ五年間パリに滞在し、その間娘さんと息子さんをフランスの学校に通わせている。娘さんがフランスで職を得、結婚したことから、今世紀に入り、今度はお孫さんをとおしてフランスの教育を見ることになった。
柏倉氏によれば、フランスの高校教育については、日本の高校と大きな差はなく、決定的に違うのは哲学の授業であるとしている。リセ(日本の高校)の最終学年においては、人文系に進むものは週8時間、自然科学系に進むものは週3時間、哲学の授業が行われ、「意識とは何か」、「情熱とは何か」、「他人とは」、「時間とは」、「言葉とは何か」といった基本概念を、古今の哲学者の文章をテキストにしつつ学んでいくということである。文系、理系で違うのは授業時間の多い少ないだけであり、生徒は論理の立て方、議論の構成を徹底的に学ぶことになる。
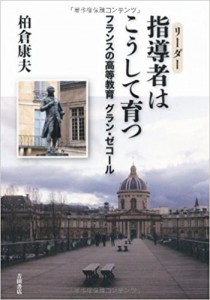 バカロレアの「哲学」の試験問題には、論理的な思考を重視するフランスの教育が反映されており、その前提として、小学校以来の国語重視の教育がある。フランスでは小学生の間に名だたる大詩人の詩や散文を徹底的に暗記させ、正しい国語で自分の考えを正確に表現することが教育の最大の眼目とされている。柏倉氏は、フランスでは子ども用に特別に書かれた詩ではなく、確固とした文学的価値をもつ作品のみを暗記させるとした上で、「思想は言葉によって育まれると信じられている文明にあって、音韻とリズムを備えた文章は、単に意思を伝えるばかりなく、感性を磨き、感情を磨くためのものとされている」と述べている。バカロレアに関して補足すれば、高校卒業の一年前(リセの第二学年)に、バカロレア受験者は全員国語(フランス語)の試験を受けることが義務付けられている。柏倉氏の本には、試験の内容も詳述されており、その内容の濃さとともに、フランスの教育においてどれだけ詩が重視されているかが窺える内容になっている。
バカロレアの「哲学」の試験問題には、論理的な思考を重視するフランスの教育が反映されており、その前提として、小学校以来の国語重視の教育がある。フランスでは小学生の間に名だたる大詩人の詩や散文を徹底的に暗記させ、正しい国語で自分の考えを正確に表現することが教育の最大の眼目とされている。柏倉氏は、フランスでは子ども用に特別に書かれた詩ではなく、確固とした文学的価値をもつ作品のみを暗記させるとした上で、「思想は言葉によって育まれると信じられている文明にあって、音韻とリズムを備えた文章は、単に意思を伝えるばかりなく、感性を磨き、感情を磨くためのものとされている」と述べている。バカロレアに関して補足すれば、高校卒業の一年前(リセの第二学年)に、バカロレア受験者は全員国語(フランス語)の試験を受けることが義務付けられている。柏倉氏の本には、試験の内容も詳述されており、その内容の濃さとともに、フランスの教育においてどれだけ詩が重視されているかが窺える内容になっている。
根本氏や柏倉氏も述べるように、フランスの国語教育では、いい文章、大詩人の詩や散文等の暗記(暗誦)に力を入れているが、それだけではない。作文のテーマに関してもわが国とは違うようである。
中島氏は、現地校で学びながら、日本語の補習校でも学んでいる二人の子どもの作文のテーマを比較しながら、本質的な違いに言及している。日本の作文は日記や感想文等が多く、「自分のこと」を書くことが多いのに対し、フランスでは、一人称を用いることが少なく、たとえ用いるにしても「現実の私」ではないことの方が多いというのである。
具体例として、中学生の娘さんへの国語(フランス語)の宿題が挙げられている。「あなたは、1914年のフランスの子どもです。ドイツとの戦争が始まった日、お父さんの召集がわかりました。その日の日記を書きなさい」。なお、この宿題は、授業で、第一次世界大戦中の出来事を語った小説を勉強した後の課題だという。
ここでは一例の紹介に止めるが、授業との関連、一人称ではあっても「現実の私」ではないという意味がお分かりいただけるのではないだろうか。
この宿題は中学校において出されたものということであるが、中学校では国語教育(フランス語教育)は文学教育が中心になるのだという。

ルソー
話をバカロレアに戻し、バカロレアの問題に関してふたつふれておきたい。
ひとつ目は、フランスのバカロレアにおける「日本語」の問題である。
フランスのバカロレアには実際に「日本語」の問題がある。というのも、第一外国語、第二外国語、第三外国語に他の言語と並んで「日本語」があるからである。
中島氏の本には、2015年のバカロレアにおける第二外国語の「日本語」の問題が紹介されている。なお、第二外国語の「日本語」を受験するのは日本語を五年間学んだフランス人ということである。
紫式部と源氏物語について書かれたテクスト1と平安時代における新しい文学の誕生について書かれたテクスト2が示され、その後に問いが設けられている。中島氏は文章の難易度としては小学校高学年レベルとしている。
問いは9問ある。「紫式部が小さかった時、女性の学者は多かったと思いますか。テクスト1のどこから分かりますか」。テクスト1の中に「お父さんは「この子が男の子だったら、立派な学者になれるのに・・・」と残念に思ったそうです」とあり、その部分を読み取らせる問題であろう。以下、問いのいくつかを列挙したい。
「紫式部はどんな子どもでしたか」
「『源氏物語』はどんな物語ですか」
「平安時代に、女の人が物を書くのは珍しかったですか。テクスト2のどこから分かりますか」
解答は全て記述であり、しかも、「特に反対の指示がない限り、完全な文章で解答しなければならない」と但し書きがある。
細かい語彙や文法、漢字の知識は一切問われていない。少しでも難しいと思われる漢字には全てルビが振ってあり、語彙にも註がついている。中島氏は、「知識を問うのではなく運用能力を見る試験」であるとしている。
ちなみに、「紫式部はどんな子どもでしたか」という問いには、「中国語と歴史の好きな勉強のできる子ども」という解答ではダメで(完全な文章で書くこととした指示に反するため)、「紫式部は中国語と歴史の好きな勉強のできる子どもでした」と書かなければならない。しかもこれだけでは半分くらいの点しかもらえず、「紫式部は平安時代の身分の低い貴族の娘で」という部分を文章中から読み取り、頭につけることが必要と中島氏は述べている。
バカロレアの一端、そして、フランスの国語教育の一端が窺える第二外国語の「日本語」の問題である。一言補足すれば、他の外国語の試験と同様、バカロレアの「日本語」の試験においても、この筆記試験の他に聴く能力と話す能力を問う口頭試験が課されることになる。
 もうひとつ、バカロレアの「哲学」の問題についてふれておきたい。
もうひとつ、バカロレアの「哲学」の問題についてふれておきたい。
バカロレアの「哲学」の問題は二種類ある。一つは論述であり、もう一つは哲学者が書いた文章の抜粋が与えられ、それを論評するというものである。
中島氏は論述の問題を例にフランスの高校生はどのような答案を書くかを示している。
論述文には、序論、本論、結論が必要としている。それなら日本も同じではないかとお思いになられる方もおられるかもしれないが、なかなかそうはいかないのである。
序論においては、与えられた問題を自分の言葉で書き直すことが求められる。
たとえば、「尊敬するためには愛さなければならないか?」という問題が出た場合、日本の小論文指導では、「愛さなければならないと思う。なぜならば」と続くであろうが、フランスの論述文は違うというのである。「ある他人を、利害関係とは無縁に絶対的な価値を持つものと考えるためには、強い愛着の感情を覚える必要があるだろうか」と問題文を書き換えねばならないというのである。以下、「愛する」とは「強い愛着の感情を持つこと」の意味で使い、「尊敬する」は「利害関係と無縁な絶対的な価値を持つものと考える」という意味で使うことをはっきりとさせるということである。その上で問題提起をするのだが、問題提起も一筋縄ではいかない。日本のように、自説のみを唱えるのではなく、「与えられた主題に、論理の一貫した答えが複数あって、それが互いに矛盾するという構図を作ること」が求められるのである。フランスの哲学の試験においては、高校生は少なくとも一人で二つの論理を発展させなければ答案を書けないというのである。ここまでが序論である。
本論では、論理的にもっともと思われる説を二つ客観的に展開していくことになる。その複数の答えを極端に押し進めていくことにより、異なる答え相互の間に、対立点をたくさん見い出していき、相反する二つの説が共に成立するという着地点に到達すること、それが本論である。
その上で結論ということになる。「いわゆる、テーズ、アンチテーズ、サンテーズという弁証法の形をとる」が、結論は、序論と本論で扱ったことの混合であってはならないとしている。結論に向けて、序論、本論で使わなかった考えをとっておくのがフランス流なのだそうであり、序論で述べたことを結論で繰り返すという日本の小論文指導との違いがここからも窺うことができるのである。
さらに、授業で習った哲学者に関しては、論述の中に自分の説を裏付けるために引用するのだという。「デカルトが言ったから正しいのではなく、正しいからこそデカルトも言った」という書き方をすることが求められるというのである。
以上、中島氏の説明の紹介であるが、四時間をかけてフランスの高校生は「哲学」の問題に挑み、このような手法を駆使しながら、答案を完成させるわけである。
 わたしたちには想像を遥かにこえるこうした答案作成。繰り返しの引用になるが、「しかし、これもどんな分野でもそうだが、格別の才能がなくても、多くの人間は「教えられればできる」のだ。一度知ってしまえば、高校生にでもできることなのだ」という中島氏の言葉が重く迫ってくる。国語教育を含めたフランスの教育が、バカロレアの「哲学」の問題に挑み、出来こそ異なるとはいえ、答案を完成させる高校生を育てていることは間違いのない事実なのである。
わたしたちには想像を遥かにこえるこうした答案作成。繰り返しの引用になるが、「しかし、これもどんな分野でもそうだが、格別の才能がなくても、多くの人間は「教えられればできる」のだ。一度知ってしまえば、高校生にでもできることなのだ」という中島氏の言葉が重く迫ってくる。国語教育を含めたフランスの教育が、バカロレアの「哲学」の問題に挑み、出来こそ異なるとはいえ、答案を完成させる高校生を育てていることは間違いのない事実なのである。
現在、フランスでは大統領選挙の真っ只中である。四人の候補が接戦を繰り広げ、さらに上位二人による決戦投票に向けての動きが進んでいる。フランス大統領とバカロレアということで中島氏が面白い話を紹介している。
バカロレアの時期になるとフランスでは著名人たちが受験生だったころ「哲学」で何点を取ったかという記事がマスコミを賑わすというのである。中島氏によれば、前大統領サルコジは、「20点満点中9点で、合格点(10点)を取れなかったということは周知の事実」であり、現大統領オランドは、「13点でまあまあの及第点」。「なんといっても優秀」なのが、大統領ではないが、ミッテラン政権でわずか37歳で首相を務め、オランド政権下で外相も務めたファビウスで、「20点満点」だという。他にも例が引かれているが、バカロレアはそれだけ一般市民の関心の的であることの証左といえよう。
本稿では、バカロレアを中心に、フランスの教育について考察してきた。もとより、国語力を考えるという問題意識が根底にある。その上で、本稿の結論に入りたい。
上記根本氏も、柏倉氏も、中島氏もそれぞれの著書で、日本とフランスの教育の優劣について言及しているわけではない。一例を引けば、柏倉氏は、「ことは優劣でなく、日本と欧米、なかでもフランスとは教育のあり方が違う、その典型が哲学教育にあらわれているという点である。こうした違いが、異なった価値観をもった人間を生み出すのは当然である。そして、国際化とは、たとえば異なる教育を受けた人たちと議論をし、相手を説得して同意を得る能力を身につけることにほかならない」と述べている。
徹底して国語を重視するフランスの教育、高校卒業認定兼大学入学資格取得試験であるバカロレア、論述と口頭試問のみからなる試験方法、「受験勉強」と「高校の勉強」が別のものにはなり得ない試験内容、併せて受験生全員に「哲学」が課されていること及びその試験内容、こうしたことからわれわれは何を学ぶべきなのだろうか。
バカロレアの「哲学」を例にとっても、わたしたちが授業で扱う哲学者の名前やその思想の内容を知ること等とは意味合いが違うことは明らかであろう。バカロレアの「哲学」は、「論理的に思考する」、「論理的な文章を書く」、「立場の違いを理解しながら対話を深める」、そうしたことのための学びであり、そのような力を培うためのものであるように感じている。
 折から、神奈川新聞に「ニッポンの人づくり 哲学する、世界が変わる」というシリーズものの記事が連載された(2016年12月から2017年2月)。わが国においても、「言葉を紡ぎ、思考を深める」、「正解のない問いを深く考える」、「他者との対話をとおして自分の価値観を見つめなおす」等の取組が、大学生、社会人、さらには小学生においても行われていることが紹介されている。
折から、神奈川新聞に「ニッポンの人づくり 哲学する、世界が変わる」というシリーズものの記事が連載された(2016年12月から2017年2月)。わが国においても、「言葉を紡ぎ、思考を深める」、「正解のない問いを深く考える」、「他者との対話をとおして自分の価値観を見つめなおす」等の取組が、大学生、社会人、さらには小学生においても行われていることが紹介されている。
そうした取組が連載記事のタイトルでもある「哲学する」と呼ばれているとすれば、まさにフランスにおける高校生の学びとしての「哲学」、あるいはバカロレアの「哲学」に近いものと言えるのではないだろうか。
このような動きをうれしく思うとともに、連載記事が紹介する意味での「哲学」をわが国の教育に取り入れることは、今後さらに研究されてよいことのように思っている。
「国語力のもつ意味を考える」ためにも、「冒頭の2020年度大学入試改革が、高大接続という本来の理想の方向に進んでいるかということも含めた日本の今後の教育を考える」ためにも、そして、「次代を担う人間をどのように育てるかということを考える」ためにも、フランスの教育について考えることは大いに意義があることのような気がしている。
最後になるが、中島さおり氏の国語教育に関する主張を以下紹介しておきたい。
「教育とは、家庭環境が与えないものと、市場が与えないものを与えること」。本シリーズ「国語力を考える(その6)」(2017年2月号)の結語として紹介した水村美苗の言葉と上述の中島氏の主張を重ね合わせながら、本稿を閉じたい。