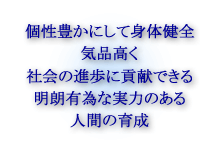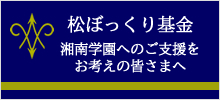第226回 全学教研集会・オンライン開催(1)
 湘南学園では、幼小中高全パートの専任教員が日常の教育実践を交流し、新たな教育の視点や今後の課題を深める機会を設けようと、「全学教育研究集会」を毎年開催しています。
湘南学園では、幼小中高全パートの専任教員が日常の教育実践を交流し、新たな教育の視点や今後の課題を深める機会を設けようと、「全学教育研究集会」を毎年開催しています。
第222回の通信で、6月末に行われた「全学教研プレ企画」についてお伝えしましたが、今回は8月27日に開催され、第10回の節目を迎えた、メイン企画の「2021全学教研」についてご紹介をします。
今年度の実行委員会では、コロナ禍の一年半の子どもたちの学園生活を振り返って気になる現実から話し合いました。そして様々な制約はあっても、学園生の学びやチャレンジを可能な限り保障しようとオンライン利用も含めて知恵を出し合い、学園生も「こうしたら実現出来ます!」と参画してきた教育活動について豊かに共有し、これから一番大切にすべき教育の課題を学んで、語り合える機会にしていこうと合意しました。
 <コロナ禍の子どもと学園教育 withコロナの一年半と、これから>を今年度のテーマに掲げ、「プレ企画」では『ちょっと気になる?!・・・子どもの心とからだ』と題する野井真吾先生のオンライン講演会を通じて、参加者一同、深い学びを共有しました。
<コロナ禍の子どもと学園教育 withコロナの一年半と、これから>を今年度のテーマに掲げ、「プレ企画」では『ちょっと気になる?!・・・子どもの心とからだ』と題する野井真吾先生のオンライン講演会を通じて、参加者一同、深い学びを共有しました。
そして今回の「メイン企画」もオンライン開催となりました。幼小中高各パートから貴重な実践報告が寄せられ、学外から多彩な分野で活躍される講師の方々もお呼びして、5つの分科会などがラインアップされましたが、コロナ禍の厳しい情勢を受け、実行委員会の先生たちは午前中のオンライン開催に短縮して実施する方向で調整してくださいました。
それでもメイン企画における学びはとても深いものとなり、今後への希望や指針を皆さんで共有できる重要な機会となりました。その概要をこれからお伝えしていきます。いつもより長くなって恐縮ですが、お読みいただければ幸いです。
まず、『子どもが子どもでいられる社会を~子どもが自己を育てていくために私たちができること~』と題された、千葉大学教育学部名誉教授の片岡洋子先生の講演をお聴きしました。
 片岡先生は、コロナ以前から指摘され、コロナ禍の中で一層あぶり出されてきた危機として、「子どもが子どもでいられない現実がある」と指摘し、「自分で自分を育てていくのを支えるのが教育の仕事」の視点から、子どもの苦悩と大人の関わりを捉える必要があると提起されました。
片岡先生は、コロナ以前から指摘され、コロナ禍の中で一層あぶり出されてきた危機として、「子どもが子どもでいられない現実がある」と指摘し、「自分で自分を育てていくのを支えるのが教育の仕事」の視点から、子どもの苦悩と大人の関わりを捉える必要があると提起されました。
その導入として、小説・映画で話題となった『あん』の作者、ドリアン助川氏の講演記録をまず紹介されました。深夜放送等で出会った中高生たちと話して「自分たちは社会で役に立つために生まれてきた。そうでなければ生きている意味はない」という声が共通することに違和感を感じ、「どんな運命を背負った人にもこの世に生まれ、この世で生きた時間があることには意味があるはず」との思いを助川氏は作品に託し、「どんなに苦しくとも自分が生きていると実感し、意味を見出せる教育を探りたい」と片岡先生は痛感されました。
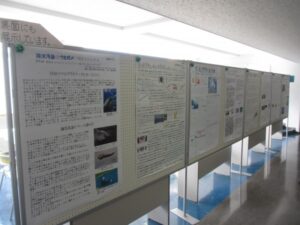 次に『プリズン・サークル』という映画を通して、国内の刑務所において実施された、受刑者たちが更生するためのTC(回復共同体)という教育プログラムの実践が紹介されました。このプログラムでは刑務官でなく支援員(心理学や福祉の専門家)が受講を希望した訓練生に対して、〇〇さんと呼ぶ真摯な対等な関係づくりに努め、1対1やグループの円卓で語り合いや問いかけがなされます。
次に『プリズン・サークル』という映画を通して、国内の刑務所において実施された、受刑者たちが更生するためのTC(回復共同体)という教育プログラムの実践が紹介されました。このプログラムでは刑務官でなく支援員(心理学や福祉の専門家)が受講を希望した訓練生に対して、〇〇さんと呼ぶ真摯な対等な関係づくりに努め、1対1やグループの円卓で語り合いや問いかけがなされます。
様々なアイスブレイクを通して生い立ちや家庭事情から、罪を犯すに至るまでの経過が思い出され、記述や語りが励まされます。訓練生の多くは親からの虐待やネグレクト、仲間のいじめなど暴力体験の中で、感情を麻痺することで生きのびてきたと推察されます。
封じていた記憶や感情に気づいて吐露する他者の語りにも触発され、自分と向き合って本音を語り、その語りを否定せずに関心を持って聞く人たちに支えられます。「自暴自棄な自分を変えたい」という自分の願いを反芻したり、一番つらかった時代の気持ちを再確認して、親に対する複雑な思いも「今が向き合う時なんだ」と言葉にしながら成長していく軌跡が感動的でした。
 次に作家の寮美千子さんが、別の刑務所で特に大きな困難を抱える受刑者の若者たちと約10年間続けた『物語の教室』の実践が紹介されました。メンバーたちを対象に絵本の朗読劇や自分の詩を書いて互いに読み合うという取り組みですが、壮絶な過去を背負い自分が何を感じるかもわからなくなり“荒野にぽつんと独りで立つ”かのような青年が、詩作を通して思いを出し合ったり、共感の言葉を受けて泣き続けた場面からその癒しを糧にして雰囲気も大きく変わり、自傷行為がぴたりと止まった人もいたことが紹介されました。
次に作家の寮美千子さんが、別の刑務所で特に大きな困難を抱える受刑者の若者たちと約10年間続けた『物語の教室』の実践が紹介されました。メンバーたちを対象に絵本の朗読劇や自分の詩を書いて互いに読み合うという取り組みですが、壮絶な過去を背負い自分が何を感じるかもわからなくなり“荒野にぽつんと独りで立つ”かのような青年が、詩作を通して思いを出し合ったり、共感の言葉を受けて泣き続けた場面からその癒しを糧にして雰囲気も大きく変わり、自傷行為がぴたりと止まった人もいたことが紹介されました。
以上を受けて片岡先生は、このような取り組みの成果は、教育学や発達心理学からどう捉えるべきか、世界と日本の教育科学の知見から説明をされました。
 ワロン(フランスの教育者)は、人間は乳幼児の段階から他者との相互作用の中で「自己受容性感覚」としての情動を発達させ自我を形成していくが、情動は他者からのケアを必要としそのケアの質と関係性に影響を受ける。情動は他者の言葉や自分の言葉の獲得と他者への表現を通じて感情へと高まっていくと説きました。先ほどの実践は、受刑者たちが青年期に、情動と感情の発達を促す言葉を獲得し直した軌跡を示していることが理解されます。
ワロン(フランスの教育者)は、人間は乳幼児の段階から他者との相互作用の中で「自己受容性感覚」としての情動を発達させ自我を形成していくが、情動は他者からのケアを必要としそのケアの質と関係性に影響を受ける。情動は他者の言葉や自分の言葉の獲得と他者への表現を通じて感情へと高まっていくと説きました。先ほどの実践は、受刑者たちが青年期に、情動と感情の発達を促す言葉を獲得し直した軌跡を示していることが理解されます。
坂元忠芳先生は、自我の発達過程を分析し、子どもの欲求と周りの関わりから他者と自己との分離が始まり、子どもは強烈に自己を反抗的に主張すると同時に、他者にいっそう甘える傾向も示すことを説かれました。
筒井順子先生は、「自己感覚」は幼児期から育っていくが、「愛情ある良い自分」も「攻撃的な自分」も両方持つことに気づいて受け入れていくことは健やかな成長の大事な証であり、「良い自分」と「悪い自分」が一つの自己として統合されていくと、並行して他者もまた両方を併せ持った存在として認識されていくことを説かれました。そしてそこに至ると人間は初めて、自分や他者を信頼し、我慢して待つこと、忍耐、思いやり、信頼、葛藤、悩むことなどが可能になると分析されました。
またL・ハーマン氏の著作から、暴力被害を受けた人たちの生きづらさや回復過程をたどる中から、「発達途上の子どもの肯定的な自己感覚は、ケアをしてくれる人が権力をおだやかに使ってくれるから生まれるのである」との重要な指摘を引用されました。
 それから片岡先生は、ごく普通の環境で育ったと映る若い世代の内面にも存在する苦悩や葛藤について、子どもの詩や作文など幅広い資料も交えて探求していきます。何気ない親や大人の一言がどんなに子どもを元気に幸せにし、深い傷も残すことか。クラスの誰にも相手にされない心配を抱え続ける小学生、いつもマラソン大会でビリになって注目を集めることがつらくて仕方ない小学生、いつも友だちの嫌悪や反発を恐れて周りに合わせる自分が嫌で変えたいと自問を続ける中学生、そうした姿を読んで自分の気持ちを素直に書けている様子に驚き、自分を振り返る大学生の姿など、読者にもじんわり共感を広げることでしょう。
それから片岡先生は、ごく普通の環境で育ったと映る若い世代の内面にも存在する苦悩や葛藤について、子どもの詩や作文など幅広い資料も交えて探求していきます。何気ない親や大人の一言がどんなに子どもを元気に幸せにし、深い傷も残すことか。クラスの誰にも相手にされない心配を抱え続ける小学生、いつもマラソン大会でビリになって注目を集めることがつらくて仕方ない小学生、いつも友だちの嫌悪や反発を恐れて周りに合わせる自分が嫌で変えたいと自問を続ける中学生、そうした姿を読んで自分の気持ちを素直に書けている様子に驚き、自分を振り返る大学生の姿など、読者にもじんわり共感を広げることでしょう。
片岡先生は、ご自分のゼミ出身の卒業生で教員になった、ある社会人の体験も紹介されます。仕事を辞めたいほど行き詰まった新任教員の時代、最も大変な児童が次々引き起こすトラブルに振り回される中で、改めて子どもの行動の意味を考え直し、学級の中のつながりをどうつくるかを追求し直しました。その子の気持ちを代弁する場面も大事にしながら、周りの子どもたちの善意や共感をひきだし、その子の本音や深い願いまでが表明されたドラマにうたれます。この経験を通って教員を続けていく心決めができたそうです。
先生は、「つらい体験を重ねた子どもは、自分の気持ちを現わす言葉が出てこないまま、自分の感情が取るに足らないものとして置き去りにされる。表現を許されなかった感情は心の中の異物となり、深い怒りの感情にも変化していく」という、森田ゆり先生の分析も紹介された上で、「これまで隠したり抑圧してきた自分の感情を解放し、それが他者に受け入れられ、改めて自己を形づくっていく」という人間の特性に注目し、学校教育が特に大事にすべき文化活動の取り組みに着目されます。
 詩や演劇、音楽やダンスなど、「情動や感情の表現が多面的な自己を統合し受け入れ、他者と相互に交流する文化活動」を指します。「ごっこ遊び」や「ファンタジー」などで、自分とは異なる誰かの役割を演じることも例示され、学校の特別活動だけでなく子育てや地域の遊びの場面でも伝統があり、「情動と感情の交流による多様な自己と他者への理解」は、「災害や暴力の被害からの回復」にも大きな貢献をはたすことが示されます。
詩や演劇、音楽やダンスなど、「情動や感情の表現が多面的な自己を統合し受け入れ、他者と相互に交流する文化活動」を指します。「ごっこ遊び」や「ファンタジー」などで、自分とは異なる誰かの役割を演じることも例示され、学校の特別活動だけでなく子育てや地域の遊びの場面でも伝統があり、「情動と感情の交流による多様な自己と他者への理解」は、「災害や暴力の被害からの回復」にも大きな貢献をはたすことが示されます。
そして先生は、コロナ禍の中でこうした様々な活動が著しい制約を受けている今こそ、ストレスや不安を重ねる子どもや若者と関わるそれぞれの現場でどう補って工夫していくかが問われている、と指摘されました。
講演のまとめに入って片岡先生は、大学の附属小学校の校長をお務めになった時代の取り組みを紹介されました。希望する保護者と二学年の全児童を対象に毎年「子ども暴力防止プログラム」を実施され、その成果と課題を踏まえて、教職員と子どもたちに「リスペクト」を附属小の合言葉に!と宣言し、次第に浸透していった経過を述べられました。
「リスペクト」とは、他の人の気持ちを尊重する/行動の裏にはどんな気持ちがあったのかを想像する/しっかり相手の話を聞く/こうした基本にもとづくことです。子どもが暴力によらない他者への要求を身につけたり、親や教員がアイメッセージも添えて子どもの表明を傾聴することにもつながることです。
 関連して、ブレイディみかこさんの著作『ぼくはイエローでホワイトでちょっとブルー』が紹介されました。英国での生活と教育体験より、中学のシチズンシップ教育で「これからはエンパシーの時代!」と提示する授業の様子が紹介され、現代世界にとってもキーワードではないかと著者は述べられました。
関連して、ブレイディみかこさんの著作『ぼくはイエローでホワイトでちょっとブルー』が紹介されました。英国での生活と教育体験より、中学のシチズンシップ教育で「これからはエンパシーの時代!」と提示する授業の様子が紹介され、現代世界にとってもキーワードではないかと著者は述べられました。
「エンパシー」(empathy)とは「他者の感情や経験などを理解する能力」であり、「能力」(ability)が含まれる点で、その人の内側から出る感情や理解を示す「シンパシー」(sympathy)とは異なるものと、ブレイディさんは説明されます。
授業を受けた息子さんは、「エンパシー」とは「誰かの靴を履いてみること」だと回答したそうです。英国の社会が直面していた、「EU離脱」や「テロリズム」など重大な問題に対して、中学生がこれからの社会に必要な視点や行動について鮮やかな表現でイメージしたのです。
 片岡先生は、「エンパシーは能力だから学習によって育てられる」ことを指摘されました。そして現代の実践例として、『LGBT 社会は変わる?』という番組から、ある日本の高校で、性的マイノリティの立場にいる同級生の告白を受けた高校生のその後が紹介されます。性について語り合う会に生徒たちが集まるようになり、性差を前提とした従来の学校のあり方まで見直され、誰もが安心して生活できる学校像が模索されました。
片岡先生は、「エンパシーは能力だから学習によって育てられる」ことを指摘されました。そして現代の実践例として、『LGBT 社会は変わる?』という番組から、ある日本の高校で、性的マイノリティの立場にいる同級生の告白を受けた高校生のその後が紹介されます。性について語り合う会に生徒たちが集まるようになり、性差を前提とした従来の学校のあり方まで見直され、誰もが安心して生活できる学校像が模索されました。
次世代の若者や子どもは、多様性が強まる現代社会において、自分と違う立場の人びとや自分と異なる意見を持つ人びとを「心と肌の感覚」で受け入れる柔軟性に優れることが指摘されます。「他人の靴を履いて」みて他者の気持ちを想像できることは、国際社会でも、またどの世代の対人関係でもますます大事になっていることでしょう。
日本の学校教育がこれから「知識や認識」に偏らず、もっと「情動や感情」そして「エンパシーの能力」の発達を大事にする教育実践を豊かにしていいけるように願っています、と先生は説かれました。そして最後にコロナ禍の中で子どもの権利を守るために、どんな気持ちでいるのかしっかり声をかけ、耳を傾け、対話することが更に重要になっていると述べられました。
 短い休憩をはさんで質疑応答の時間をいただきました。まず、子どもの気持ちに寄り添う大事さを理解しつつも、しんどい児童や生徒の対応に悩み続ける親や教員へのメッセージをいただければとの要望に対して、「周囲の子どもが複数でその子を受け入れてくるようになると状況に変化がおきやすい」こと、「その子をめぐる先生方の様々な気づきや協議が大切になる」こと、「親の苦悩や背景を理解できてくると教員の伝え方も変わって両者の協力が広がりやすくなる」こと、「両親でその子の見方が違うとその子の振る舞いにも影響が出やすい」ことなど、いくつか実践的な助言がなされました。
短い休憩をはさんで質疑応答の時間をいただきました。まず、子どもの気持ちに寄り添う大事さを理解しつつも、しんどい児童や生徒の対応に悩み続ける親や教員へのメッセージをいただければとの要望に対して、「周囲の子どもが複数でその子を受け入れてくるようになると状況に変化がおきやすい」こと、「その子をめぐる先生方の様々な気づきや協議が大切になる」こと、「親の苦悩や背景を理解できてくると教員の伝え方も変わって両者の協力が広がりやすくなる」こと、「両親でその子の見方が違うとその子の振る舞いにも影響が出やすい」ことなど、いくつか実践的な助言がなされました。
関連して、「子ども理解のカンファレンス」のあり方についての質問には、いじめなどの事実の認知を強めるため「複数の学年ごとに独自の役割を持つ教員を配置した」例や、担任教員の不安に配慮した教員チームの協働やサポートのあり方が説明されました。また様々な意見や立場を尊重し合うと、「結局みんな考えが違うからまとまらないのは仕方ない」といった方向に行きやすい心配があるのではとの質問には、「自分はどんな立場に立ち、どんな願いを持っているのか」を各自が問い直し、対話によって一致点や合意を求める姿勢を忘れないことが大事ですと述べられ、問題に直面する人間の「人権はどうなっているのか」の視点にいつも立ち戻り解決策を考え合うことが大切ではないかと述べられました。
 そして「LGBTの課題に向き合う授業の実践例」についての質問に対しては、「性的マイノリティとは個別に多様なものであり、その子がいる前では扱いが難しいことも多い。いずれこの先どこかで出会う可能性は相当に大きいからこそ、その時に差別的な対応をしないようにするためにも「そういう人の靴を履いてみる」学びにより、エンパシーの能力を伸ばしていく」ことが大切ではないかと述べられました。そして「LGBT」と一括りにせず、「みんな独りひとりが多様な性を生きている」視点から、誰もが「自分は自分でいいんだ」「すべて含めて自分のことが好きだから」と安心して生きていける社会、楽しく支え合って暮らしていける社会を目指していきたいです、とのお言葉で講演を結ばれました。
そして「LGBTの課題に向き合う授業の実践例」についての質問に対しては、「性的マイノリティとは個別に多様なものであり、その子がいる前では扱いが難しいことも多い。いずれこの先どこかで出会う可能性は相当に大きいからこそ、その時に差別的な対応をしないようにするためにも「そういう人の靴を履いてみる」学びにより、エンパシーの能力を伸ばしていく」ことが大切ではないかと述べられました。そして「LGBT」と一括りにせず、「みんな独りひとりが多様な性を生きている」視点から、誰もが「自分は自分でいいんだ」「すべて含めて自分のことが好きだから」と安心して生きていける社会、楽しく支え合って暮らしていける社会を目指していきたいです、とのお言葉で講演を結ばれました。
長文をお読みいただいてありがとうございました。この続きは次回の通信で紹介させていただきます。