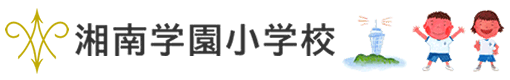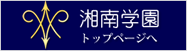「読書と体験の子どもキャンプ」レポート4
4日目のレポートです。
【Yさんのレポート】

実際の作品
しばらくすると、湘南学園の先生が来て、2つ質問をしてきました。1つ目は、「この、どこでも図書館に字の読めない子(1年生)が来たらどう対応するか」でした。これは、読み聞かせをすると答えました。2つ目は、「なやみをもった人がきたらどうするか」でした。これは、なやみを聞いてあげて、おすすめの本をわたしてあげると答えました。
発表が終わると、大学の教じゅである、植村八潮先生の講評がありました。植村先生は、私の班の作品を見て、「本の表紙をひらいたとき、題名がかいてあるページを、本のとびらといい、これをひらくことによって本の世界に入ることができる。この作品は、そういうことがよく分かる」と言っていました。
私は、本を読んでいるときに、主人公の気持ちになって考えるのが好きでしたが、この講評を聞いて、その本の世界を想像するのもいいと思いました。
その後、閉会式をして、みんなで軽食のサンドウィッチを食べました。すると、テーブルに大量のうまいぼうが運ばれてきて、これは、きのうのクイズ大会の参加賞だよ、といわれました。みんな3本ずつもらいました。交流の時間が終わると、みんな荷物をまとめて、帰るしたくを始めました。そして、最後に友達のカメラで写真をとって、解散しました。私は、たった数日間でしたが、友達がたくさん出来ました。
キャンプを終えて、私は読書に対する考えが変わりました。今まで読書は、知識を深めるためのものと思っていましたが、この体験を通して、読書は知識を深めるとともに、心を豊かにするものと思いました。このキャンプは、私に読書の楽しさを教えてくれました。このきかくに参加させていただいて、私は色々なことを感じました。
今の湘南学園の図書室は、たくさんの本と読む場所があっていいと思います。私は、このワークショップで、好きな空間で本が読める図書館を作り上げました。そして、本を読む空間を変えることで、本に集中できたり、本の世界に入り込むことができると思いました。だから、読書の空間づくりは大切だと思います。
学園の図書室も、この空間づくりを取り入れてはどうでしょうか。

湘南学園小学校メディアセンター
1.海のイメージの場合は、床を砂浜のうすだいだいの色にして、天井には、太陽の絵をかき、かべには、海の絵をかざります。波の音のBGMも流します。
2.森のイメージの場合、木にかこまれているように、木の絵をたくさんかいて、うす暗い空間にして手元にライトを置き、本が読めるようにします。
3.雲の上の場合、ゆかにクッションをたくさん置き、かべに雲や鳥などの絵をかいて、天井には、太陽の絵をかきます。
このように本を読む空間を変えることで、本に興味のない人も本を読んでみようという気持ちになると思います。また本が好きな人は、いつもとちがう空間で本を読むことで、ちがった本の楽しさを発見できると思います。
本は、考える力をつけ、想像力を豊かにしてくれる存在だと私は思います。一人でも多くの児童が本を楽しむことができるようになれば、たいいく表現まつりや音楽会は、より一層、み力的な内容になることと思います。
本は、私にとって、心を大きく育ててくれる大切な存在です。(おわり)
【Mさんのレポート】

実際の作品
これから発表だからトイレに行こうと思って、レセプションホールから出て、ふと受付の方をみると大きいいつものカメラを持った湘南学園の先生がいたので、びっくりして
「あ! 先生!」
て言ったけど、気付かないみたいでした。そのあと来たお母さん達は気付きました。
発表開始!! 私はかなりきんちょうしたけど、あんまりまちがえませんでした。よかった…。
「近くに行って本を見ていいですよ」
という時間に、子どもは面白そうな本を探すけど、大人は上の段を指さして、くすくす笑います。その指の先にあるのは「新庄のコトバ」。野球選手だった新庄さんの言葉を集めた本みたいです。この本の表紙に新庄さんの顔がデカデカと書いてあるんだけど、
「この顔って、千原ジュニアさんに似てるよね~」
ていう一言で大ウケしたり、人の笑いをさそってくれる本みたいです。
私達の発表終了! 次はちがう班の学校図書館を見に行きます。ほかの班の図書館も面白かったけど、私の所が一番現実味があったんじゃないかと思います。
発表の後はお昼ごはん。食べ終わるとすぐに帰る人もいます。幸い私とAちゃんは、帰るのが最後の方だったので、ずーっとしゃべっていました。話してたことは、
「すぐ手紙送るからぁ」
「帰ったら書くよ~」
「ずーっとずーっと送り続けるよ」
手紙の事ばかり。一緒に建物を出ました。最後、お父さんの大きいカメラで写真を1枚とってもらいました。キャンプで一番最後にしたことは『約束したこと』です。
ついしん 本当に今も手紙を交かんしています。(おわり)