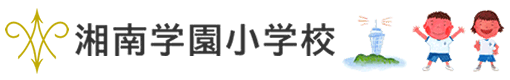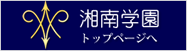🐟 3年生 社会科見学レポート:片瀬漁港へ行きました! 🌊


9月29日、3年生は社会科の学習で「海辺で働く人」について学ぶため、片瀬漁港へ見学に行ってきました! 教室で学んでいたことが、実際に自分の目で見ることができ、みんな興味津々でした。
⚓ 漁港の「へえ〜」がいっぱい!
漁港には、漁師さんたちが安全に、そして効率よく働くための工夫がたくさんありました。
漁船と泊地
漁船が止まっている場所は「泊地(はくち)」と呼ばれ、まるで漁船のお家のようでした。漁船は、なんと夜中の1時から漁へ出発することもあるそうです!漁船は、約20トンもある大きなもので、魚を積み降ろしするためのクレーンも乗っています。
灯台と漁の方法
港には、白灯台と赤灯台があり、船が安全に進むための目印になっています。また、片瀬漁港では主に大型定置網という漁を行っており、1日で600kgもの魚が捕れると聞いて、みんなその多さに驚いていました!
防波堤と消波石
私たちがよく知っている「テトラポット」とは違い、片瀬漁港では「消波石(しょうはせき)」という大きな石が使われていました。これは、船を守るために波の勢いを弱める役割があるそうです。


船揚場でのメンテナンス
船揚場(ふなあげば)では、船に付いたフジツボを取り除いたり、ペンキを塗り直したりする作業が行われています。漁師さんの仕事は、海で魚を捕るだけでなく、陸地で網の手入れなどの大切な仕事もあるんですね!
 🧊 捕った魚の行方は?
🧊 捕った魚の行方は?
漁で捕れた魚は、すぐに新鮮な状態を保つための作業が行われます。
荷捌きと選別
「荷捌き施設」では、捕れた魚を種類ごとに分ける作業が行われます。ここでは、魚の種類を自動で分ける「魚介類自動選別機」が活躍するそうです!
鮮度を守る氷の秘密
「製氷貯氷施設」では、魚を冷やすための氷が作られていました。
ボタンを1回押すだけで500kgもの氷が出てくるそうです!
作られた氷は平べったく、角が丸い形をしていました。
この丸い氷を使うのは、魚の体に傷が付かないようにするための漁師さんの優しい工夫だそうです。
✨ 見学を終えて
今回の社会科見学を通して、海の仕事はたくさんの人が協力し、さまざまな道具や工夫が使われていることがよく分かりました。漁師さんたちの苦労や、美味しい魚を届けてくれるための努力を知ることができ、とても貴重な体験になりましたね。
片瀬漁港の皆様、お忙しい中、貴重なお話をたくさん聞かせていただき、ありがとうございました!