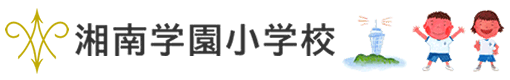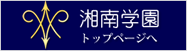修学旅行紀

6年生と奈良・京都へ修学旅行に行ってきました。
知らぬ土地で初めての風景に出会い、歴史と物に触れ、地元の人と話をすることは旅の原点であり醍醐味です。旅をすれば机上で知ったこととは違う新しいことにたくさん出会えます。
子どもたちは、明日香の地で今は姿無き悠久なものに思いを馳せました。金峯山寺では金剛蔵王大権現のたたなづく青が、およそ1300年前とは思えないほど鮮やかに残っているのを目の当たりにしました。玉虫厨子に僅かに残る金緑に輝く翅しかり。世界最古の木造建築である法隆寺も、その存在感は決して威圧的ではなく、あくまでも清静で温もりがあることを見て感じて知りました。東大寺を見上げた男の子の気づきは、ベテランのガイドの方も知らないことでした。豊臣秀吉が歩いた廊下に自分の足を重ねられるのも、今自分がここにいるからです。
そして、予期せぬことが起るほど旅は楽しくなり深まります。京都の宿の然林房が中学3年生の修学旅行で自分が泊まった宿だと知ったときから、子どもたちと訪れる京都がより思い出深きものになりました。そして今年も、子どもたちだけの予期せぬ楽しみが、僕等が知らないところであったことでしょう。




6年生とともに旅をするのは楽しいものです。
大興奮した新幹線のスピード、鹿に頭突きされた痛み、もうお寺は充分と嘆く顔、心を奪われた金閣寺の煌びやかな姿、叱られてしょげる表情、タクシー行動から帰ってきた時の笑顔、みんなで箸を伸ばしたすき焼き、ガイドさんの話をノートに記す姿、カメラに向かってのピースサイン。
子どもと過ごした修学旅行の思い出は、映画のカットのように断片的に瞼の裏に焼き付いています。今となっては、人に話してもストーリーのないものですが、もしかしたら・・・
こういうのを心に残ると言うのでしょう。
こういうのを一生ものと言うのでしょう。
子どもたちにとって、いつの日か断片的になってしまう思い出も、何かの折に奈良や京都のことが脳裏を掠めたとき、小学校時代の修学旅行の一場面がふと蘇ることがあるはずです。それがきっと、自分の心に残る一生の思い出になったということなのでしょう。
「勝手にできる自分でつくる。」
大徳寺大仙院の住職の、「そこまで鍛錬すべし」という心に残る言葉です。
紅葉の盛りを向かえた奈良・京都は、まさに「うましうるわし」でした。