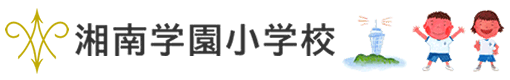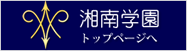幼保小連携の視点から考える湘南学園小学校

小学校からみた幼稚園園舎と園庭
いま、全国の幼稚園、保育園はおしなべて「認定子ども園」をめぐる対応の渦中にあります。それぞれに歴史と伝統を築いてきた各園では、自園の方向性についてどのような選択をするにしても改革を含めた大きな決断が求められる状況にあるといってよいでしょう。発達や学びの連続性をふまえた円滑な接続が幼児教育の大切さとして重視されるなかで、魅力ある改善や充実が求められています。
その具体的内容についてはよく指摘されるところですが、主に異年齢交流と教員間交流の2つをあげられます。前者については、小学校生活の体験機会をつくるなど異年齢交流をイベント的なものから教育課程内に位置づけて取り組むこと、後者については、異年齢交流を通じてスムーズな接続から、接続期間を設定し教員の教育指導や対応のあり方をも視野に教員連携を図ることです。幼稚園と小学校の教員同士が、それぞれに子ども観や指導方法などを交流し学び合い、指導の一貫性や連続性を協同的作業のなかから作り上げていくことです。また資格的側面からみますと、幼稚園教諭免許・保育師免許、小学校教諭免許など複数の免許を持つことで、子どもへの理解が深まるのではとの指摘もなされています。加えて最近の調査データをみると、指導要録は国公立の約8割、私立の約6割が小学校に送付しているとのことです。指導要録の送付と共に、教員相互の子どもの理解を深めるための話し合いが求められそうです。
幼保小連携は小中連携にもつながり、中高一貫とも相まって、まさしく総合学園としての湘南学園が現在重視して取り組んでいる「連携・接続・一貫教育の強化」の指針そのものといえます。立地条件としても、湘南学園幼稚園・小学校・中高は隣り合わせに配置されており、「連携・接続・一貫教育の強化」を体系的に取り組む上でも大変好都合な環境にあります。

小学生の劇を見学に来た園児たち
現在、公立小学校もそれぞれの特色を打ち出し、学校改革を通じて新しい魅力づくりに腐心しています。私たち私学教育に携わる一員として、幼保小連携の視点を生かした公立小学校などの取り組みから、何を学び考えるのかを、双方向において交流する機会を得られたことは大変に意味あることでした。