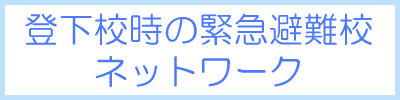防災対策
◎湘南学園がめざす「防災・減災」教育~「湘南学園ESD」の一環として
2011年3月11日に発生した東日本大震災。その記憶がまだ生々しかった頃、高2研修旅行の「東北コース」で被災地を訪れた生徒たちは、現地の同世代から、「あなたたちの地域は『未災地』です」という話を伺ったそうです。「今はまだ、大規模な災害に遭っていないけれども、災害大国・日本に住んでいる限り、どこにいようが、いつか必ず、大規模な災害に見舞われる。だから、『備え』が大切なのだ」ということを教えられたのだと思います。
東日本大震災から10数年。その甚大な被害状況を、リアルに感じることができる生徒は年ごとに少なくなっていきます。しかし、その中でも、「未災地」で生活している我々は、「備え」を、そして「もし災害が起きたらどう取り組むのか」という“問い”への模索を、怠ることはできません。
湘南学園は、海岸線から約1.2㎞離れたところにあります。県の想定では、津波が発生しても、湘南学園までは届かないであろうとされています。しかし、「想定外は十分にありえる」という認識のもと、湘南学園では、大地震・大津波に対応した防災対策を重視しています。


1、避難訓練について
- 震度6.5強の地震に耐えられる構造設計になっている校舎は、海抜7~8mの土地に建っており、屋上まで昇れば、海抜約20mの高さとなります。従って、津波警報が発令された時は、校舎の最上階または屋上への避難をすることになります。
- 2024年度からは、以下のように設定します。
- 年度初めの4月に、新学年の避難ルートを確認するための訓練を行う。
- 年度内のどこかで事前予告なしの訓練を行う。
2、非常備品について
- 3日間分の非常食・飲料水や毛布といった必要最低限の備品だけではなく、携帯トイレ・LED懐中電灯・さらには自家発電機や災害用照明も備えています。また、災害対応自動販売機もいくつか設置されています。今後も非常備品の充実化は進めていきます。
3、「減災」という視点をもつこと
- 大規模災害が発生すると、その被害は、学校だけにとどまらず、地域全体に及びます。「自助・共助・公助」でいうところの、「共助」<地域の方々と助け合っていくこと>をより重視しながら、被害を少しでも減らせるようにしていこうという視点も必要です。藤沢市の避難施設にも指定されている湘南学園ですが、コロナ禍の前には、生徒の発案で、「生徒」「地域住民」「市職員」「教員」たちが一堂に会し、地域防災のことについて語り合う機会も設けられました。コロナ禍が落ちついてきた段階で、このような動きを、生徒たちと共に、さらに活発化・深化させ、継続していくことを目指していきます。
4、「登下校時の緊急避難校ネットワーク」について
- 神奈川県と東京都の私立小中高校は連携して「登下校時の緊急避難校ネットワーク」という取り組みを行っています。この取り組みは、登下校の時間帯に震災が発生し、首都圏の交通機関がストップするような状況においても所在不明の生徒を極力出さないよう、帰宅困難生徒の保護とその情報の伝達について学校間で協力し合うというものです。
ユネスコスクール、つまり「ESD(持続可能な開発のための教育)の拠点」として位置付けられる湘南学園にとって、「防災・減災」について考え、学び、実践していくことは、「持続可能な社会のつくり手を育成する」ための重要な柱になるものであると考えています。
▼ 登下校時の緊急避難校ネットワーク